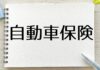国内における自動運転機能の審査期間を大幅短縮し、これまで11カ月を要していたが2カ月での審査完了を目指すようだ。改正道路交通法によりレベル4が解禁されてから1年が経過したが、レベル4認可は4件、サービスを提供する特定自動運行
許可は1件にとどまっている。その背景には、こうした審査期間も大きく影響していそうだ。
一方、海外では米Waymoの自動運転タクシーが週5万回超のライドを達成している。この差を少しでも埋めるべく、官民総出で取り組みを加速してほしいところだ。
2024年5月の10大ニュースを振り返り、国内外の取り組みに触れていこう。
記事の目次
- ■ガストのロゴ、ホンダ車が「進入禁止」と勘違い(2024年5月1日付)
- ■自動運転トラック、新東名高速で「高精度地図なし」実証 ティアフォー(2024年5月6日付)
- ■無人航空機の衝突回避、「日本案」が国際標準化(2024年5月6日付)
- ■トヨタの成長投資、5,000億円増の「1.7兆円規模」に AIや自動運転開発に注力(2024年5月8日付)
- ■自動運転、天敵は「路上駐車」!手動介入要因の47% 鳥取で実証(2024年5月10日付)
- ■自動運転車にLED攻撃、標識の認識を「無効化」 脆弱性が浮上(2024年5月13日付)
- ■テスラ、「自動運転の松葉杖」呼ばわりしたLiDARの購入発覚!方針転換か(2024年5月15日付)
- ■Googleの自動運転タクシー、すでに「週5万回規模」運行 3都市での実績値(2024年5月18日付)
- ■ライドシェアで自民党分裂!タクシー会社限定に幹事長「おかしい」(2024年5月20日付)
- ■大幅短縮!自動運転の審査期間、平均11カ月を「2カ月」に ついに国も本腰?(2024年5月21日付)
- ■【まとめ】国内勢の取り組み加速に期待
■ガストのロゴ、ホンダ車が「進入禁止」と勘違い(2024年5月1日付)
ホンダセンシングが、天下一品に続きガストの企業ロゴも進入禁止と誤認するケースが報告されたようだ。過去には、日産のプロパイロットがENEOSのロゴを誤認識したこともあったという。「道路標識認識機能」が抱える問題は、想像以上に根深いのかもしれない。
ガストの看板は、赤地に白い文字で「ガスト」と入っており、その上部に黄色で「Caféレストラン」と記載されている。ENEOSの看板、赤系の渦柄に白文字で「ENEOS」と入っている。看板は四角いが、渦部分を「赤丸」に認識していたのかもしれない。
天下一品のロゴを「車両進入禁止」と誤認するのはわかるが、さすがにガストやENEOSは……というのが率直な感想ではなかろうか。認識精度に幅を持たせたのかもしれないが、さすがに緩過ぎだろう。
SNSにおける顧客の声に応え、標識認識システムが改変されることを望みたいところだ。
【参考】詳しくは「ガストのロゴ、ホンダ車が「進入禁止」と勘違い」を参照。
ガストのロゴ、ホンダ車が「進入禁止」と勘違い | 自動運転ラボ https://t.co/0MI2iYT1Wp @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) April 30, 2024
■自動運転トラック、新東名高速で「高精度地図なし」実証 ティアフォー(2024年5月6日付)
自動運転分野で活躍するティアフォーが、高速道路におけるトラック向けの自動運転システム開発に乗り出した。高精度地図を要しない自動運転を実現するという。
2024年度から新東名高速道路で実証を開始し、開発成果はリファレンスデザインとして商用車メーカーに提供し、早期導入を支援していく。
自動運転技術には、独スタートアップdriveblocksの認識技術を活用するという。同社は自動運転車によるサーキットレス「ロボレース」で実績を有するエンジニアが立ち上げたスタートアップで、高精度地図に依存することなく物体を確実に検出して周囲を認識し、自律走行を実現する「Mapless Autonomy Platform(マップレス・オートノミー・プラットフォーム)」の開発を進めている。
このマップレス技術がレベル5に通じるものなのかどうかは不明だが、革新的な技術であることに違いはない。ティアフォーの自動運転システムが新たな境地に達するのか、要注目だ。
【参考】詳しくは「自動運転トラック、新東名高速で「高精度地図なし」実証 ティアフォー」を参照。
自動運転トラック、新東名高速で「高精度地図なし」実証 ティアフォー | 自動運転ラボ https://t.co/UgBrRLtqHg @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 5, 2024
■無人航空機の衝突回避、「日本案」が国際標準化(2024年5月6日付)
無人航空機の衝突回避に関し、日本発の提案が国際規格の策定に大きく貢献しているようだ。2023年に衝突回避に関する改定版に採択されたほか、日本無線と三菱総合研究所が取りまとめた技術報告書「ISO/TR 23267」もこのほど公開された。
無人航空機の衝突回避6ステップで使用されるハードウェアとソフトウェアなどを提示した内容で、この技術報告書により、これまで開発者らが個別に進めてきた衝突回避システムに対し、共通概念を提供することが可能になったという。
無人航空機は、農業や測量をはじめ、今後は物流などさまざまなシーンで活躍することが予測される。空は広いとは言え、同時に飛行する機体が増えれば増えるほど衝突する危険性は増し、その被害は地上における事故を凌駕しかねない。
空飛ぶクルマをはじめ、ドローンもグローバル化が進んでいる。安全面に関しては、国際的に統一されたルールのもと運用されることが望ましいのは言うまでもないだろう。
【参考】詳しくは「無人航空機の衝突回避、「日本案」が国際標準化」を参照。
無人航空機の衝突回避、「日本案」が国際標準化 | 自動運転ラボ https://t.co/8H6yDGA8kI @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 5, 2024
■トヨタの成長投資、5,000億円増の「1.7兆円規模」に AIや自動運転開発に注力(2024年5月8日付)
トヨタの2024年3月期(2023年4月〜2024年3月)の通期決算が発表された。売上高は前期比21.4%増の45兆953億円に達し、利益は国内企業未踏の5兆円を突破した。事業環境が安定化し、収益構造強化の取り組みが結実した成果としている。
次期2025年3月期は、連結営業利益を前期比-7,000億円の4兆3,000億円 と予測している。人への投資とモビリティカンパニーへの変革に向けた投資として、成長領域への投資を1.7兆円(前期比5,000億円増)とするようだ。
佐藤社長は「『トヨタらしいソフトウェア・ディファインド・ビークル』の実現に向け、この1年は車載OS「アリーン」の開発やソフトウェア基盤の整備に注力してきた」とし、「これから、生成AIなどの活用により自動運転も含めてモビリティの進化を実現していきたい。AI関連の投資も拡充していく」と語っている。
ハイブリッドに軸を置いたトヨタの全方位戦略は、湧き上がるEV(電気自動車)ブームの中でかえってその価値を高めた。おそらく、自動運転技術においても同様の考え方で、急がず慌てずじっくりと社会に必要とされる技術の実装を進めていくのではないだろうか。引き続き今後の動向に注目したい。
【参考】詳しくは「トヨタの成長投資、5,000億円増の「1.7兆円規模」に AIや自動運転開発に注力」を参照。
トヨタの成長投資、5,000億円増の「1.7兆円規模」に AIや自動運転開発に注力 | 自動運転ラボ https://t.co/CdkBpGEeOn @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 8, 2024
■自動運転、天敵は「路上駐車」!手動介入要因の47% 鳥取で実証(2024年5月10日付)
鳥取県鳥取市内で2024年1~2月に行なわれた自動運転実証の成果報告書によると、手動介入は691回発生し、その要因の半数近くが「路上駐車」だったという。
たかが路上駐車と思われるかもしれないが、走行車線にまたがる形で駐停車する車両を回避するのは大変だ。交通量が多い片側複数車線の道路で、駐車車両をかわすタイミングを見失って固まっているドライバーは、初心者やペーパーを含め相当な数に上る。
現時点における自動運転技術がなかなか対応しきれないのも仕方のない部分がある。交通量が多ければなおさらで、ちょっとやそっと技術が向上したくらいでは対応しきれないだろう。
これは多くの自動運転車に共通する問題だ。自動運転車の走行区間においては、厳密に駐停車を禁止するなどの対策も必要となりそうだ。
【参考】詳しくは「自動運転、天敵は「路上駐車」!手動介入要因の47% 鳥取で実証」を参照。
自動運転、天敵は「路上駐車」!手動介入要因の47% 鳥取で実証 | 自動運転ラボ https://t.co/OYv7kNGBNZ @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 9, 2024
■自動運転車にLED攻撃、標識の認識を「無効化」 脆弱性が浮上(2024年5月13日付)
シンガポールの南洋理工大学などに所属する研究チームが、LEDを用いて自動運転システムの画像認識機能を誤認させる攻撃方法について警鐘を鳴らした。
LEDで道路標識に特定のパターンの光を照射することで、画像認識ソフトウェアが標識を正常に認識できないようにする技術で、人間には攻撃が行われているか確認不能という。
このようなセキュリティの穴を見つける研究は、これまでもいろいろ実施されている。道路標識関連では、標識に特定パターンのシールを貼ることで別の標識に誤認識させるものもある。
こうしたセキュリティ上の脆弱性は、悪用される前に早期対策する必要がある。今のところ表立って自動運転車をターゲットに危害を加える動きは出ていない模様だが、今後はいたちごっこが本格化する可能性が高い。
社会を変革させるほどの技術が、悪意で阻害されることがあってはならない。安全性向上に向け、セキュリティ面での研究開発がいっそう重要性を増してくることになりそうだ。
【参考】詳しくは「自動運転車にLED攻撃、標識の認識を「無効化」 脆弱性が浮上」を参照。
自動運転車にLED攻撃、標識の認識を「無効化」 脆弱性が浮上 | 自動運転ラボ https://t.co/HsPjG5SUcE @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 12, 2024
■テスラ、「自動運転の松葉杖」呼ばわりしたLiDARの購入発覚!方針転換か(2024年5月15日付)
自動運転開発を進める米テスラが、米Luminar TechnologiesからLiDARを購入したことが判明した。イーロン・マスク氏は自動運転におけるLiDAR不要論の急先鋒として知られるが、ついに心変わりしたのだろうか。
マスク氏はかねてより「自動運転における目はカメラで十分であり、高価なLiDARは不要」といった旨を発言しているLiDAR不要論者だ。2021年にLuminar Technologiesに接触した旨報じられたが、当時マスク氏は黙秘し、Luminar Technologiesもノーコメントを貫いていた。
しかし、Luminar Technologiesの2024年第1四半期決算報告書により「テスラは第1四半期最大の顧客で、収益の10%以上を占めた」と報告されたのだ。
SNS「X」では、マスク氏にコメントを求める投稿が寄せられているようだが、今のところ同氏は明確な返答を避けている。
これまでにも、テスラのテスト車両にLiDAR搭載モデルが存在することが報じられるなど、LiDARの可能性を排除しきっていないものと思われるテスラ。ロボタクシーに向けたビジョンを8月に発表する予定もあり、自動運転実現に向け方針を変えた可能性も考えられる。結末が気になるところだ。
【参考】詳しくは「テスラ、「自動運転の松葉杖」呼ばわりしたLiDARの購入発覚!方針転換か」を参照。
テスラ、「自動運転の松葉杖」呼ばわりしたLiDARの購入発覚!方針転換か | 自動運転ラボ https://t.co/TsKwF8UYzz @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 14, 2024
■Googleの自動運転タクシー、すでに「週5万回規模」運行 3都市での実績値(2024年5月18日付)
グーグル系Waymoが、週5万回以上自動運転タクシーを提供しているとSNS「X」で発表した。セーフティドライバー付きの運行も含んでいそうだが、それにしてもなかなかの数字だ。
同社は現在カリフォルニア州サンフランシスコとロセンゼルス、アリゾナ州フェニックスの3都市でサービス提供している。最新状況がつかみにくいため正確な情報は不明だが、フリートは1,000台規模に達している。
1,000台と仮定すると、1台当たり1日に約7回客を輸送している計算となる。そう考えると少なく思えるが、恐らく常時1,000台が稼働しているわけではないため、実際に「出勤」した1台当たりのライド数はもう少し多いものと思われる。
事業は相当な規模に達しているが、そろそろ気になってくるのが損益分岐点だ。Waymoはまだ投資段階であり、積み重なり続ける研究開発費の影響で赤字決算から脱却できていないものと思われるが、仮にサービス事業者が1,000台の無人自動運転タクシーを導入した場合、どの程度稼働すれば単年度収支は均衡し、そして何年でイニシャルコストを回収できるか……と言った具合に、ビジネス面での目安をそろそろ示すことができるのではないだろうか。
自動運転車の価格や維持管理費用などに左右されるが、そうした点も踏まえた上でのビジネス的なポテンシャルを知りたいところだ。
【参考】詳しくは「Googleの自動運転タクシー、すでに「週5万回規模」運行 3都市での実績値」を参照。
Googleの自動運転タクシー、すでに「週5万回規模」運行 3都市での実績値 | 自動運転ラボ https://t.co/bflMxy2phg @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 17, 2024
■ライドシェアで自民党分裂!タクシー会社限定に幹事長「おかしい」(2024年5月20日付)
自民党の幹事長である茂木敏充氏が、日本型ライドシェア事業(自家用車活用事業)の制度に関し、ネットメディアでダメ出ししたようだ。
茂木氏は日本型ライドシェアについて「(運行可能なのがタクシー会社限定は)おかしいと思う」「考え方が業界目線。顧客目線じゃない」「全面的に改善すればよいが非常に動きが遅い」などと評した。明確に本格版ライドシェアを支持する発言こそなかったものの、「日本は慎重過ぎる。もっとチャレンジすればよい」とも話しており、解禁議論に前向きな様子だ。
本格ライドシェア解禁をめぐっては、一部政党を除き与野党とも内部で意見が分かれているものと思われる。自民党はかつてライドシェア導入を阻止する立場にいたが、潮目が変わってきたようだ。
それでも反対派勢力も根強い。解禁に向けた法案が提出されても、それがすんなりと決議されるかどうか、非常に計算しづらい状況だ。まずは6月に取りまとめられる予定の案でどのような方針が示されるのか。そして、それを受け各国会議員がどのような態度を示すか。要注目だ。
【参考】詳しくは「ライドシェアで自民党分裂!タクシー会社限定に幹事長「おかしい」」を参照。
ライドシェアで自民党分裂!タクシー会社限定に幹事長「おかしい」 | 自動運転ラボ https://t.co/ro8jhViQur @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 19, 2024
■大幅短縮!自動運転の審査期間、平均11カ月を「2カ月」に ついに国も本腰?(2024年5月21日付)
国土交通省、経済産業省、警察庁が、自動運転の審査に必要な手続の在り方を見直し、審査期間の大幅短縮化を図るようだ。これまで平均11カ月要していた審査を最短2カ月での完了を目指す方針だ。
平均11カ月かかっていることにまず驚きだ。車両や走行の安全性を確認するのに8カ月、運輸手続きに1カ月、都道府県警察手続きに1.5カ月を要しているという。審査に当たる国土交通省や警察庁にとって自動運転は未知の領域であり前例が乏しいため、一定程度時間を要するのは理解できるが、さすがに11カ月は長過ぎる。審査を終えるころには、その自動運転システムは次のバージョンを迎えているのでは……と危惧してしまう。
こうした課題解決に向け、審査内容や手続、様式などの明確化や、過去の審査事例の公表・共有などを行うことで審査を円滑化するという。実際どこまで効果が上がるかは不明だが、自動運転の社会実装を加速させるには必要不可欠となる取り組みだ。
【参考】詳しくは「大幅短縮!自動運転の審査期間、平均11カ月を「2カ月」に ついに国も本腰?」を参照。
大幅短縮!自動運転の審査期間、平均11カ月を「2カ月」に ついに国も本腰? | 自動運転ラボ https://t.co/WjM83PDvQR @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 20, 2024
■【まとめ】国内勢の取り組み加速に期待
Waymoが着実に実績を積み重ねる一方、日本国内勢は実質的に実証段階から抜け出せていないのが現状だ。2024年度中に無人サービスがいくつ誕生するか、期待を込めて各社の取り組みに注目したい。
6月は、本格ライドシェアに向けた取りまとめが発表される予定となっている。引き続き、自動運転をはじめモビリティに関するさまざまな動きをしっかりチェックしていこう。
- 【2024年4月の自動運転ラボ10大ニュース】日本版ライドシェア事業がスタート
- 【2024年3月の自動運転ラボ10大ニュース】アップルが自動運転開発を断念
- 【2024年2月の自動運転ラボ10大ニュース】トヨタがついに自動運転サービス実証に着手
- 【2024年1月の自動運転ラボ10大ニュース】車載半導体開発が国内でも加速
- 【2023年ランキング】自動運転ラボ、読まれた記事トップ10
- 【2023年12月の自動運転ラボ10大ニュース】日本政府のライドシェア方針にがっかり……
- 【2023年11月の自動運転ラボ10大ニュース】米Cruiseが無人タクシー中止 その余波は?
- 【2023年10月の自動運転ラボ10大ニュース】北米でレベル3まもなく始動
- 【2023年9月の自動運転ラボ10大ニュース】自動運転支援道の先行導入地域が明らかに
- 【2023年8月の自動運転ラボ10大ニュース】トヨタが中国で自動運転車量産へ
- 【2023年7月の自動運転ラボ10大ニュース】Uberの配車プラットフォームに開発勢が殺到?
- 【2023年6月の自動運転ラボ10大ニュース】デジタル庁が新ロードマップ策定に着手
- 【2023年5月の自動運転ラボ10大ニュース】国内初の特定自動運行認可
- 【2023年4月の自動運転ラボ10大ニュース】テスラに新たな噂
- 【2023年3月の自動運転ラボ10大ニュース】海外では勝ち組と負け組が鮮明に……?
- 【2023年2月の自動運転ラボ10大ニュース】新体制に向けトヨタが組織変革
- 【2023年1月の自動運転ラボ10大ニュース】レベル3~4計画が次々
- 2022年「空飛ぶクルマ」10大ニュース!国内ベンチャーも躍進
- 2022年「MaaS」10大ニュース!海外展開に向けた動きも
- 【国内版】2022年「自動運転」10大ニュース!レベル4解禁へ
- 【海外版】2022年「自動運転」10大ニュース!社会実装に勢い
- 【2022年11月の自動運転ラボ10大ニュース】Argo AI停止、SBGはArmに注力
- 【2022年10月の自動運転ラボ10大ニュース】モービルアイがIPO申請、業界最大規模の上場へ
- 【2022年9月の自動運転ラボ10大ニュース】日本初の次世代モビリティ専門職大学が認可
- 【2022年8月の自動運転ラボ10大ニュース】日本初の空飛ぶタクシー向けの駅が判明?
- 【2022年7月の自動運転ラボ10大ニュース】レベル5開発のTURINGが資金調達
- 【2022年6月の自動運転ラボ10大ニュース】レベル4市販車発売計画が明らかに
- 【2022年5月の自動運転ラボ10大ニュース】ホンダに続くレベル3が登場!
- 自動配送ロボットが次のフェーズへ!2022年4月の自動運転ラボ10大ニュース
- 870万円で無人タクシー製造!2022年3月の自動運転ラボ10大ニュース
- 自動運転タクシーの実用化が世界で加速!2022年2月の自動運転ラボ10大ニュース
- 自家用レベル4計画が明らかに!2022年1月の自動運転ラボ10大ニュース
- 2021年の「空飛ぶクルマ」10大ニュース!
- 2021年の「自動運転」10大ニュース!
- 【2021年11月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2021年10月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2021年9月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2021年8月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2021年7月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2021年6月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2021年5月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2021年4月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2021年3月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2021年2月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2021年1月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 自動運転ラボ、2020年に読まれたニュース記事ランキング!
- 【2020年12月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2020年11月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2020年10月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2020年9月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2020年8月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2020年7月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2020年6月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2020年5月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2020年4月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2020年3月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2020年2月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2020年1月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 2019年に読まれた「解説記事」ランキング
- 2019年に読まれた「コラム」ランキング
- 【2019年12月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2019年11月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2019年10月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2019年9月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2019年8月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2019年7月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2019年6月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2019年5月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2019年4月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2019年3月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2019年2月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2019年1月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 自動運転・コネクテッドカー・MaaS系ニュースで2018年に注目を集めたニュースを振り返り!
- 【2018年11月分】自動運転・MaaS・AIの最新ニュースまとめ
- 【2018年10月分】自動運転・ライドシェア・AIの最新ニュースまとめ
- 【2018年9月分】自動運転・ライドシェア・AIの最新ニュースまとめ
- 【2018年8月分】自動運転・ライドシェア・AIの最新ニュースまとめ
- 【2018年7月分】自動運転・ライドシェア・AIの最新ニュースまとめ
- 【2018年6月分】自動運転・ライドシェア・AIの最新ニュースまとめ