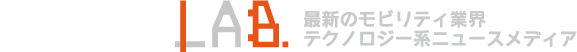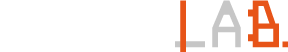国内ではソフトバンクとトヨタ自動車との提携や、米ウーバーや中国DiDiなどのタクシー配車サービス参入などさまざまなニュースが流れ、海外ではグーグル系ウェイモによる自動運転タクシーの実用化で幕を閉じた2018年。コネクテッドカーの普及や空飛ぶクルマの開発なども大きな話題となった。
続く2019年は、果たしてどのような年になるのか。国内外とも2020年を一つのターニングポイントに据えており、来年に向けたさまざま取り組みが表面化してくる可能性が高そうだ。そこで今回は、2019年中に起こりそうな変化やモビリティ業界の潮流について推測してみる。
記事の目次
■レベル3搭載の市販車、国内でも発表へ
一定条件下で自動運転が可能となる自動運転レベル3(条件付き運転自動化)。独アウディが生産モデルとして世界で初めてその技術を搭載した量販車「Audi A8」を2017年に発売したものの、各国の法整備や国際基準の策定が追い付かないため、自動運転レベル2(部分運転自動化)搭載車両として販売されているのが現状だ。
法整備面では、ドイツ連邦議会が2017年に道路交通法改正案を可決し、同年6月に施行。自動運転レベル3相当の自動運転実用化を認めることを決定し、他国に先行するものと思われたが、公道走行には、国連欧州経済委員会の下にあるWP29(自動車基準調和世界フォーラム)において当該機能に係る国際的な車両安全基準の策定を要するため、実現には至っていない。
米国では、従来自動運転車に係る規制を各州が独自に法制化してきたが、州ごとに要件が異なるなどばらつきが見られるため、米国統一ルールとして連邦法の制定が検討されており、2017年9月に連邦法「SELF DRIVE Act」が米国下院にて法案可決された。しかし、上院において「SELF DRIVE Act」にいくつかの変更を加えた「AV START Act」が議論されているが、未成立の状況となっている。
一方、日本では、自動運転の実用化に対応した道路交通法改正試案が発表され、パブリックコメントを経て2019年の通常国会に提出される運びとなっている。トヨタ自動車やホンダなど国内自動車メーカーは2020年にも自動運転レベル3相当の技術を搭載した車両を市場に送り出す見込みだ。
各国の法整備は慎重ながらも一定の進展を見せており、有力な国際基準が提示されればその動きはいっそう加速する可能性が高い。ここで重要となるのが車両の自動運転技術を図る認証基準だ。自称・自動運転レベル3ではメーカー間の技術にばらつきが生じて信頼性が揺らいでしまうため、一定レベル以上の技術を国際的かつ公的に認証する必要が出てくる。
このほか、EDR・CDR(事故データ抽出・解析)の搭載義務化など事故の際の責任を明確にする仕組みも必要となるだろう。WP29では、こういった点なども踏まえ検討を始めており、早ければ2019年後半までに国際基準案の策定を目指すこととしている。
国際間競争が激しさを増す中、安全面を考慮して慎重な姿勢を示しつつも他国に先駆けて自動運転レベル3を承認するメリットは思いのほか大きい。自動車メーカーサイドも次世代車のシェア獲得に向けいち早く製品化したい思惑があるだろう。WP29の動向を見越し、2019年中に実質上のレベル3搭載車が販売される可能性は決して低いものではないだろう。
【参考】自動運転レベル3については「【最新版】自動運転レベル3の定義や導入状況は?日本・世界の現状まとめ」も参照。
自動運転レベル3の定義や導入状況は?日本・世界の現状まとめ https://t.co/GXqhbmAipw @jidountenlabさんから
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) June 19, 2018
■自動運転タクシー・バスの実用化に向けた実験活発化
2018年12月、米ウェイモが自動運転レベル4(高度運転自動化)相当を搭載した自動運転タクシーの運行を開始した。現状は万が一に備えドライバーが同乗しているようだが、新たな時代の到来を感じさせる事業化がついに幕を開けた。
米ゼネラル・モーターズ(GM)もEV自動運転タクシー事業を2019年に始める計画を発表しており、米国を舞台にさまざまなサービス拡充や検証が進みそうだ。
日本国内では、ロボットベンチャーのZMPと日の丸交通が2018年8~9月にかけて世界初となる自動運転タクシーによる公道営業サービス実証実験を行った。両社は2020年の実用化を目指している。また、自由な移動をコンセプトに掲げる交通サービス「Easy Ride」を共同開発するDeNAと日産自動車も、2018年3月に遠隔監視による無人運転車両でタクシーサービスの実証実験を行っている。こちらは2020年代早期に本格サービスの提供を目指すこととしている。
一方、バス事業では、群馬県前橋市が群馬大学と日本中央バスとともに、日本初となる営業ナンバーによる自動運転バスの実証実験を2018年12月に開始したほか、JR東日本らで構成するモビリティ変革コンソーシアムもBRT(バス高速輸送システム)路線で自動運転バスの技術を検証する実証実験を行っている。
また、国土交通省主導のもと全国各地の道の駅でも実証実験が進められており、中山間地域における人流・物流の確保に向けてビジネスモデルの在り方など協議を進め、2020年までの社会実装を目指すこととしている。
東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年をターニングポイントと捉える取り組みは官民足並みがそろっており、一年後に向けた実証実験やデモンストレーションなどがますます過熱する一年になりそうだ。
【参考】自動運転タクシーについては「【最新版】自動運転タクシーの実現はいつから? 料金やサービスは? 開発している会社・企業、メリットやデメリットを解説」も参照。
徹底解説、自動運転タクシーは善か悪か 21世紀民として考えよう AI、ビッグデータ、ITなどの最先端技術で自動車型交通にイノベーション|自動運転ラボ https://t.co/JTZM2H89dE @jidountenlab #自動運転タクシー #いつ実現? #まとめ #解説 #メリットとデメリット
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) August 24, 2018
■タクシー業界が超戦国時代化、プロモーション合戦も
DeNAの事業拡大やソニーをはじめとした新会社「みんなのタクシー」の設立、そしてウーバーやDiDiといった大手配車サービス事業者の本格進出など、2018年の国内タクシー業界は大きな変革を予感させる年となった。
これらDeNAやみんなのタクシー、ウーバー、DiDiは、2019年も台風の目となる可能性が高い。DeNAは2018年12月から、プロモーション活動の一環として広告料金を活用した「0円タクシー」を開始。みんなのタクシーは後部座席広告事業を提供予定で、キャッシュレス化の浸透とともにタブレットを備えた車両が増加する中、タクシー事業者の新たな収入源として期待が持たれる。
2018年9月には、ウーバーが名古屋で、DiDiとソフトバンクの合弁会社DiDiモビリティジャパンが大阪で配車サービスをそれぞれ正式にスタートし、初乗り無料サービスなどのキャンペーンで差別化を図りながら他都市への拡大を図っている。配車サービスのプラットフォーム競争は過熱の一途をたどっており、2019年も、引き続き提携タクシー事業者のさらなる獲得とともに、スポンサー企業の無料クーポンサービスやイベント連動サービス、期間限定サービスなど、さまざまなサービス展開で他社との差別化を図り顧客シェア拡大を目指す動きが活発化しそうだ。
【参考】タクシー業界の動向については「2018年のタクシー業界10大ニュース!配車アプリ続々、進むキャッシュレス化」も参照。
金土無料、キャッシュレス化…タクシー業界10大ニュースは? AI需給予測や広告配信事業も注目 https://t.co/0cRVPGbcC9 @jidountenlab #タクシー #10大ニュース #配車アプリ #PR
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) December 26, 2018
■「トヨタ×ソフトバンク」に続き、IT企業巻き込む連携加速
自動運転や新しいモビリティサービスを見据え、共同で新会社の設立を発表したソフトバンクとトヨタ自動車。2018年度内に新会社「MONET Technologies」を設立し、オンデマンドモビリティサービスを皮切りに事業に着手する予定だ。
このような自動車メーカーとIT系の提携は近年のトレンドで、グーグル(ウェイモ)やインテル、アップル、マイクロソフト、百度など、大半の大手IT系が何かしらの形で自動車メーカーと手を組んでいる。
今後、自動運転やコネクテッド技術の進展、MaaS(Mobility as a Service:移動のサービス化)の浸透などに伴い、こうした結びつきはいっそう強まることが予想される。
例えばアップルは、2018年5月に独フォルクスワーゲン(VW)と自動運転車分野で提携を結んだことが報道により明らかとなったが、VWの商用ミニバン「T6 Transporter」をベースに無人の自動運転車を開発し、アップルの従業員を送迎するオフィス間シャトルとして活用するなど、提携の中身はまだまだ薄いものだ。
自動運転開発に力を入れつつもこれまで自社発表を控えてきたアップルが、ある局面で世間を驚かせるようなビッグな提携を突如発表し、世界の注目を集めるとともに自動運転開発の主導権を一気に奪取する―—。これはあくまで憶測による一例だが、こういったビッグニュースが2019年に発表される可能性は決して低くものではないはずだ。
【参考】モネテクノロジーズについては「MONET Technologies(モネテクノロジーズ)とは? トヨタとソフトバンク出資、自動運転やMaaS事業」も参照。
【解説】ゼロから分かるMONET Technologies トヨタ自動車とソフトバンクが出資、自動運転やMaaS事業展開|自動運転ラボ https://t.co/8DyLu16Hof @jidountenlab #MONET #トヨタ #ソフトバンク #MaaS #自動運転
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) October 10, 2018
■空飛ぶクルマ、日本初の有人飛行実施で投資マネー急流入か
ドローンも含め世界各地で開発が進む空飛ぶクルマ。この夢の事業ともいえる空飛ぶクルマの開発を日本国内で手掛ける有志団体CARTIVATOR(カーティベーター)と株式会社SkyDrive(スカイドライブ)が2019年6月、日本初となる有人飛行試験を実施する予定だ。
国も空知ぶクルマの産業化を積極的に支援しており、国土交通省と経済産業省が主導する「空の移動革命に向けた官民協議会」は実現に向けたロードマップの素案を2018年11月に発表。実証実験を2020年代の前半に実施した上で、同年代において空飛ぶクルマの事業化も実現させる。実用化は地方から進めていき、都市部での実用化は2030年代を見込んでいる。
一方、カーティベーターは独自目標として2020年の東京オリンピック開会式における聖火点灯デモを掲げており、2023年に有人機の販売を開始し、2026年に先進国向けモデルの量産、2030年に新興国モデルの量産を開始することとしている。
プロボノ活動(=各分野の専門家が知識や経験を生かすボランティア活動)として発足し、クラウドファンディングでの資金集めなど地道に下積みを重ねてきたカーティベーターだが、現在ではトヨタ自動車をはじめアイシン精機、デンソー、ダイハツ工業、ジェイテクト、豊田通商、日野自動車、NEC、パナソニック、富士通、リクルートテクノロジーズなど大手40社以上が出資などの支援を行う規模にまで成長している。
また、スカイドライブ社も、ドローン社会やエアモビリティ社会の実現を目指す「Drone Fund」から3億円の資金調達を2018年11月に発表している。
開発に向けては莫大な資金を要することとなるが、2019年の有人飛行試験で注目度が飛躍的に高まることが予想され、東京五輪でのデモンストレーションなども決定すれば話題性にも事欠かない。これを契機として、多額の投資マネーが動く可能性も高そうだ。
【参考】CARTIVATORについては「【最新版】CARTIVATOR(カーティベーター)が開発する「空飛ぶクルマ」とは? 実現いつ? 誰が運営?」も参照。
空へ挑む技術者たち…ニッポン発の空飛ぶクルマ、徹底解剖 トヨタ自動車も支援、加速する資金調達 東京オリンピックでデモ実施へ https://t.co/bU1TytSQku @jidountenlab #空飛ぶクルマ #Cartivator #実現はいつ?
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) November 11, 2018
■改正道路交通法の成立見越し、保険業界が商品開発に注力
2019年は、日本も自動運転実現に向け大きく動き出す一年になりそうだ。警察庁が自動運転の実用化に対応した道路交通法改正試案を2018年末に発表し、2019年1月23日までパブリックコメントを受け付けている。2019年の通常国会に提出する予定で、審議が順調に進み計画通り成立すれば、2020年前半にも施行されることになる。
試案では、①自動運行装置(仮称)の定義等に関する規定の整備②自動運行装置を使用して自動車を運転する場合の運転者の義務に関する規定の整備③作動状態記録装置(仮称)による記録等に関する規定の整備――に触れている。
具体的には、自動車を運行する者の運行に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する自動運転システムを「自動運行装置」として新たに定義するほか、自動運行装置を使用して自動車を運転する者は、一定の条件を満たさなくなった場合に直ちに適切に対処することができる態勢でいるなどの場合に限り、携帯電話などの無線通話装置の使用を禁じた「法第71条第5号の5」の規定外としている。自動運行装置の一定の条件を満たさない場合には、当該自動運行装置を使用した運転を禁止することとしている。
また、自動運行装置を備えた自動車の使用者などに対し、同装置の作動状態を確認するために必要な情報を記録する装置「作動状態記録装置」を備えていない状態での運転を禁止するとともに、同装置により記録された情報を保存することを義務付けることなどが盛り込まれている。
現段階ではあくまで試案のため審議過程を見守る必要があるが、内閣が進める「官民ITS構想・ロードマップ2018」においても、制度面で2020年を目途に自動運転レベル3の自動運転システムに係る走行環境の整備を図ることとしており、2020年の実現に向け大きく前進する年となるだろう。
こうした動きに素早く反応しているのが保険業界だ。政府は2018年、自動運転における事故の責任は車の所有者にあるとする考え方をまとめ、自動車損害賠償責任保険(自賠責)においては従来通り相手の被害を補償する方針を打ち出した。
これを受け、自動車保険を提供する各損保会社も新たな保険商品の開発を進めており、自賠責で補償外となるケースや責任の所在が複雑に問われるケース、責任の所在を明確にするEDRなどの取り扱い、サイバーセキュリティリスク、自動運転で新たに必要となる付加サービスなどさまざまな観点から検討を開始している。他社との共同研究や実証実験なども進めている模様で、自動運転の解禁に合わせて新商品を販売できるよう躍起になっている。
【参考】道交法改正案については「自動運転を想定した道路交通法改正試案、5つのポイント レベル3でスマホ利用可能に」も参照。
【解説】AI自動運転を想定した道交法改正案、5つのポイント 自動車イノベーションの土台作り進む https://t.co/t6jwYgng5H @jidountenlab #自動運転 #道路交通法 #改正案
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) January 2, 2019
■次なる注目は「自動運転車の中」の覇権争い
自動運転車の実現はもはや夢物語ではなくなり、焦点は「いつ実現するか」といったことへ移り変わっている昨今。自動運転技術とは別に開発が加速しているのが、自動運転車だからこそ実現できる車内システムや利便性の高いサービスだ。
インフォメーションとエンターテインメントを組み合わせた「インフォテイメント」関連は、コネクテッドカーの普及とともに爆発的に伸びることが予想される分野。さまざまな情報やコンテンツを、車内スペースを生かしてどのように利活用できるかがカギで、発想と技術の両面から研究開発が進められている。
現在、フロントガラスに車両の状況や交通情報などを投影するヘッドアップディスプレイなどが製品化されているが、完全自動運転が実現すればガラス一面をモニターとして活用することが可能になる。韓国の大手自動車部品メーカー・現代モービスは、米ラスベガスで2019年1月開催のCES 2019で車両の窓ガラス一面がディスプレイとなる車載インフォテイメントシステムを発表した。ガラスを透明にすることもでき、手動運転にも対応した技術で、娯楽映像などエンターテインメントのほか広告業界などからも注目が寄せられている。
こういったディスプレイなどのハード面における技術開発と、そのハードを生かした有効なコンテンツの開発競争が今まさに水面下で繰り広げられている最中だ。初歩的な技術は既存のコネクテッドカーなどに採用される可能性も高く、コネクテッドカーの普及を見据えた動きがそろそろ表に出てきそうだ。
また、一般車両へのキャッシュレス決済導入に向けた取り組みも前進するのではないかと思われる。現在、タクシー業界などを中心にプラットフォームを活用したキャッシュレス決済が普及しているが、今後、ガソリンスタンドや有料駐車場などの決済に対応したサービスの普及なども考えられる。コネクテッドカーが進展すれば決済の機会も増加することが予想されるため、こういった自動運転技術以外における覇権争いもそろそろ水面から顔を出すのではないだろうか。
【参考】決済のキャッシュレス化については「「トヨタペイ」の衝撃 ”夢の車”と決済、手数料長者に誰がなる?」も参照。
「トヨタペイ」の衝撃 "夢の車"と決済、手数料長者に誰がなる? コネクテッド自動運転社会、自動車会社はどう動くのか https://t.co/68sMb9YKZN @jidountenlab #トヨタペイ #コネクテッドカー #誕生なるか
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) November 27, 2018
■LiDARが低価格化、数百万円から数万円に?
自動運転において目の役割を担うセンサーの一つで、高性能がウリのLiDAR(ライダー)。数年前までは1台数十万円から数百万円が相場で、実験車両に搭載されるだけの一般ドライバーにはなじみのない製品だった。
しかし、米ベロダインライダーをはじめとする大手が開発にいっそう注力し、多くのスタートアップの登場もあって性能の向上や量産体制、低価格化が著しく進んでいる。量産車では、自動運転レベル3技術で話題の「Audi A8」が世界で初めてLiDARを搭載しており、一般ドライバーへの普及の道を切り開いた格好だ。
今後、さまざまな自動運転レベル3搭載車の登場とともにLiDARを量販車に採用するメーカーも増加することが予想され、量産体制の充実とともに価格は下落し、1台当たり数万円程度が相場になるとの見方も強い。
また、低価格LiDARの開発に特化したスタートアップも次々と登場しており、カメラやレーダーなどが主流の自動運転レベル2車両への搭載が実現する可能性も否定できない。LiDAR採用による差別化・ブランド化や、将来的な技術開発体制の早期構築に向けた採用など、こういった動きが2019年中に起こっても不思議ではないだろう。
なお、LiDARを含むレーザーの市場規模は、2017年の約25億円から2030年には約4959億円まで200倍に拡大すると言われており、矢野経済研究所によると、2030年の自動運転用センサーの製品別シェアでは、レーダーが1兆3914億円、カメラが1兆2976億円、LiDARとレーザーが約4959億円、超音波が約904億円という。
【参考】LiDARについては「【最新版】LiDARとは? 自動運転車のコアセンサー 機能・役割・技術・価格や、開発企業・会社を総まとめ」も参照。
LiDAR完全解説&開発企業まとめ 自動運転の最重要センサ トヨタ自動車もスタートアップも開発競争 イノベーションに必須、データをAI解析|自動運転ラボ https://t.co/Uul4BS2teZ @jidountenlab #自動運転 #巨大市場 #業界関係者必見 #世界と日本
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) August 26, 2018
■サブスク型など車の所有の在り方が変わるサービス続々
マイカー所有といえば、ディーラーや中古車事業者などでローンを組んで愛車を購入するのが当たり前……という時代が変わりつつある。トヨタ自動車は2018年11月、「筋斗雲」をイメージした「KINTO」という愛車サブスクリプションサービスを2019年初旬に開始することを発表した。
KINTOは定額制の自動車乗り換えサービスで、税金や保険の支払い、車両の整備などの手続きもパッケージ化されており、気軽に好きなクルマ・乗りたいクルマを選ぶことができる。サブスクリプション方式は利用期間に応じて毎月定額でマイカーに乗れるサービスで、2017年以降、米GMや独ポルシェ、BMW、ダイムラーなど各社がサービス展開している。
国内ではトヨタ自動車のほか、中古車買取・販売店ガリバーでおなじみの株式会社IDOMが2018年10月、定額料金で車両を貸し出す「NOREL(ノレル)」を拡充し、BMW日本法人と連携して新車を貸し出すサービスを発表している。
世界的に導入が進んでいるサブスクリプション方式は今後、国内他メーカーの動向にも注目が集まりそうで、2019年中にトヨタ自動車に追随する動きが出てきてもおかしくはないだろう。
一方、自動車を「所有から利用へ」とサービス転換を図るカーシェア業界も多様化している。DeNAが2015年にスタートした個人間カーシェアサービス「Anyca(エニカ)」は、サービス開始から3年で登録会員数17万人、登録車数6000台をそれぞれ突破するなど新しいシェアリングサービスの形として人気が高まっている。
また、IDOMも個人間カーシェアサービス「GO2GO」を2019年4月にスタートする予定だ。個人間カーシェア事業にはNTTドコモの「dカーシェア」や株式会社trunkが運営する「CaFoRe」などがあり、このようなCtoCサービスは認知度の向上とともにまだまだ成長が見込める分野だ。
このほか、タイムズカーレンタルやタイムズカープラスなどを手掛けるパーク24は、無人サービスであるカーシェアリングと有人サービスであるレンタカーそれぞれの強みを組み合わせた新しい形のモビリティサービス「タイムズカー」の本格展開に向け、2019年1月よりトライアルを開始することとしている。MaaS事業に力を入れる同社の取り組みにも注目が集まるところだ。
サブスクリプションやカーシェア事業の多様化などで、自動車所有の概念が変わりつつある昨今。2019年はより多くの選択肢が出てくる一年になりそうだ。
【参考】KINTOについては「トヨタ、定額乗り換え放題サービス「KINTO」を2019年初旬に開始」も参照。
「筋斗雲」イメージ…トヨタ自動車の定額乗り換え放題サービス、2019年に開始 https://t.co/uh4I1VyJlr @jidountenlab #トヨタ #乗り換え放題 #筋斗雲
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) November 5, 2018
■技術者不足深刻化…日本でも欧米流のドライな引き抜き合戦
欧米では技術者の引き抜き合戦が常態化している。2018年には、米アップルがEV大手の米テスラ・モーターズやグーグル系ウェイモから技術者を引き抜いたことなどがニュースになったほか、過去にはグーグル社を退職した一人のエンジニアをめぐり、企業秘密を不正に持ち出したとして訴訟沙汰に発展したケースなどもある。
これは極端な例だが、日本国内でも技術者需要の高まりとともに技術者の絶対数不足が指摘されており、官学民がAI開発やプログラミング技術などの人材育成に鋭意力を入れているのが現状だ。
トヨタグループは2018年3月、自動運転開発を手掛ける新会社「トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント(TRI-AD)」を立ち上げ、トヨタやデンソーの技術者を含め1000人規模の開発体制を構築するため大規模なキャリア求人を出した。
トヨタに限らずこうした求人は常設化されており、優秀な人材確保の動きはますます過熱していく感が強い。
国内でも自動運転に関連したスタートアップが次々と産声を上げ、高度な技術が認められ多額の出資を受ける例もしばしば目にする。今後、こういったスタートアップの囲い込みをはじめ、優秀なエンジニアの引き抜き合戦が国内でもドライに繰り広げられるというのは、もはや想定外の話ではないだろう。
【参考】人材育成については「「自動運転×人材育成」の最新動向まとめ AI人材育成を国策で推進」も参照。
国策で進む「自動運転×人材育成」、最新動向まとめ AIやIT人材の育成急務、コンテスト実施も https://t.co/eWLDDdaKyJ @jidountenlab #自動運転 #人材育成 #国策 #民間企業
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) December 12, 2018
■【まとめ】2020年に向けた重要な変化の年に
日本をはじめ各国が2020年までに自動運転レベル3の実現を目指すのであれば、法整備などの環境面の構築で本年中に大きな動きが起こることは間違いのないもので、これに合わせ車両開発や付随するサービスの開発なども加速するだろう。
また、MaaSを見据えた取り組みも芽を出し始め、つぼみを付ける段階まで大きく進展する可能性もある。モビリティを取り巻く構造変化の節目の年として、2019年も自動運転業界から目を離すことができない一年になりそうだ。
【参考】関連記事としては「2018年の自動運転・モビリティ業界の10大ニュース コネクテッドカー、ライドシェア、MaaS、タクシー配車アプリ」も参照。
2018年の自動運転・モビリティ業界の10大ニュース 資金調達活況、開発計画から消えるレベル3 https://t.co/PtGStncuf5 @jidountenlab #10大ニュース #自動運転 #コネクテッドカー
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) December 25, 2018