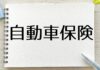名古屋大学発の自動運転スタートアップである株式会社ティアフォー(本社:愛知県名古屋市/代表取締役社長:加藤真平)。オープンソースの自動運転OS(基本ソフト)「Autoware(オートウェア)」に重点を置いた戦略で、自動運転シーンをリードする国内有力企業だ。
「自動運転の民主化」をビジョンに掲げる同社は、未来の交通社会にどのような可能性をもたらすのか。同社の取り組みに迫る。
<記事の更新情報>
・2023年10月19日:2022〜2023年の取り組みを追記
・2019年1月22日:記事初稿を公開
記事の目次
■ティアフォーの企業概要
加藤真平氏を中心に2015年創業
ティアフォーは、同社の社長兼CEO(最高経営責任者)兼CTO(最高技術責任者)で東京大学特任准教授(2023年4月~)を務める加藤真平氏らを中心に2015年12月に設立された。
加藤氏は慶應義塾大学で博士課程を修了後渡米し、カーネギーメロン大学とカリフォルニア大学で研究を積み重ねた。帰国後は名古屋大学准教授に着任し、コンピューターサイエンス技術を武器に自動運転関連の研究を進め、オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」の開発を主導した。
このAutowareの自動運転システムのさらなる開発や普及を図るため、名古屋大学オープンイノベーション拠点を本拠地にティアフォーを立ち上げたのだ。
自動運転タクシーや自動搬送ソリューションの開発などをはじめ、Autowareの業界標準を目指す国際業界団体の設立や関連企業の立ち上げ、他の業界団体への参画や連携など、国内外にまたがる事業展開で年を追うごとに存在感を強めている。
開発プラットフォームで市場シェア獲得
市場黎明期(~2026年)においては、ティアフォーが定義する自動運転システムやハードウェアをパッケージ提供することでエコシステムを形成し、市場成熟期(2030年)には自動運転システムを自ら作りたい顧客に対しプラットフォームを提供することで市場シェアを獲得していくという。
現在は、後述する「Web.Auto」や「Pilot.Auto」といったソリューションで開発設計のベースとなるリファレンスデザイン込みのプラットフォームを提供している。これにより、黎明期の自動運転サービスの需要を満たす容易な開発環境が整備され、顧客層の母数が増大する。このプラットフォームサービスの収益化を図りつつ、市場成熟期に向け開発の自由度を高めていく戦略だ。
標準化戦略の前提となる市場導入に向けての取組方針としては、「車両仕様のオープン化」「車載ソフトウェアのクラウド化」「ソフトウェアプラットフォームによる安全確保のためのルール作り」に重点を置いている。
オープン化に向けては、Foxconn主導の「MIH(Mobility in Harmony)」に参画し、自動運転の設計をリードし自動運転プラットフォームのデファクトを狙っている。
クラウド化に関しては、ソフトウェアディファインドビークル向けのオープン標準準拠のアーキテクチャとして英Armが発足した「SOAFEE」に参画し、このプラットフォームと連携したAutoware開発キットの開発をリードしデファクトを狙うとしている。
KGI(経営目標達成指標)には、以下3つの目標を掲げている。
- 10~1,000Wの範囲の消費電力で実行可能なレベル4の自動運転機能に対し、現行比100倍以上の「消費電力あたりのユースケース数」を達成
- 10カ国以上の異なる地域における標準的なODD(運行設計領域)に対し、平均5万マイル以上の「自動運転による連続走行距離(Miles per Disengagement)」を達成
- オープンソースソフトウェアとしてGitHub上で10万以上の「スター数」と3,000人以上の「コントリビューター数」を達成
2022年度時点では、消費電力あたりのユースケース数は1.05倍、自動運転による連続走行距離は自動運転タクシーが1.5マイル、自動搬送車が18マイル、GitHubにおけるスター数6,700、コントリビューター数163となっており、消費電力あたりのユースケース数以外は年次目標をおおむね達成している状況だ。
■Autowareの概要
自動運転開発を促進するオープンソースソフトウェア「Autoware」

Autowareは、ティアフォー設立前の2015年8月、名古屋大学や長崎大学、産業技術総合研究所らで取り組んだ「市街地の公道での自動運転」向けに開発された。その後、世界初となるオープンソースの自動運転ソフトウェアとして公開され、大学の研究開発から企業の製品開発まで幅広く利用されるようになった。
交通量の多い市街地においても自車位置や周囲の環境を認識でき、交通ルールに従った操舵制御の機能も搭載されている。車両や歩行者、車線、信号などの認識をはじめ、3次元(3D)位置推定や3D地図生成、経路生成、操舵制御、センサーフュージョン、キャリブレーション、ダイナミックマップ、シミュレーション、データロガーなどさまざまな機能を備える。
世界各地でAutowareを活用した自動運転開発が進められており、国内では2020年8月までに18都道府県の約50市区町村でAutoware搭載車両による公開型実証が約70回実施されている。
海外では、2023年10月時点で、米国や中国、台湾、エストニア、イスラエル、タイなど20カ国以上、500超の事業者がAutowareを活用した取り組みを進めているという。
トヨタが開発を進めるモビリティサービス専用の自動運転EV(電気自動車)「e-Palette(イー・パレット)」にAutowareが搭載されたこともあるようだ。
【参考】関連記事としては「【スクープ】トヨタe-Paletteに「アピール用」と「量産廉価型」 自動運転OSにはAutoware採用」も参照。
【スクープ】トヨタe-Paletteに「アピール用」と「量産廉価型」 自動運転OSにはAutoware採用 https://t.co/6cHil1TkAY @jidountenlab #トヨタ #自動運転 #e-Palette
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) December 19, 2019
■ティアフォーのソリューション
開発車両
古くは、アイサンテクノロジーと共同で2017年末までに製作したワンマイルモビリティのプロトタイプ初号機「Milee(マイリー)」が存在する。

ヤマハ発動機の電動ゴルフカートをベースにした4~5人乗りの自動運転EVで、ハンドルやアクセルなどのペダルを備えないレベル4専用車両となっている。
車体には3Dプリンター樹脂材が使用されており、重量は約700キログラム。丸っぽく可愛らしいデザインに仕上がっており、最高速度は時速19キロメートルに抑えられている。卵のような丸みを帯びたデザインが魅力的だ。
また、物流業務用に設計した小型の自動搬送ロボット「Logiee(ロージー)」や、ラストマイルデリバリーに向けた低速自動運転EV「Postee(ポスティー)」なども発表している。

Logieeは2020年12月、遠隔監視・操縦機能を搭載した小型の自動搬送ロボット「Logiee S1(ロージー・エスワン)」として進化を遂げ、自動配送ロボット実証などに用いられている。
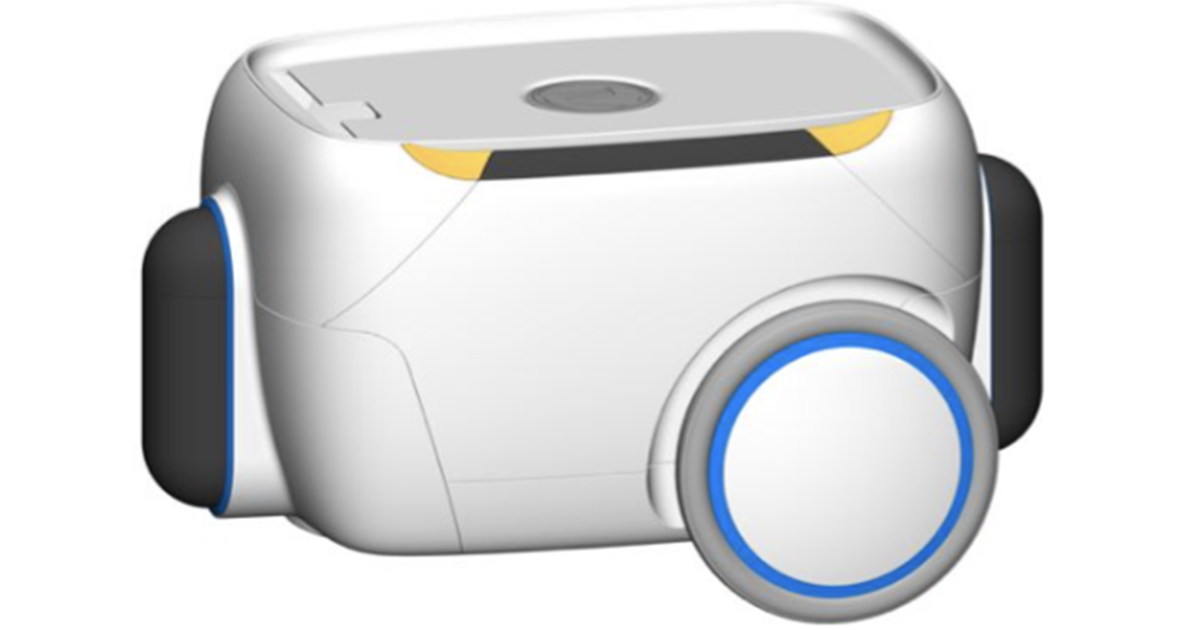
後述するが、自動運転EV生産に向けたソリューション「ファンファーレ」や、トノックスとのパートナーシップなど、2023年には自動運転車両量産化に向けた動きも活発化している。
【参考】Posteeについては「ティアフォー、低速完全自動運転EVの「Postee」発表へ Autoware搭載」も参照。
Web.Auto
IoT・クラウド技術を活用し、自動運転システムの利用・運用・開発の全てをサポートするウェブプラットフォームサービスで、サービス事業者へAutowareと連動した運行管理システムを、開発者へAutowareを使うためのツールをそれぞれ提供する。
事業者向けには、自動運転車の配車管理を行うフリートマネジメントシステム(FMS)や安全なオペレーションを提供するFMSコンソール、遠隔地の車両をリアルタイムで監視するAutoware Driveなどが用意されている。
また、開発者向けには、効率的なシステム開発を実現するシミュレーターをはじめ、高精度地図の作製をブラウザ上で行うことが可能なVector Map Builder、ディープラーニングに不可欠な教師データを効率的に作製できるAutomanなどが用意されている。
デジタルツイン指向の自動運転シミュレーター機能「AWSIM」の追加など、リリース後もしっかりと進化を遂げている点もポイントだ。
Pilot.Auto
Autowareを利用した自動運転ソフトウェアプラットフォームで、あらかじめ用意された「シャトルバス」などのリファレンスデザイン(参照設計)をベースに開発を進めることで、目的に沿った効率的な自動運転システムの開発と運用を可能にするソリューションだ。
自動運転バスやタクシー、配送ロボットなどあらかじめ用意された5タイプのユースケースの中から目的を満たすもの、あるいは近いものを選択することで、開発初期に必要となる作業を大幅に軽減することが可能になる。
新規ユースケースの追加や認識性能の向上、不要な機能の削除など仕様に基づいたソフトウェアのカスタマイズなどにも広く対応している。
【参考】Web.AutoとPilot.Autoについては「バス自動運転化などの「起点」に!ティアフォーが新サービス」も参照。
バス自動運転化などの「起点」に!ティアフォーが新サービス https://t.co/t5iRfkVQ1h @jidountenlab #自動運転 #ティアフォー
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) November 9, 2022
センサーソリューション
車載センサー関連の開発も盛んだ。2022年には、自動運転に特化した車載カメラの生産・販売に向け大手カメラODMのAbility Enterpriseとパートナーシップを結んでいる。
同年、量産出荷を開始するロボティクス・車載向けHDRカメラ「C1」とNVIDIAが提供するJetson AGX Orin開発者キットを組み合わせた「C1カメラ画像認識スターターキット」の販売を開始した。
2023年6月には、容易に導入可能なセンサーフュージョン開発キットの提供も開始すると発表した。最先端の車載カメラやLiDAR、自動運転用コンピューターを統合し、センサーフュージョンによる高度なパーセプション技術の開発環境をワンパッケージで提供している。
遠隔監視ソリューション
ティアフォーは2023年9月、レベル4水準の自動運転サービスに対応した遠隔監視ソリューション「L4リモートモニタリング」の提供を開始すると発表した。
遠隔監視に必要な車載カメラとマイク、クラウド上の映像配信サーバー、モニタリングアプリケーションを提供する包括的なソリューションで、カメラとマイクから得られる映像と音声によって自動運転車両の走行環境をリアルタイムに再現することができる。
開発運用基盤「ブルーバード」
ティアフォーは2023年9月、自動運転システムの開発運用を容易に事業化する新たなソリューション「ブルーバード」の提供を開始した。
同社が所有する開発運用基盤のライセンス提供を中心としたソリューションで、独自の自動運転ソリューションを構築する際に活用できる。自動運転関連のソフトウェア開発やハードウェア生産が可能となり、特定企業に依存しない持続可能なエコシステムを形成できるという。
■実証関連の取り組み
自動運転タクシー関連
ティアフォーとJapanTaxi、損害保険ジャパン、KDDI、アイサンテクノロジーの5社は2019年、自動運転タクシー事業化に向け共同でサービス実証を進めることに合意したと発表した。
トヨタ製JPN TAXIを自動運転化し、全国各地の自治体との連携のもと、さまざまな実証などへの参画を通じてサービス機能の拡充や事業モデルの精査を図っていく。その後の事業化段階では、自動運転タクシーの最終整備とともに継続的なサービス提供に必要なオペレーション体制の構築を進めていく方針だ。
2020年11月に東京都内で実証に着手し、遠隔操舵の有用性の検証を行った。その後も2021年度に信号などのインフラ連携、2022年度にイベントと合わせた運行を行うなど、レベルアップを図っている。
2023年度は、7月から毎月3日間程度運行を行い、経験値を積み重ねているようだ。
【参考】自動運転タクシーに関する取り組みについては「西新宿で「LINEで自動運転車」サービス!ビル25階から遠隔監視」も参照。
西新宿で「LINEで自動運転車」サービス!ビル25階から遠隔監視 https://t.co/t8vXP4Uw8K @jidountenlab #自動運転 #LINE
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) June 30, 2023
自動運転バス関連
ティアフォーは2020年11月、埼玉工業大学などとともに長野県塩尻市内の一般公道でバス型自動運転車両を用いた走行実証実験「塩尻型次世代モビリティサービス実証プロジェクト」を行うと発表した。
埼玉工業大学が所有する自動運転バスとAutowareを活用し、高精度3次元地図をベースに自己位置推定や障害物認識などの機能を実装した実証実験車両を走行させた。
塩尻市内では2021年11~12月にも自動運転用のデータ取得に関するアナウンスが発されており、近々新たな公道実証が行われるものと思われる。
このほか、2021年6月には、栃木県の事業「栃木県ABCプロジェクト」の一環で実施された自動運転バスの実証実験にフィールドオートとともに参加している。
2023年には、愛知県の「自動運転社会実装プロジェクト推進事業」のもと愛・地球博記念公園で将来の無人走行を見据えた遠隔管制システムを用いた運行検証や、石川県小松市における自動運転バス導入に向けた実証、岩手県陸前高田市における自動運転サービス実証など、活躍の場をどんどん拡大している印象だ。
自動搬送ロボット(自動配送ロボット)関連
ティアフォーと三菱商事、三菱地所は2020年12月までに、岡山県玉野市の公道でルート最適化技術を利用した低速・小型自動配送ロボットの公道走行を実施した。
自動搬送ロボット「Logiee S1(ロージー・エスワン」にオプティマインドのルート最適化アルゴリズムを適用し、エリア内のドラッグストアやクリーニング店などの小売店から医薬品や食品などをピックアップして配送する取り組みだ。
2021年11月には、ティアフォーと損保ジャパン、SOMPOケア、川崎重工業の4社が自動搬送ロボットを活用し、地域包括ケアシステムにおける人手を介さない物流システム実現に向けた実証を東京都内で開始した。
ティアフォーと川崎重工がそれぞれ開発した自動搬送ロボットにテAutowareを搭載し、都内の公道で医薬品や食品、日用品などを配送するで、「Web.Auto」上の運行管理システムで複数種類の自動搬送ロボットを同時制御する取り組みも進めているようだ。
2022年2月には、川崎重工、KDDI、損保ジャパン、小田急電鉄などとともに、自動配送ロボットが5Gを活用して公道走行しラストワンマイル配送を行う実証も行っている。
【参考】玉野市での取り組みについては「三菱商事と三菱地所が「自動運転×配送」に注力!?国内初の実証実験、岡山県玉野市で」も参照。
【参考】東京都内での取り組みについては「強力布陣で挑む!自動搬送ロボ、いよいよ都内で「車道端」も走行」も参照。
強力布陣で挑む!自動搬送ロボ、いよいよ都内で「車道端」も走行 https://t.co/9L4B5DPUCl @jidountenlab #自動配送ロボ #川崎重工 #ティアフォー
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) September 9, 2021
■ティアフォーの主なパートナーシップ
アイサンテクノロジーとSOMPOホールディングス
ティアフォーは2017年、アイサンテクノロジーと岡谷鋼機とワンマイルモビリティの事業化に向け業務提携を交わした。
2019年には、アイサンテクノロジーと損保ジャパンとともに、インシュアテックソリューション「Level IV Discovery」の共同開発に向け提携しているなど、2社とは各地の自動運転実証でも協力体制を敷くことが多い。
ヤマハ発動機
ティアフォーとヤマハ発動機は2020年2月、自動運転技術を使った自動搬送ソリューションを展開する合弁「eve autonomy」を設立した。Autowareをヤマハ発動機のランドカーに統合し、自動運転車両や搬送台車の開発・販売・リース・レンタルをはじめとした自動搬送ソリューションの提供を行っている。
ヤマハ発動機の工場で運用を重ね、2021年9月に自動搬送サービス「eve auto」の受注を開始した。初期導入時のハードルとなりがちな高い初期費用と長期間におよぶ導入工事のクリアを目指し、サブスクリプション型契約形態を採用したほか、運行管理システムやアフターサポートもワンストップで提供する。
パナソニックグループへの試験導入をはじめ、プライムポリマー、富士電機、日本ロジテム、ENEOSなどで運用されている。2023年7月には、三菱ふそうトラック・バスの工場で無人走行による試験導入も開始しているようだ。
【参考】eve autonomyについては「ダブルの「国内初」!自動運転EVで搬送サービス&専用保険」も参照。
ダブルの「国内初」!自動運転EVで搬送サービス&専用保険 https://t.co/t3dqGYSxde @jidountenlab #自動運転 #国内初
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) December 4, 2022
ADLINKやAutoCore
ティアフォーと台湾の産業用電子機器メーカーADLINK、ITRI(台湾工業技術研究院)は2020年6月、インテリジェント交通システムの構築を見据えたオープンソースの自動運転技術の開発拡大に向け協業を発表した。
翌月には、ティアフォーとADLINKがモビリティ向けソフトウェア開発を手掛けるAutoCoreと提携を交わしたことも発表されている。ADLINKのエッジコンピューティングやAutoCoreのデータ駆動型ミドルウェア、ヘテロジニアスコンピューティングなどを統合し、広範な次世代自動運転アプリケーションの開発を進めるとしている。
トノックス
特装車の企画・開発や製造を手掛けるトノックスとティアフォーは2023年6月、レベル4自動運転EVの量産に向け協業を開始したと発表した。
レベル4水準の自動運転機能を既存商用車に追加するには、車両の特殊設計を担うパートナー企業が必要不可欠となるが、ティアフォーが策定した「レベル4自動運転化ガイドライン」のもと、トノックスの技術によってレベル4水準に対応する電動化・冗長化対応、ボディの設計・製造・構築などが可能になる。
国産自動運転車の量産化がついに実現するのか、要注目だ。
【参考】トノックスとの協業については「ティアフォー、「自動運転レベル4」EVの量産開始へ」も参照。
ティアフォー、「自動運転レベル4」EVの量産開始へ https://t.co/W2CKl8qpkv @jidountenlab #ティアフォー #自動運転
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) June 27, 2023
資本提携関連
ティアフォーは、合弁eve autonomyのほか、前出のAutoCoreやトルコのLeo Drive、オプティマインド、AI教習所とも資本提携を交わしている。
Leo Driveは自動運転向けのセンサーキットの開発を進めており、オプティマインドはAIを活用したルート最適化サービスの開発を手掛けている。AI教習所は南福岡自動車学校を運営するミナミホールディングスとの合弁で、AIと自動運転技術を活用した新しい運転教習システムの開発を行っている。
The Autoware Foundation(AWF)
世界各地へAutoware普及を図るべく、積極的に世界戦略を進めるティアフォー。米シリコンバレーにおける事業活動にも力を注いでいるようだ。
日本国内とは交通ルールなどの環境が異なる場所でAutowareの試験を進めることで、自動運転システムの応用力を高めることができるほか、自動運転システム開発に積極的な開発パートナーに恵まれた環境も魅力だ。米Apex.AIなど、現地の自動運転スタートアップや新興企業などとAutowareのデファクト化に向けた走行実験なども積極的に行っている。
2018年12月には、自動運転OS「Autoware」の業界標準化を目指し、Apex.AIと英Linaroと共同で世界初となる国際業界団体「The Autoware Foundation(AWF)」を設立することを正式発表した。Autowareに関する全ての権利はこのAWFに委譲された。
AWFは、Autoware.AI、Autoware.Auto、Autoware.IOという3つのカテゴリーの中で、Autowareに関する種々のプロジェクトを発足させ、発展させていくための非営利団体。豊富な機能を持つAutowareの組織化・整理を進め、参画企業とともにさまざまな検証を行っていく方針だ。
Autoware.AIは、2015年から続く従来のAutowareプロジェクトを踏襲するカテゴリーで、主に研究開発用途として国内外で既に100社以上、30種類以上の自動運転車両に導入されている。
また、Autoware.Autoは、Autoware.AIを機能安全の観点から見直し、次世代のRobot Operating System(ROS)であるROS2フレームワークを用いて再設計された新しい車載用Autowareの開発に関するカテゴリーで、Autoware.IOは、Autoware向けのさまざまなECUやアーキテクチャ、車両制御インタフェース、サードパーティ製ソフトウェア、ツール関係を取りまとめるカテゴリーだ。
AWFのプレミアムメンバーには、2023年10月時点でティアフォーやArm、TomTom、AutoCore、AMD、eSOL、Foxconnなど21企業が名を連ねている。
このほか、アイサンテクノロジーやAxell、日立、マクニカ、 Hesai、Ouster、Robosense、NXP、NTTデータ、名古屋大学、東京大学、埼玉大学、フロリダ工科大学、ポズナン工科大学など、産学界合わせ計65団体・企業が参画している。
ROS 2 Technical Steering Committee
ティアフォーは2019年、ROS 2の開発チームに相当する「ROS 2 Technical Steering Committee(TSC)」に加盟したと発表した。
ROS 2は、自動運転を含むロボットアプリ用ソフトウェアプラットフォームとして知られる「Robot Operating System(ROS)」の次世代規格で、開発チームは非営利団体「Open Source Robotics Foundation」が運営している。
今後、ROS 2の開発ロードマップの策定やAutowareの基盤としてROS 2を採用する取り組みなどを進めるほか、安全性が重視される組込みシステムや決定論的なロボットソフトウェア、ハードウェアアクセラレータを用いた高性能計算等におけるROS 2の開発・普及に貢献するとしている。
ロボットデリバリー協会
ティアフォーと川崎重工業、ZMP、TIS、日本郵便、パナソニック、本田技研工業、楽天グループの8社は2022年2月、自動配送ロボットを活用した配送サービスの普及と人々の生活の利便性向上を目指しロボットデリバリー協会を立ち上げたと発表した。
参画各社の知見を生かし、行政機関や団体との連携のもと自動配送ロボットが公道走行するための業界における自主的な安全基準の制定や認証の仕組みづくりに取り組むとしている。
2023年10月現在、ウーブン・バイ・トヨタや京セラコミュニケーションシステム、スズキ、本田技研、LOMBYなども参画しており、賛助含め会員企業は31社に上る。
【参考】ロボットデリバリー協会については「自動配送ロボの普及に弾み!ロボットデリバリー協会、活動内容は?」も参照。
自動配送ロボの普及に弾み!ロボットデリバリー協会、活動内容は? https://t.co/iRF0HCzw4z @jidountenlab #自動配送 #ロボット #協会
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 11, 2022
MIH
台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業傘下の富士康科技集団(Foxconn=フォックスコン)が展開する世界最大級のEV開発コンソーシアム「MIH(Mobility in Harmony)」にも参画し、Autowareを武器に自動運転開発を主導している。
MIHの自動運転ワーキンググループは、ティアフォーのクリスチャン・ジョン氏が議長を務め、ADAS(先進運転支援システム)や自動運転機能の共通インターフェイスやセンサーフュージョン、エッジコンピューティング、HDマップ統合などを定義付け、これらの機能を開発者向けにオープン化している。
クラウドからエッジまでのソリューションを迅速に開発するための網羅的なADリファレンス・プラットフォーム「Open AD Kit」をベースに、MIHのOpen EVKitプラットフォームの要件に沿った車載グレードの自動運転システムソリューションを定義し、開発者が拡張可能な車載グレードの自動運転システムを容易に製品化できるよう取り組んでいる。
【参考】MIHについては「世界最強の自動運転連合に!台湾MIH、加盟2,600社突破」も参照。
世界最強の自動運転連合に!台湾MIH、加盟2,600社突破 https://t.co/ptYYvQ6QNr @jidountenlab #自動運転 #MIH
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) April 27, 2023
■グループ企業
専門技術有する子会社が6社
ティアフォーの子会社には、2023年10月時点でMAP Ⅳ(マップフォー)、EMB Ⅳ(エンブフォー)、BRAIN Ⅳ(ブレインフォー)、Synesthesias(シナスタジア)、Human Dataware Lab(HDL)、フィールドオートの6社が名を連ねる。
マップフォーは3次元地図作成技術・位置推定技術、エンブフォーは仮想空間テストで使用するシナリオ作成や性能分析する手法のノウハウ、ブレインフォーは機械学習を用いたデータ解析、シナスタジアは自動運転車内におけるエンタメサービス開発やVR・ARコンテンツ制作、HDLは深層学習を用いた自動運転運転に関する研究開発、フィールドオートは埼玉工業大学発ベンチャーで自動運転実証を手掛ける。
いずれも専門技術・ノウハウを生かし自動運転開発分野で活躍する企業だ。
■資金調達
累計約300億円規模に
ティアフォーは2019年7月、シリーズAラウンドで累計113億円の資金調達を実施したと発表した。出資者には、損害保険ジャパン日本興亜(現社名:損害保険ジャパン)やヤマハ発動機、KDDI、ジャフコ系、アイサンテクノロジーなど、開発パートナーとしても密接に関わりのある企業が名を連ねている。
同年8月には、ECU開発を手掛ける台湾のクアンタ・コンピュータからも10億円の出資を受けたと発表した。ECUの開発と商用化に共同で注力し、業界標準の獲得を目指すとしている。
2020年8月には、SOMPOホールディングスと資本提携を交わし、これまでの資金調達額が累計175億円に達したことを発表した。自動運転ソフトウェア技術とインシュアテックソリューション「Level IV Discovery」を一体として提供し、自動運転の社会実装を支援する自動運転プラットフォームの開発を両社で展開する方針だ。
2022年7月には、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が募集した「グリーンイノベーション基金事業」の自動運転ソフトウェアに関する研究開発項目に採択され、今後、同基金を活用して現行技術比100倍以上の電力効率を達成可能とする自動運転ソフトウェアの開発を推進すると発表した。
同基金の事業規模は2030年度までの9年間で計254億円を予定しており、既存株主のSOMPOホールディングスとヤマハ発動機に新たにブリヂストンを加えた3社を引受先としたシリーズBラウンドで121億円の資金調達を実施した。累計資金調達額は296億円になったという。
【参考】自動運転業界の資金調達については「2022年資金調達、「自動運転」が「EV」上回る!Cruiseが調達額トップ」も参照。
2022年資金調達、「自動運転」が「EV」上回る!Cruiseが調達額トップ https://t.co/pcMIvNiGch @jidountenlab #自動運転 #資金調達
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) March 12, 2023
■その他
国内初の自動運転セーフティレポートを公開
ティアフォーは2020年8月、国内初となる自動運転のセーフティレポート「Tier IV Safety Report 2020」を公開した。同社のこれまでの取り組みをはじめ、自動運転に対するアプローチや考え方、実証実験で得られた安全性に関する知見、今後の課題や対策などがまとめられている。
ODDの類型化や実証実験に至るまでのプロセスとインシデント対応、走行コースのリスクアセスメントなど、自動運転の導入を目指す上で必要となる知見が分かりやすく集約されている。導入を検討している事業者や自治体など、一度目を通してもらいたい内容だ。
【参考】セーフティレポートについては「【資料解説】ティアフォーが公開した自動運転のセーフティレポートとは」も参照。
【資料解説】ティアフォーが公開した自動運転のセーフティレポートとは https://t.co/iQbU378ShY @jidountenlab #自動運転 #ティアフォー #セーフティレポート
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) September 10, 2020
レベル4自動運転化ガイドライン公開
ティアフォーは2023年6月、レベル4自動運転化ガイドラインを公開した。保安基準への適合を含む量産向け自動運転EVの全体設計指針となるものだ。
ガイドラインには、E/Eアーキテクチャの設計からドライブバイワイヤ化、外界センサーの配置、自動運転システム開発、評価、実装例などが盛り込まれている。
同月には、自動運転機能に対応したEV生産を加速させる新たなソリューション「ファンファーレ」の提供も開始している。
駆動系の電動化モジュールやレベル4水準の自動運転機能に対応したE/Eアーキテクチャなどによって自動運転機能を再定義することが可能な設計・環境を開発済みで、これらの技術を活用することで利用者は自社ブランドを通じてレベル4水準の自動運転EVを製品化・販売・利用できるよう支援する。
ファンファーレは、ティアフォーが開発したEVをホワイトレーベル製品として提供し、利用者自らが自動運転機能を定義することで、自社ブランドで自動運転EVを生産できるようになる
まずは小型バスの提供から開始し、2024年までに9車種の商用車モデルを順次出荷する予定としている。
■【まとめ】プラットフォームサービスで裾野拡大 市場シェア獲得へ
自動運転ソフトウェア「Autoware」を軸に技術をオープンプラットフォーム化することで開発の裾野を広げ、「自動運転の民主化」を果たしながら市場シェアを獲得していく戦略だ。
ここ数年、Web.AutoやPilot.Auto、ファンファーレのようなソリューションを立て続けに発表するなど、プラットフォームサービスを大きく前進させている。レベル4実用化に向けた法環境が整う中、自動運転サービスに関心を示す企業や自治体の需要は潜在的に伸びているものと思われ、こうした層をどのように獲得していくかに注目が集まるところだ。
サービス提供・収益化のフェーズに本格移行し始めたティアフォー。新たなソリューション開発やパートナーシップの発表など、さらなる飛躍に引き続き期待したい。
▼事業戦略ビジョン報告用抜粋版|ティアフォー
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/industrial_restructuring/pdf/015_08_00.pdf
(初稿公開日:2019年1月22日/最終更新日:2023年10月19日)
【参考】関連記事としては「自動運転業界のスタートアップ一覧(2023年最新版)」も参照。
自動運転業界のスタートアップ一覧(2023年最新版) https://t.co/DAWR4iehj9 @jidountenlab #自動運転 #スタートアップ
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) January 31, 2023