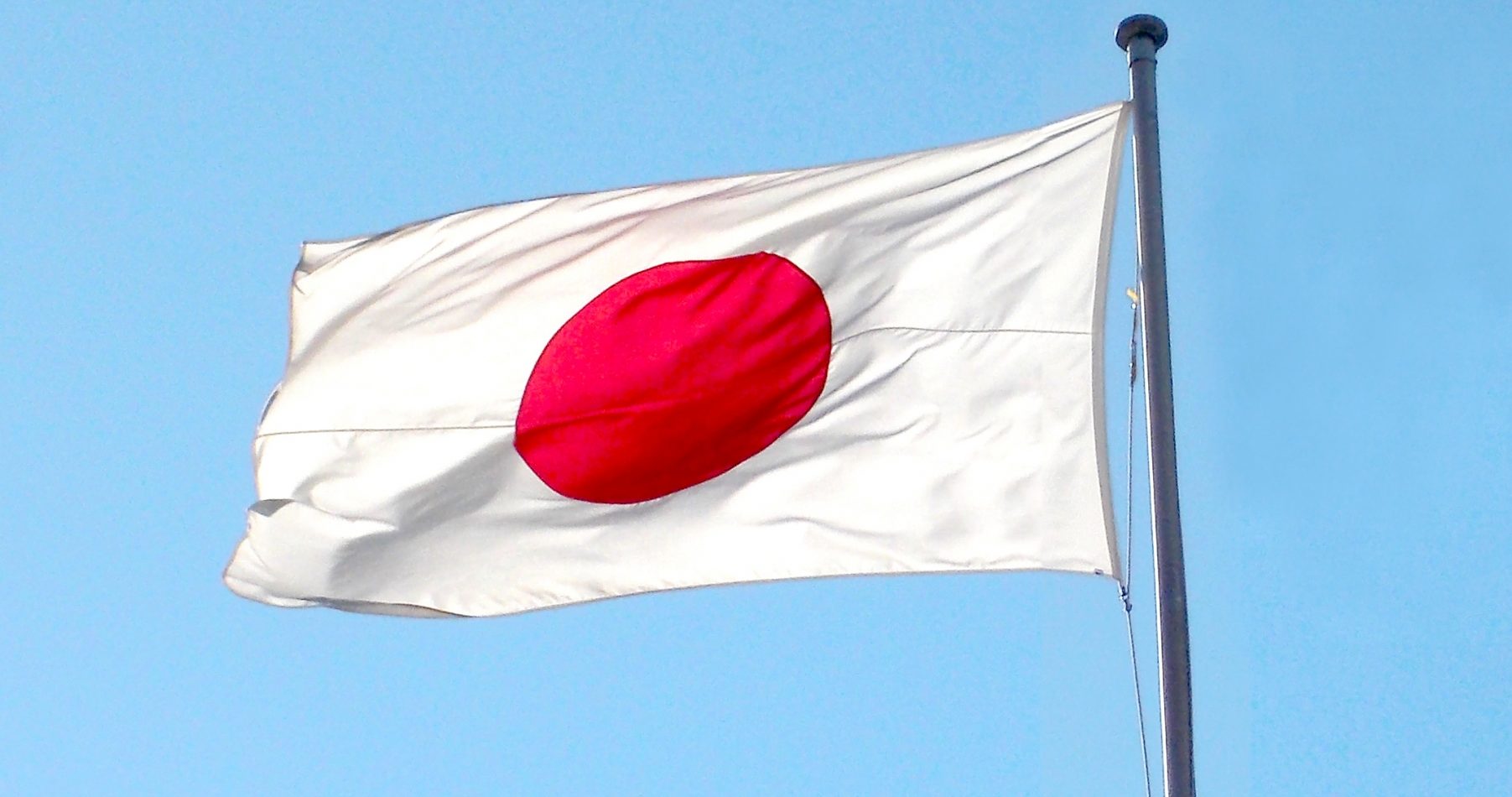
世界各国で実用化が始まった自動運転技術。米国や中国では自動運転タクシーが各都市で実装され、車内無人の移動サービスが本格化している。
日本でも自動運転サービスは始まっているが、あらゆるケースに対応するにはまだ環境整備が不十分な面もうかがえる。では、どこまで許されているのだろうか。
「日本で自動運転はできる?」――という観点から、現状の規制についてまとめてみた。
記事の目次
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |
| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |
| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |
| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| パソナキャリア |  |
| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |
| タクシーアプリDiDi |  |
| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |
| MOTAカーリース |  |
| お好きな車が月々1万円台から! | |
| スクエアbang! |  |
| 「最も安い」自動車保険を提案! | |
■自動運転関連の規制の歴史
従来はドライバーの存在が前提となっていた
自動運転は、ドライバーの存在を前提としたものとドライバーレスを前提としたものがある。前者は主に自家用車を対象とし、後者は主にサービス用途を想定している。いずれにしろ、最終的に行き着く未来は、あらゆるシチュエーションでドライバーの存在を必要としない完全自動運転だ。
一方、法に定められた自動車の規格や道路交通法など、従来の枠組みは人間のドライバーの存在を前提としており、自動運転に対応していなかった。人間のドライバーが果たすべき役割・義務が定められていたり、サイドミラーなど完全無人運転車には必要ない装置の搭載が義務付けられていたりするため、新たな法整備がなければ公道実証すらままならなかった。
日本では2010年代に官民連携のもと自動運転開発が本格化したが、法整備が整っていなかったため、「自動走行システムの公道実証実験のためのガイドライン」(2016年)や「遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準」(2017年)、「自動運転車の安全技術ガイドライン」(2018年)などを都度取りまとめ、実証環境を提供した。
道路使用許可基準関連では、2019年にハンドルやブレーキといった従来の制御装置と異なる特別な装置で操作する自動車(=特別装置自動車)に関する取り扱いについても盛り込まれている。
こうした指針を明確にし、民間各社の公道実証を加速しなければ、自動運転開発は進展しないのだ。
2020年施行の道交法でレベル3解禁

そして2019年、参議院で道路運送車両法と道路交通法の改正案がそれぞれ可決され、保安基準対象装置に自動運行装置が追加されるなど自動運転車の安全性を確保する制度が整備された。両法とも2020年4月に施行された。
道路運送車両法においては、新たに自動車の装置に「自動運行装置」が設けられた。自動運行装置は「プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置」で、「自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるもの」と定義されている。いわゆる自動運転システムの存在が法律に明記されたのだ。
一方、道路交通法には、自動運行装置を使用して自動車を用いる行為も「運転」に含まれる旨規定された。この自動運行装置を使用する運転者の義務として、作動条件外となった際直ちに適切に対処できる状態でいる場合に限り携帯電話使用等禁止規定の適用を除外することや、作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置(作動状態記録装置)による記録及び保存が義務付けられた。
これは、自動運転レベル3を可能にする改正だ。「自動運行装置を使用する運転者の義務」が定められているように、ドライバーの存在を前提としている。理屈上、車内無人で遠隔地にいるオペレーターがドライバーの役割をなすことも可能だが、システムから運転交代要請(テイクオーバーリクエスト)があった際は迅速に運転を行わなければならない。
目視外の遠隔操作そのものの取り扱いも不透明なため、レベル4に向けた過程として捉えた方が良さそうだ。
いずれにしろ、この改正でレベル3の公道走行が可能になり、ホンダが世界に先駆けてレベル3搭載自家用車を実現することとなった。同社は2020年11月、レベル3 システムの型式指定を国土交通省から取得し、2021年3月に渋滞時に自動運転を可能にするトラフィックジャムパイロットを含む「Honda SENSING Elite」を搭載した新型LEGEND(レジェンド)を限定リース販売した。
【参考】ホンダの取り組みについては「ホンダの自動運転戦略まとめ レベル3車両発売、無人タクシー計画は?」も参照。
【参考】自動運転レベル3については「自動運転レベル3とは?「条件付運転自動化」を解説。展開メーカーは?」も参照。
2023年の改正道交法ではレベル4走行を可能にする「特定自動運行」を定義
次のフェーズは2023年に訪れた。改正道路交通法が2023年4月に施行され、レベル4運行に相当する「特定自動運行」が定められたのだ。
改正法では、自動運行装置が使用条件を満たさなくなった際、ただちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるもので、その自動運行装置に係る使用条件で運行することを「特定自動運行」と定義した。
また、「運転」の定義についても、 「道路において車両又は路面電車をその本来の用い方に従つて用いること(特定自動運行を行う場合を除く。)をいう」(第2条17)としており、特定自動運行は運転に該当しないこととなった点もポイントだ。
自動運行装置によるレベル3は運転で、自動運行装置によるレベル4相当の特定自動運行は運転ではなく、明確に区別されたのだ。おそらく、人間が介在する「運転」と介在しない「特定自動運行」を切り分け、後々責任の所在などで区別するための措置と思われる。

特定自動運行は許可制
特定自動運行は許可制だ。まず、前提として使用する自動運行装置が国土交通省からODD(運行設計領域/走行環境条件)を付与されていなければならない。申請者は、場所や天候、速度など自動運転が可能となる条件を記載した申請書などを国土交通省に提出する。国土交通省は、その性能が保安基準に適合すると認めたとき、条件を付与する。
この国土交通省から認められた自動運行装置によって特定自動運行を行うものは、特定自動運行計画の策定や遠隔監視装置の設置、特定自動運行主任者の配置、自動運転システムで対応できない場合の措置など必要な体制を整え、運行を行うエリアの都道府県公安委員会に申請書を提出する。これが認められれば許可が下り、特定自動運行が可能になる。
【参考】特定自動運行については「【資料解説】自動運転レベル4を解禁する「道路交通法改正案」」も参照。
小型自動配送ロボットも届出制で運用可能に
2023年の道交法改正では、主に歩道などを走行する小型の自動配送ロボットを「遠隔操作型小型車」として定義し、公道走行を可能にしている。
遠隔操作型小型車は、「人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているもの」と定義された。
道路交通法施行規則では、車体の大きさが長さ120センチ×幅70センチ×高さ120センチ以下で、時速6キロメートルを超える速度を出せないことなどが定められている。通行場所は歩行者と同じで、歩行者相当の交通ルールに従うほか、歩行者に対しては進路を譲らなければならない。
走行するエリアを管轄する都道府県公安委員会へ事前届出を行うことでサービスを提供することが可能になる。
【参考】自動配送ロボットについては「自動配送・宅配ロボットの届出・審査の流れ」も参照。
2024年度までに7カ所で特定自動運行許可
このように、日本では自動運転で公道走行する環境がすでに整備されている。国土交通省が2025年4月開催のデジタル行財政改革会議で示した資料によると、北海道上士幌町、茨城県日立市、東京都大田区(羽田)、福井県永平寺町、長野県塩尻市、三重県多気町、大阪府大阪市(万博)、愛媛県松山市の8カ所でレベル4自動運転が実装されているという。
このうち、上士幌町を除く7カ所が特定自動運行許可を受けている。着々とレベル4サービスの輪は拡大しているのだ。
政府はデジタル田園都市国家構想総合戦略の中で、2025年度を目途に50カ所程度、2027 年度までに100カ所以上で地域限定型の無人自動運転移動サービスを実現する目標を掲げている。今後数年で取り組みは大きく加速し、自動運転サービスが身近な存在へと変わっていくことになりそうだ。
【参考】政府目標については「【最新版】自動運転、日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。
■自動運転を取り巻く課題
広範囲に及ぶ自動運転の許可はどうする?
自動運転走行可能な環境は一応整備されてはいるものの、課題はなお山積している。例えば、高速道路における特定自動運行だ。特定自動運行許可は対象エリアの都道府県公安委員会から得る必要があるが、複数の都道府県をまたがる場合、それぞれの都道府県公安委員会から許可を得なければならない。
現行ルールで不可能ではないとは言え、相当な時間を要することが想定される。各公安委に許可を求める手間もあるが、特定自動運行の許可基準には「地域住民の利便性又は福祉の向上に資すること」が求められており、公安委はエリア内の市町村長に意見聴取したうえで判断するとされている。
つまり、現行ルールでは走行エリアにかかるすべての市町村長から意見を聴取する必要があるのだ。高速道路における特定自動運行は本質的に地域性を意識したものではないにも関わらずだ。
高速道路においては、現在長距離自動運転トラックの実証が加速しているが、近い将来長距離バスなども実用化されるものと思われる。許認可の在り方については、今後改善する必要がありそうだ。
保安基準や事故原因究明などについても議論が加速
このほかにも、無人走行前提の自動運転車に対応した保安基準の改正や、事故が起こった際の原因究明と再発防止の在り方、被害が生じた場合における補償の在り方など、さまざまな点で課題は残っており、現在進行形で議論が進められている。
保安基準に関しては、保安基準の細目告示やガイドラインにおいて、現行の自動運行装置に係る細目告示の具体化に向けた検討を2024年度より進めており、2025年度にかけてとりまとめを行う。
具体化を進めた後、より適用基準が明確となるよう裁判例を含む道路交通法などの実運用の状況や交通流量などの統計情報、その時点における技術的状況、国際的な議論の動向などを踏まえながら、定量化に向けた検討を行う方針としている。
事故原因の究明に関しては、現在調査協力が義務付けられていないことから、基準認証などの段階における義務付けや、報告徴収権限の行使など、事業者による調査協力を促す方策について検討を進めており、2025年度にかけとりまとめを行う。
並行して、職権行使の独立性が保障されている運輸安全委員会のような組織による事故調査機関の設置に向けた検討や、捜査機関との連携の在り方、検証・分析のための情報共有の仕組み、報告・共有すべきデータ範囲、目的、方法などについても議論を進めている。
補償関連では、自賠法における損害賠償責任に関し検討を進めており、運行供用者責任の考え方、被害者補償の在り方などの点を含め、2025年中にとりまとめを行うとしている。
■【まとめ】自動運転はまだまだ発展する
現状、国内では自動運転走行が可能であるものの、突き詰めていかなければならない点が後から続々と出てきている状況だ。
例えば、市街地で柔軟に走行可能な自動運転自家用車が将来実用化される可能性が考えられるが、現行の仕組みでは対応できない。ODD(運行設計領域)における走行可能エリアや道路条件が広範に及ぶため、都道府県の枠に収まりきらず、かつ自家用車のため遠隔監視などの体制もサービス車両とは異なる。
自動運転技術の高まりとともにその利用の仕方も多様化するため、既製の枠に収まらないものが今後も次々と登場し、その都度対策を迫られる……といったいたちごっこのような状況がしばらくの間続きそうだ。
しかし、これは自動運転社会が進展している証左であり、既成概念を超える新たなソリューション・イノベーションが巻き起こるということでもある。引き続き業界の動向を注視したい。
【参考】関連記事としては「自動運転はいつ実用化される?(レベル別・モビリティ別) 市場予測は?」も参照。













