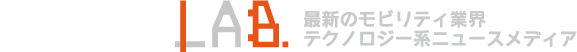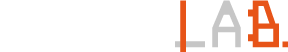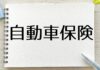コンサルティング大手のアーサー・ディ・リトル・ジャパン(Arthur D. Little Japan)=ADL=が作成した「モビリティサービスの事業性分析(詳細版)」が非常に興味深い。鉄道やタクシーなどの従来の交通手段に新しいモビリティサービスを導入した際の事業性を検証した内容で、ビジネスモデル構築に向けた参考資料として有用だ。
都市、地方を問わず新たなモビリティの導入を見据えた取り組みが盛んになる中、各地域においてどのようなモビリティサービスが適するかを模索する動きは年々強まっている。今回はこの資料の内容を紹介し、新たなモビリティサービスの可能性に触れていこう。
記事の目次
- ■「モビリティサービスの事業性分析(詳細版)」とは?
- ■鉄道事業・バス事業・タクシー事業の収益性分析
- ■マルチモーダルサービス事業のビジネスモデル・収益構造
- ■マイクロトランジット事業のビジネスモデル・収益構造
- ■貨客混載事業のビジネスモデル・収益構造
- ■タクシー配車事業のビジネスモデル・収益構造
- ■相乗りタクシー事業のビジネスモデル・収益構造
- ■ライドヘイリング事業のビジネスモデル・収益構造
- ■カーシェア事業のビジネスモデル・収益構造
- ■ロボタクシー事業の収益性の感度分析
- ■無人バス事業のビジネスモデル・収益構造
- ■無人配回送カーシェア事業のビジネスモデル・収益構造
- ■【まとめ】自動運転は採算面でも大きなインパクトをもたらす
■「モビリティサービスの事業性分析(詳細版)」とは?
この資料は、経済産業省が設置した「IoTやAIが可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会」が2019年4月に報告書を発表した際に、参考資料として添付された。アーサー社は経産省とともに同研究会の事務局を担っている。
▼モビリティサービスの事業性分析(詳細版)
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/smart_mobility_challenge/pdf/20190408_04.pdf
資料は、新しいモビリティサービスの事業性を検討するにあたって、既存の交通サービスの収益構造を基にサービス導入による変化を分析した内容となっており、各モビリティサービス事業の可能性について11項目にわたってまとめている。
以下、各項目の詳細を見ていこう。
■鉄道事業・バス事業・タクシー事業の収益性分析
【ここがポイント】
・JR6社平均の営業利益は7%
・全国バス事業者の営業利益はマイナス2%
・全国タクシー事業者の営業利益は1%
既存の交通事業での平均的な収益構造をもとに試算すると、全国平均的な利用量の近傍で各事業の損益が分岐しており、収益化が難しい地方での交通網衰退が懸念されるとしている。
JR6社平均の収益構造において、売上高を100%とした場合の営業利益は7%となっており、全国バス事業者の平均では同マイナス2%、全国タクシー事業者の平均では同1%となっている。輸送密度や輸送人員が低い地方ほど収益化が難しい構造であることを指摘している。
■マルチモーダルサービス事業のビジネスモデル・収益構造
【ここがポイント】
・交通サービスからの仲介手数料のみを収益源とする場合、収益化は難しい
複数の交通機関を連携させるマルチモーダルサービスにおいては、鉄道やバス、タクシーなどの交通サービスからの仲介手数料のみを収益源とする場合、収益化は難しい可能性が高いと指摘している。
ビジネスモデルの前提条件として、マルチモーダルサービスを利用する場合の移動パターンが大規模都市における利用者の移動パターンと同じであり、同サービスによる仲介手数料を3%と仮定し、また利用者一人当たりにかかるコストの構造は、他の交通系プラットフォーム事業者のコスト構造と同等であると仮定した場合、売上高に対する支払金利前税引前利益(EBIT)はマイナス38%になると試算している。
【参考】マルチモーダルサービスについては「MaaSアプリ、まとめて解説!新潮流、国内で続々リリース!」も参照。
MaaSアプリ、まとめて解説!新潮流、国内で続々リリース! https://t.co/QU7cFswsim @jidountenlab #MaaS #アプリ #まとめ
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) November 4, 2019
■マイクロトランジット事業のビジネスモデル・収益構造
【ここがポイント】
・経路の柔軟化によって、バス事業に比べ収益性が改善する可能性
デマンドバスなどのマイクロトランジット事業については、経路の柔軟化によって運行効率を高めることができれば、バス事業に比べ収益性が改善する可能性があるとしている。
前提条件として、バス事業に比べ経路の柔軟化によって運行効率が高まることで、走行距離が2割減少し、車両の耐久年数も2割増加すると想定し、また運行時間や経路のオンデマンド化に伴い、利用者数は増減せず、運行管理費などその他の管理費が売上高の4%分増加すると想定した場合、営業収益がマイナス2%からマイナス1%へ改善する試算をはじき出している。
車両1台当たりの収益性の感度分析では、元々のバス需要が乗車率20%程度の利用規模を割り込んでいる場合に、マイクロトランジットへの移行によって収益性の改善が可能としている。
■貨客混載事業のビジネスモデル・収益構造
【ここがポイント】
・貨客混載でバスの営業収益がマイナス2%からマイナス1%へ改善も
バス事業者が貨客混載事業を行う場合、物流による増収分がドライバーの工数増加やバスの走行距離増加の影響分を上回れば、収益性が改善する可能性があるとしている。
前提条件として、1日のバス運行12本のうち2本で貨客混載を行い、1回につき60サイズの荷物6個を運送すると想定し、また貨客混載を行う場合、物流センターへの移動に伴ってドライバーの工数とバスの走行距離が1.5倍に延伸すると想定した場合、営業収益がマイナス2%からマイナス1%へ改善すると試算している。
車両1台当たりの収益性の感度分析では、元々のバス需要が乗車率21%程度の利用規模を割り込んでいる場合に、貨客混載によって収益性の改善が可能としている。
■タクシー配車事業のビジネスモデル・収益構造
【ここがポイント】
・タクシーの運行効率化などが実現されない場合、営業収益が1%から0%へと悪化も
タクシー配車事業を行う場合、利用者数が増加せず運行上のメリットを実現できなければ、収益性がかえって悪化する可能性があると指摘している。
前提条件として、タクシー配車システムを導入しても利用者数は増加せず、システム導入費やシステム運用費がかかると想定し、また配車システムの導入に伴い、タクシーの運行効率化などのメリットも実現されないものと想定した場合、営業収益が1%から0%へと悪化すると試算している。
車両1台当たりの収益性の感度分析では、損益分岐点が1日あたりの輸送人員15.6人から15.9人に高まり、元々の需要に対して約2%程度の新規利用者を獲得できれば、収益性の維持が可能としている。
利用者側に配車アプリが浸透し、その利便性によってタクシーの利用者・利用回数が増加するかどうかが当然カギとなるが、配車サービスとセットになりつつある後部座席のタブレットを活用したデジタルサイネージ広告の導入や、配車アプリならではの新たな料金サービスの実現など、発展系を見通すことでプラスの効果も大きくなるものと思われる。
【参考】配車アプリについては「【比較】最強のタクシー配車アプリは?横浜で実験 JapanTaxi、DiDi、MOV、S.RIDE、Uberを解説」も参照。タクシーの広告効果については「電通の広告費調査、「タクシー広告は大幅増」の一文に注目せよ」も参照。
★情報更新しました★【比較】最強のタクシー配車アプリは?横浜で実験 JapanTaxi、DiDi、MOV、S.RIDE、Uberを解説 https://t.co/eVMqwFSflc @jidountenlab #タクシー #配車アプリ #比較 #まとめ
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) January 6, 2020
■相乗りタクシー事業のビジネスモデル・収益構造
【ここがポイント】
・利用者数が増加しない場合は営業収益が1%から0%へと悪化する可能性
相乗りタクシー事業を行う場合、利用者数が増加せず運行上のメリットも実現できなければ、収益性がかえって悪化する可能性があるとしている。
前提条件として、相乗りタクシーの導入によって全利用者のうち相乗り利用率10%、相乗り時の運賃割引率30%を想定し、また、相乗りマッチング・配車システムの導入によって利用者数は増加せず、システム導入費とシステム運用費がかかることを想定した場合、営業収益が1%から0%へと悪化すると試算している。
車両1台当たりの収益性の感度分析では、損益分岐点が1日あたりの輸送人員15.6人から16.6人に高まり、元々の需要に対して約2%程度の新規利用者を獲得できれば、収益性の維持が可能としている。
【参考】タクシーの相乗りについては「タクシー、配車アプリと相乗りアプリが連携!S.RIDE×AINORY、利便性アップ」も参照。
タクシー、配車アプリと相乗りアプリが連携!S.RIDE×AINORY、利便性アップ https://t.co/TUVl40UNiP @jidountenlab #タクシー #配車アプリ #相乗り
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) February 29, 2020
■ライドヘイリング事業のビジネスモデル・収益構造
【ここがポイント】
・タクシー事業からライドシェア事業への移行で、収益赤字を回復できる可能性
タクシー需要がわずかの地域でライドヘイリング(ライドシェア)事業に移行する場合、地域住民の協力によってドライバーへの賃金を抑えられれば、収益赤字を回復できる可能性があるとしている。
前提条件として、タクシー需要が1日当たり2人だけであるような地域において、タクシーの半額でサービスを提供し、かつドライバー業務を担う地域住民には、売上高から各種コストを差し引いた残額のみが賃金として支払われ、ドライバーは利用者からの依頼時のみ運転すると想定した場合、営業収益はマイナス68%から0%へと大幅に改善すると試算している。
■カーシェア事業のビジネスモデル・収益構造
【要点】
・駐車場コストがかさむステーション型カーシェアでは収益化が難しい
カーシェア事業では、駐車場コストが全体のうちの大きな割合を占めており、駐車場コストがかさむステーション型カーシェアでは収益化が難しい見込みとしている。
前提条件として、カーシェア車両の稼働率を20%と仮定し、設備関係費として、都市部の駅前などの利便性の高い場所における駐車費用と同額のコストがかかると想定。また、複数の駐車場で車両返却可能なステーション型カーシェアでは、元の場所へ返却するラウンドトリップ型に比べて車両1台当たりの駐車スペース及びコストが2倍になり、車両の再配置も必要になると想定した場合、営業収益はラウンドトリップ型1%に対し、ステーション型はマイナス105%と試算している。
ラウンドトリップ型においては、展開エリアの違いによって駐車場コストが抑えられる場合には、その減少分だけ損益分岐点となる稼働率の水準も低下する。たとえ駐車場コストがゼロでも、車両の稼働率が約7%以上である必要があり、そのためには展開エリアの人口密度が約7000人/平方キロ以上必要と試算している。
【参考】カーシェアについては「カーシェアの各社サービス料金を比較 市場拡大中のMaaS系サービス」も参照。
1分5〜15円が相場!カーシェアの7社料金を一挙に比較してみた トヨタ自動車も事業展開 https://t.co/MD0RjR2K4C @jidountenlab #カーシェア #料金 #比較
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) April 7, 2019
■ロボタクシー事業の収益性の感度分析
【ここがポイント】
・営業収益が平均的なタクシー事業の1%から26%へとなる可能性も
ロボタクシー事業を行う場合、車両関連コストが仮に従来の10倍程度になるとしても、ドライバーの人件費がゼロになれば収益性が大きく改善する可能性があるとしている。
前提条件として、自動運転によってドライバーの人件費はゼロになり、自動運転車関係のコストとして車両維持費や車両償却費が従来のタクシー車両の10倍になると想定。また、タクシー配車システムの導入に伴って、システム導入費及びシステム運用費がかかると想定した場合、売上高に占める労務費72%が0%になり、営業収益は平均的なタクシー事業の1%から26%に大幅に改善すると試算している。
需要が一定の輸送人員を上回り、自動運転車両の初期コストをカバーできる場合には、ロボタクシーによって収益性の改善が見込まれ、車両1台当たりの収益性の感度分析では、損益分岐点が1日あたりの輸送人員15.6人から11.5人に減少し、収益化を見込みやすくなるとしている。
【参考】ロボタクシーについては「自動運転タクシーの商用化に挑む世界の企業まとめ」も参照。
自動運転タクシーに商用化に挑む世界の企業まとめ ウェイモが一番乗り、中国でも実証スタート https://t.co/2hClnWhUeP @jidountenlab #自動運転 #タクシー #世界
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) September 30, 2019
■無人バス事業のビジネスモデル・収益構造
【ここがポイント】
・ドライバーの人件費がゼロになれば収益性が大きく改善
無人バス事業を行う場合、車両関連コストが仮に従来の3倍程度になるとしても、ドライバーの人件費がゼロになれば収益性が大きく改善する可能性があるとしている。
前提条件として、自動運転によってドライバーの人件費はゼロになり、自動運転車関係のコストは車両維持費や車両償却費が従来のバス車両のそれぞれ10倍、3倍になると想定。また、無人バス向けの配車システムの導入に伴うシステム導入費とシステム運用費がかかることを想定した場合、営業収益は平均的なバス事業のマイナス2%から7%に改善すると試算している。
需要の大小に関わらず運行頻度を変えない場合、コストがほぼ一定となるため、どのような利用規模でも無人バスによって収益性の改善が見込まれ、車両1台当たりの収益性の感度分析では、損益分岐点が1日あたりの輸送人員199人から177人に減少すると試算している。
■無人配回送カーシェア事業のビジネスモデル・収益構造
【ここがポイント】
・駐車場コストなどが軽減できれば収益性が大きく改善する可能性
カーシェア事業に自動運転技術を導入し、無人配回送が可能になった場合、車両関連コストが従来の10倍程度になるとしても、駐車場コストなどが軽減できれば収益性が大きく改善する可能性があるとしている。
前提条件として、ユーザーが自動運転機能を利用できるため単価が従来の2倍になると仮定し、自動運転によって車両の再配置に係る人件費はゼロになり、ステーション型に比べ駐車スペースやコストが半分になると想定。また、自動運転車関係のコストとして、車両維持費や車両償却費が従来のカーシェア車両の10倍になると想定した場合、営業収益はステーション型のマイナス105%からマイナス67%に改善すると試算している。
【参考】カーシェアの回送については「自動運転時代を先取り!「お届けカーシェア」の有望性」も参照。
自動運転時代を先取り!「お届けカーシェア」の有望性 将来は駐車場いらず?「所有から利用」加速 https://t.co/ZjjX2qPgLt @jidountenlab #自動運転 #カーシェア #デリバリー
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) October 9, 2019
■【まとめ】自動運転は採算面でも大きなインパクトをもたらす
総評として、カーシェアリングなど収益化には一定程度の人口密度が必要となるサービスもある一方、既存バス事業のデマンド化や貨客混載などのように、一定の需要を割り込むような特定条件下で収益性を向上できる可能性も存在し、導入地域に適したサービスの選択・設計が肝要としている。
また、自動運転によってモビリティサービスの収益性を更に向上できる可能性があるため、新しいモビリティサービスに取り組むビジネス上の意義は大きいことも指摘している。
特にタクシー事業は、人件費である労務費がゼロとなり、車両維持費+15%、車両償却費+21%を加味しても営業収益が25%向上するという試算は無視できない。配車サービス同様デジタルサイネージによる広告なども加えることで、その収益は一段と向上する。
高価とされる自動運転車も、普及期から一定以上経過することで生産効率や管理効率が上がり、単価が低減する可能性は高い。自動運転タクシーの利便性が増せば増すほど都市部を中心に自家用車離れに弾みがつき、好循環が生まれる。
自動運転のインパクトは高度な技術に留まらず、事業の採算面においても大きなインパクトをもたらすのだ。
【参考】関連記事としては「自動運転、ゼロから分かる4万字まとめ」も参照。