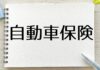自動運転車を活用した通年運行が、2024年12月末までに19カ所で行われていることが明らかになった。多くは実質レベル2運行に留まっているものの、レベル4認可を受けたエリアも続々と出始めており、石破政権下の2025年中に花を咲かせる取り組みが一気に増加しそうだ。
国内各所で進められている自動運転サービスの最前線に迫る。
▼自動運転の社会実装に向けた施策の取組状況、及び、今後の検討スケジュール|デジタル庁
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/6936350f-a070-42d7-8ab1-3bbd9471bba8/eaba1e1b/20250128_meeting_mobility-working-group7_outline_06.pdf
記事の目次
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |
| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |
| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |
| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| パソナキャリア |  |
| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |
| タクシーアプリDiDi |  |
| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |
| MOTAカーリース |  |
| お好きな車が月々1万円台から! | |
| スクエアbang! |  |
| 「最も安い」自動車保険を提案! | |
■自動運転サービスの通年運行の現状
2024年末で19カ所で通年運行が実現
デジタル庁所管のモビリティワーキンググループで示された資料によると、補助事業などを通じて2024年12月末時点で一般道における通年運行を行っているのは19カ所に上るという。
2024年度は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (自動運転社会実装推進事業)において地方公共団体から申請のあった事業のうち全都道府県に及ぶ99事業が採択されており、このうち26件で通年運行が予定されているという。

通年運行実施済みのエリア(19カ所)は以下だ。
- ①北海道上士幌町
- ②秋田県上小阿仁村
- ③茨城県常陸太田市
- ④茨城県境町
- ⑤千葉県横芝光町
- ⑥東京都大田区
- ⑦東京都(有明)
- ⑧愛知県春日井市
- ⑨愛知県日進市
- ⑩岐阜県岐阜市
- ⑪新潟県弥彦村
- ⑫石川県小松市
- ⑬福井県永平寺町
- ⑭三重県多気町
- ⑮大阪府河内長野市
- ⑯大阪府四條畷市
- ⑰愛媛県松山市
- ⑱愛媛県伊予市
- ⑲沖縄県北谷町
②⑧⑬⑮⑯⑲は定員5~7人ほどの小型カートを用いた自動運転サービスで、国内初の特定自動運行を実現した⑬永平寺町などが含まれる。ゴルフカーなどを改造した安価かつ小さい車体で低速運行することに特化しており、限定空間や交通量の少ない一般道で用いられることが多い。グリーンスローモビリティの延長線としても導入しやすく、最も実用化しやすいモデルと言える。

⑤⑫⑰は小型EVバスを用いた自動運転サービスで、混在空間で時速40キロ以下を目途に運行するケースが多い。2024年度の補助事業99件中、3分の1の33件がこのモデルに相当する。
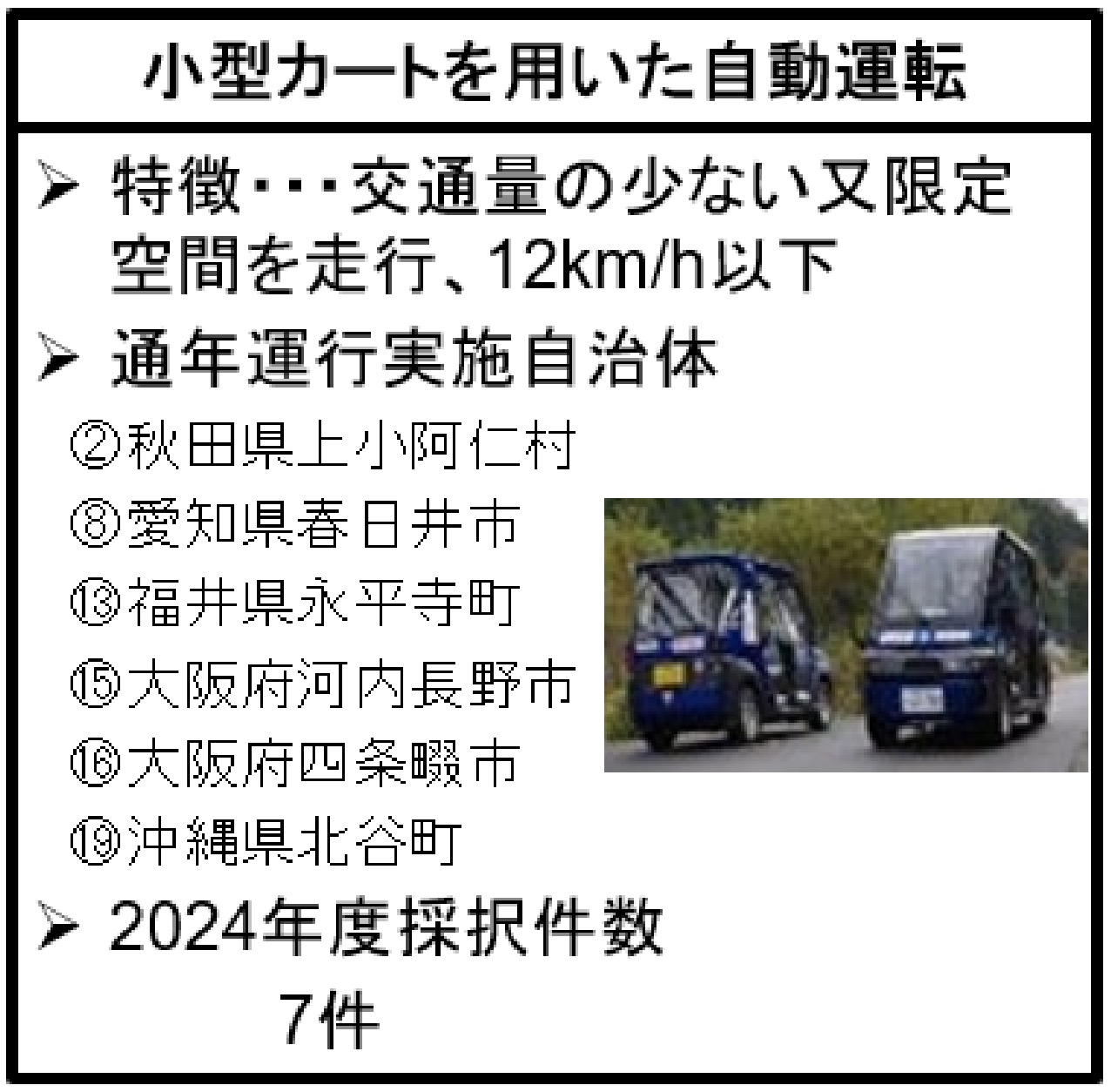
①③④⑥⑨⑩⑪⑭⑱は、ハンドルなどの制御装置を備えない自動運転専用車を用いた自動運転サービスを目指している。ARMA(Navya Mobility)やMiCa(Auve Tech)などが代表モデルで、汎用性に優れ完成度の高い車両により、導入速度を早めることができそうだ。

⑦は乗用車タイプで、自動運転タクシーを含むオンデマンドサービスに適している。特定ルートに制限しない走行エリアを検討しているものが多い印象だ。
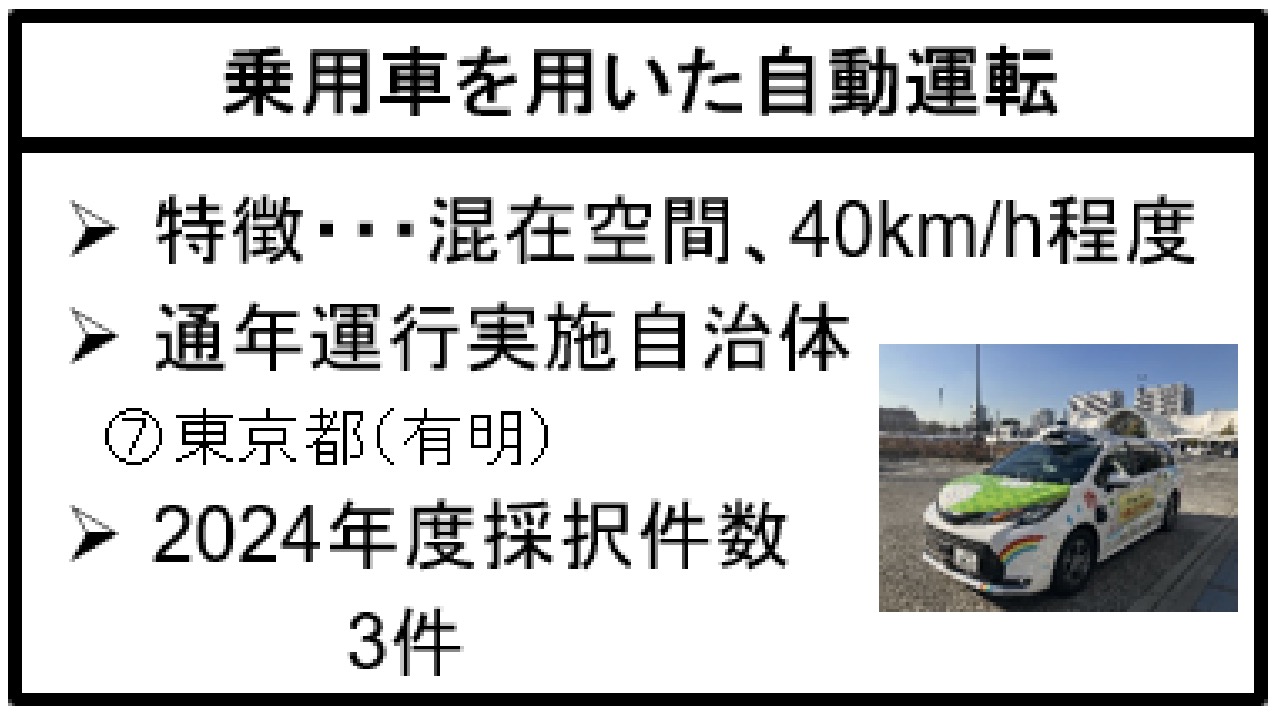
以下、種別ごとに各エリアでの取り組み概要を紹介する。
■小型カートを用いた自動運転サービス
導入容易でグリーンスローモビリティとしてなじみやすい小型カートタイプ
小型カートタイプは、産総研などが開発した磁気誘導線を用いたモデルと、名古屋大学が開発したゆっくりカートモデルの2タイプが主流のようだ。
福井県永平寺町では、鉄道廃線跡で歩行者・自転車用道路として活用している「永平寺参ろーど」を路線に設定し、自動運転移動サービス「ZEN drive」の試験運行を2020年12月に開始した。
磁気マーカーシステムを併用することで精度を高め、2021年3月に遠隔監視・操作型の自動運行装置として正式に認可を受け、保安要員のみのレベル3による運行に移行し、レベル4を解禁する道路交通法改正に合わせる形でレベル4システムの認可と特定自動運行許可を取得し、2023年5月に国内初の公道におけるレベル4サービスの定常運行を実現した。
現在、志比(門前)停留所から荒谷停留所間の約2キロを無人走行しているようだ。
沖縄県北谷町でも同様の車両・システムを使用しており、2021年3月に西海岸フィッシャリーナ地区~アメリカンビレッジ海岸線の約2キロのルートで車内無人のレベル3運行を開始している。
秋田県上小阿仁村では、道の駅を拠点とした自動運転実証に早くから取り組んでおり、暫定的ながら国内初の自動運転サービスを2019年に開始したことでも知られる。
一般車道路線の一部区間を一般車両が進入しない専用区間とすることで自動運転を実現したもので、現在はセーフティドライバーが同乗する実質レベル2で運行を続けている。
一方、愛知県春日井市では、自家用有償旅客運送として提供しているオンデマンド型送迎サービスに自動運転カートを導入し、2023年2月からレベル2運行を実施している。
誘導線を用いない名古屋大学の自動運転システム「ゆっくりカート」により、あらかじめ決められた運行ルート(停留所 128 カ所)の範囲内を走行する。
大阪府河内長野市では、開発団地再生モデルとしてグリーンスローモビリティを活用した移動支援サービスを展開しており、ここに自動運転カートを導入する。
電磁誘導線式のレベル2運行にすでに着手しており、2024年度は複数地域を1拠点で同時に遠隔監視する体制の整備やレベル4を見据えた運行体制の構築、自動運転専用道及び注意喚起表示の整備検討協議などを進めている。
大阪府四條畷市では、2024年に市レベル4モビリティ・地域コミッティを設置し、遠隔監視システム実証に着手しているようだ。
【参考】ゴルフカーベースの自動運転については「自動運転、日本でのレベル4初認可は「誘導型」 米中勢に遅れ」も参照。
■小型EVバスを用いた自動運転サービス
ティアフォー製Minibusなどの導入事例が続々
千葉県横芝光町では、町とBOLDLY、京葉銀行がティアフォー製の自動運転小型 EV バス「Minibus」を導入し、2024年2月に運行を開始した。
JR 横芝駅、東陽病院、カスミ横芝光店を結ぶ1周約5.5キロのルートでレベル2運行を重ねており、2025 年以降をめどに一部区間でレベル 4 運行を実現する構えだ。
石川県小松市では、ティアフォー、BOLDLY、アイサンテクノロジー、損害保険ジャパンが連携し、JR小松駅と小松空港間約4.4キロのルートで自動運転バスの通年運行を行っている。
運行は2024年3月に着手し、半年後の9月には利用者が1万人を突破したという。
愛媛県松山市では、伊予鉄グループが全国初となるレベル4による路線バスの本格運行を2024年12月に開始した。
EVモーターズ・ジャパン製のバスにBOLDLYの自動運転システムを搭載し、松山観光港と伊予鉄道高浜駅を結ぶ往復約1.6キロの路線を走行する。
ただ、運転席には大型2種免許を持つ保安員(特定自動運行主任者)を配置し、必要に応じて手動運転に切り替えるという。この「必要に応じて」の内容次第では、実質レベル2~3となる可能性も否定できないが、まずはレベル4サービスの誕生を祝したい。
【参考】伊予鉄の取り組みについては「NHK、「全国初の自動運転レベル4」と大誤報か ”必要に応じて手動介入”が前提なのに・・・」も参照。
■自動運転専用車両を用いた自動運転サービス
ARMAやMiCaが大活躍
ARMAやMiCaを導入するBOLDLYや、NAVYAを傘下に収めたマクニカなどが中心となって活躍している領域だ。基本的に車種が絞られるため、横展開が容易である点がポイントだ。
北海道上士幌町では、BOLDLYがARMAを導入し、レベル2運行を続けている。2024年5月には自動運行装置がレベル4認可を受け、同年10月には車内無人のレベル4実証にも着手した。
本格運行に期待が寄せられるところだが、豪雪地帯における冬季のレベル4実現の行方にも注目したい。
茨城県常陸太田市では、みつばコミュニティがマクニカと連携し、2024年3月にNavya MobilityのEVOによる定常運行を開始した。当面の間レベル2運行を積み重ねるとしている。
茨城県境町は、一般道のバス路線における定常運行に初めて自動運転車を導入した自治体として名を馳せた。2020年11月に定常運行を開始しており、すでに丸4年が経過している。
町として、観光や経済活性化などにつなげる策が注目を集めているほか、運行を担うBOLDLYも同町での取り組みから膨大な知見を積み重ねている。その意味でも非常に有用だ。
ただ、レベル4への移行はてこずっているようで、未だ無人化は実現していない。このあたりのハードルに関するレポートが待ち遠しいところだ。
東京都大田区では、HANEDA INNOVATION CITYでレベル4運行が始まっている。BOLDLYらが取り組んでおり、2024年6月に特定自動運行許可を取得し、同年8月から敷地内でレベル4運行を行っている。
当面は車内に特定自動運行主任者を配置するとしており、現在の状況は不明だ。また、近隣の一般車道への拡大も検討しており、今後の取り組みにも期待が寄せられる。
愛知県日進市では、BOLDLYらの協力のもと2023年1月にARMAを導入し、2024年2月には2台目、そして2025年2月には3台目となるティアフォー製Minibusを導入し、運行ルートを拡大している。
岐阜県岐阜市では、キャッチコピー「自動運転バスがいつも走っているまち」のもと2023年11月にARMAによるレベル2運行を開始した。
2028年まで継続運行する長期計画で、どの段階でレベル4を実現するか要注目だ。
新潟県弥彦村では、BOLDLYらの協力のもと2024年2月からMiCaの通年運行が行われている。上士幌町同様弥彦村も積雪地帯で、冬季含めどのようにレベル4を実現するか注目だ。
三重県多気町では、商業リゾートVISON 構内で自動運転運行を行っている。BOLDLYが導入するMiCaが2024年10月、VISON内の自動運転専用レーンと専用レーン外の一部道路を対象にレベル4認可を受けている。
愛媛県伊予市でも、BOLDLYらの協力のもと2024年1月からMiCaによる定常運行が行われている。
【参考】ARMAによる運行については「電磁誘導線を使わない「自動運転レベル4」、日本で認可!鹿島やBOLDLYが発表」も参照。
■乗用車タイプの自動運転サービス
MONET Technologiesやティアフォーがお台場で実証に着手
東京都(有明)の取り組みは、おそらくMONET Technologiesかティアフォーによる移動サービスと思われる。同社は2024年8月、東京臨海副都心(有明・台場・青海地区)の公道で自動運転技術を用いた移動サービスを2024年度後半に開始すると発表した。
米May Mobilityの自動運転システムを搭載したトヨタ製ミニバン「シエナ」2台を導入し、レベル2運行を行う内容だ。
ティアフォーは、トヨタ製JPN TAXIを改造した自動運転タクシーで実証に着手しており、2024年11月に事業化を目指すとしている。
先行する米国、中国では自動運転サービスの中心となっている自家用車モデルだが、国内では希少と言える。今後の動向に大きな注目が集まる取り組みだ。
【参考】ティアフォーの取り組みについては「東京に自動運転タクシー!トヨタ車で11月事業化へ ティアフォー発表」も参照。
【参考】MONET Technologiesの取り組みについては「理由不明!トヨタ系モネ、自動運転シャトルに「国産技術」搭載せず」も参照。
■【まとめ】2025年度目標は全都道府県での通年運行計画策定
2023年度の一般道における通年運行事業は約10カ所で、この1年で倍増した格好だ。政府は、2025年度に全都道府県での通年運行の計画策定または実施を目指す目標を掲げており、同年度を目途に50カ所程度、2027年度には100カ所以上で自動運転サービス実現を目指す。
この目標は岸田政権下で策定されたもので、石破政権下では今のところ目標を左右する新たな動きはない。
99件に及ぶ補助事業採択事業はすでに全都道府県にまたがっているが、正直一部は受動的な印象が強い。温度差が大きいのだ。
全都道府県にこだわらず、まずは先行地域をはじめとしたやる気のある地域を猛烈プッシュし、真のレベル4構築を進めた方が良い気もする。多くはティアフォーやBOLDLYらが手掛けるシステムであり、良い意味で寡占的であるため、横展開が容易だ。
成功事例とともに近未来のビジョンを見通せる状況になれば、受動的・消極的な自治体も重い腰を上げるだろうし、他の開発事業者も事業展開しやすい環境となる。
2025年中に自動運転車による通年運行エリアはどこまで増加し、このうちレベル4への道を開くエリアが何カ所誕生するのか。
普及拡大期に入りつつある自動運転サービスの動向に引き続き注目したい。
※自動運転ラボの資料解説記事は「タグ:資料解説|自動運転ラボ」でまとめて発信しています。
【参考】政府方針については「岸田首相は「自動運転メガネ」!?通年運行、14都道府県に拡大」も参照。