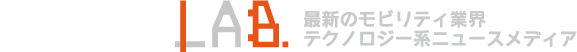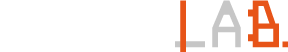米Google(グーグル)系の自動運転開発会社Waymo(ウェイモ)が2019年11月までに、米アリゾナ州フェニックスでセーフティドライバーを同乗させない無人自動運転タクシーのサービス提供を一部で開始したようだ。
2018年12月に自動運転タクシーサービスを開始して以来、万が一に備えセーフティドライバー同乗のもと運用を続けてきたが、1年足らずで無人自動運転にこぎつけた形だ。
このセーフティドライバーの有無は、「無人」を標榜する自動運転においては非常に重要なステップとなる。セーフティドライバーによる車両制御への介入の必要性そのものをクリアしたからだ。
この無人化の「壁」はどのくらい高いものなのか。今回は、セーフティドライバーの有無に焦点を当て、自動運転が実証段階からどのように無人化を図っていくのかを見ていこう。
【参考】ウェイモの自動運転タクシーについては「Google系自動運転タクシー、遂に「完全無人化」 ローンチ1年弱で」も参照。
記事の目次
■完全無人では「万が一」が許されない
各地で自動運転の実証実験が進められているが、公道における実証の際は、基本的にセーフティドライバーの乗車が義務付けられている。自動運転システムの故障や自動車そのものの故障、他の交通事故に巻き込まれるといった外部要因など、不測の事態が発生した際に、責任をもって道路交通の安全を確保するためだ。
自動運転車は事故を起こさないように設計・開発が進められているが、現実問題として事故を100%防ぐことは限りなく不可能に近い。実証段階においてはなおさらで、不測の事態を経験値として生かし、一つひとつクリアして想定内に収めていくことも自動運転の精度を高めていくのに重要な過程となる。
もちろん、それを理由に実証段階の自動運転車が事故を起こして良いはずもない。開発段階にある自動運転システムの不備を補うため、また外部要因による事故などを極力防ぐため、セーフティドライバーが乗車し、万が一の際に備えているのだ。
また、万が一発生してしまった事故時の対応についても、セーフティドライバーの有無は大きく影響する。セーフティドライバーが乗車していれば、事故相手への対応や警察などの機関への迅速かつ詳細な報告、現場の安全確保などを速やかに図ることができる。
いわばセーフティドライバーは事故を未然に防ぐ最後の砦であり、自動運転におけるバックアップシステムとなるのだ。また、事故時の対応を行う現場の車両責任者となる側面も持つ。こうした存在を「無人」にするということは、それを補う技術の高度化や新装備など、相応する安全の確保・保証が前提となる。
言い換えると、無人自動運転車が何らかの理由により事故を起こした場合、「セーフティドライバーが同乗していれば未然に防ぐことができた」という状況はあってはならないのだ。「セーフティドライバーが手動運転していても回避することができなかった」という状況以外、あらゆる事態を想定して事故を回避するシステムが無人自動運転には求められるのである。
なお、警察庁は2016年に発表した「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」において、「運転者となる者が実験車両の運転者席に乗車して、常に周囲の道路交通状況や車両の状態を監視(モニター)し、緊急時等には、他人に危害を及ぼさないよう安全を確保するために必要な操作を行うこと」を求めている。
【参考】公道実証については「自動運転の公道実証実験における重要7条件まとめ」も参照。
また、翌2017年には、自動車から遠隔に存在する運転者が通信技術を活用して自動車の運転操作を行う「遠隔型自動運転システム」に対応するため、自動運転システムの構造や緊急時の措置、走行方法などを定めた「遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準」も発表している。
遠隔型の場合はセーフティドライバーの乗車を必要としないが、乗車する場合と同等の要件が遠隔監視・操作者に求められている。
技術開発中の実証段階においてセーフティドライバーやそれに相応する存在は必要不可欠であり、裏を返せば、高度な自動運転技術が完成して初めて「無人」が許されることになるのだ。
【参考】関連記事としては「自動運転車に実証実験・テスト走行が必須な理由 実用化に向けて回避すべき危険・リスクは?」も参照。
知られざる舞台裏…自動運転車の実証実験、その全貌を徹底解説 イノベーションに向けた試行錯誤、Ai技術で自動車業界の変革近し 実施するスタートアップも|自動運転 https://t.co/CfKdnIi7RE @jidountenlab #自動運転 #実証実験 #テスト #知られざる舞台裏 #検証
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) August 23, 2018
■周囲の理解が最初は得られにくい
新しい技術やサービスに対し、すぐに全面的に受け入れられる人は少ない。懐疑的であったり、不安視・静観する人の方が多いのではないだろうか。自動運転であれば、その傾向はより顕著に表れるだろう。
自動運転は道路交通をはじめ人間の体を機械に預ける新技術だ。感覚としては、これを無条件で受け入れられる方が普通ではないだろう。
こうした自動運転の公道実証が各地で進められているが、セーフティドライバーの有無は周辺住民の社会受容性(アクセプタンス)にも影響を与える。
セーフティドライバーの有無にかかわらず、同一の自動運転システムが運転操作を担っていることに変わりはないが、バックアップシステムとして「人」が乗っている安心感は思いのほか大きい。いざというときに、従来と変わりのない手動運転が可能であれば、その安心感は従来のバスやタクシーとほぼ変わらないものとなる。
こうした安心感を担保しながら、少しずつ自動運転という新技術への理解を深めてもらう意味でも、セーフティドライバーは一役買っていると言えるだろう。
【参考】関連記事としては「自動運転のアクセプタンス(受容性)向上の鍵は「モニター参加」にあり」も参照。
自動運転のアクセプタンス(受容性)向上の鍵は「モニター参加」にあり https://t.co/gYIJgKRbrt @jidountenlab #自動運転 #社会受容性 #アクセプタンス
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) August 23, 2019
■「念のため係員も」から「完全無人」へのステップはどのように?
では、セーフティドライバーから脱却し、無人化を進めるにはどのようなステップを踏むのか。
実証を重ねる段階で、実際にセーフティドライバーが介入した事案を一つひとつ検証し、改良を重ねてセーフティドライバーの介入がなくなる段階までシステムを向上させることが第一段階となる。
合わせて、新たな不確定要素や想定外といった事案が発生しない段階まで実証を積み、自動運転システムの性能に太鼓判を押すところまでもっていって初めて無人化に踏み込むことができるのだ。
ウェイモの自動運転タクシーも、当初はセーフティドライバー同乗のもと運用していたが、実用実証を重ね、同社の判断として自動運転システムが無人化の域に達したことを確認したからこそ無人サービスを開始したものと思われる。
なお、法的要件など客観的な基準がない場合、こうした判断は各社に委ねられることになる。セーフティドライバーの介入がゼロになるまで改良を重ねる企業もあれば、手動運転よりも精度が高まった段階で無人化に踏み切る企業もあるだろう。
【参考】関連記事としては「自動運転の普及へ、「安全」と「安心」の違いを心得えよう」も参照。
自動運転の普及へ、「安全」と「安心」の違いを心得えよう https://t.co/lu72VVUry9 @jidountenlab #自動運転 #安全 #安心
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) November 5, 2019
■ちなみに今の介入度はどれくらい?
中山間地域における道の駅などを拠点とした自動運転サービスの実証実験を進める国土交通省は、この実証実験の結果などを踏まえ自動運転車が普及していくために必要な道路空間のあり方などを議論する「自動運転に対応した道路空間に関する検討会」を設置しており、この中で2017年度の実証実験において手動介入した事案についてまとめている。
実証実験の総走行距離は約2200キロメートルで、手動介入した回数は計1046回に上る。1キロ当たり0.48回、1000キロ換算だと約480回介入する計算だ。このうち、単路における介入が全体の56%、交差点・駐車場がそれぞれ5%、その他34%となっている。
要因別では、「路上駐車の回避」が最多の17%を占め、次いで「GPSなどの自己位置特定不具合」が12%、「対向車とのすれ違い」「自転車・歩行者の回避」がそれぞれ7%、「除雪した路側の雪の検知」「雑草などのセンサー検知」「交差点における右折待ちや道譲り」がそれぞれ5%、「駐車場における駐車車両の回避」が4%、「後続車による追い越し」が2%となっている。
なお、海外に関するデータでは、要因別は不明だが米カリフォルニア州車両管理局(DMV)が同州における開発各社の公道実証テストの解除報告(Disengagement Report=手動介入と同義)に関するデータをまとめている。
この報告書によると、2017年12月から2018年11月までの期間、28社が公式に走行テストを実施しており、走行距離は計203万6296マイル(325万8074キロメートル)で、手動介入回数は計14万3720回となっている。平均すると、1キロメートル当たり約0.044回、1000キロメートルでは約44回となる。
1000キロメートル当たりの離脱数では、少ない順にウェイモが0.06回、GMクルーズが0.12回、zooxが0.33回と続く。多い順では、ウーバーが約1630回、アップルが約545回の状況だ。また、日本企業では、日産が2.97回、トヨタが約246回、ホンダが約286回となっている。
それぞれ自己申告であり、手動介入に対する考え方などの違いもあるためあくまで参考にとどまるが、こういったデータが統一された基準によって適切に公表されれば、各社の開発能力や開発姿勢などをうかがうことができそうだ。
■【まとめ】無人自動運転の高い壁は徐々に低く 完全無人自動運転の実現は遠くない
このようにセーフティドライバーの有無で自動運転のハードルは大きく変わり、「人」というバックアップシステムをなくすためには相応のシステムの高度化を図る必要がある。
しかし、ウェイモが無人化に踏み切ったように、徐々にそのハードルに迫る企業は増えている。無人による自動運転が乗り越えられる壁になりつつあるのだ。
国内でも2020年に一部で自動運転サービスが始まる予定となっている。当初はセーフティドライバーが同乗する可能性も高そうだが、完全無人が実現する時代もそう遠くないように感じる。
【参考】関連記事としては「自動運転、ゼロから分かる4万字まとめ」も参照。