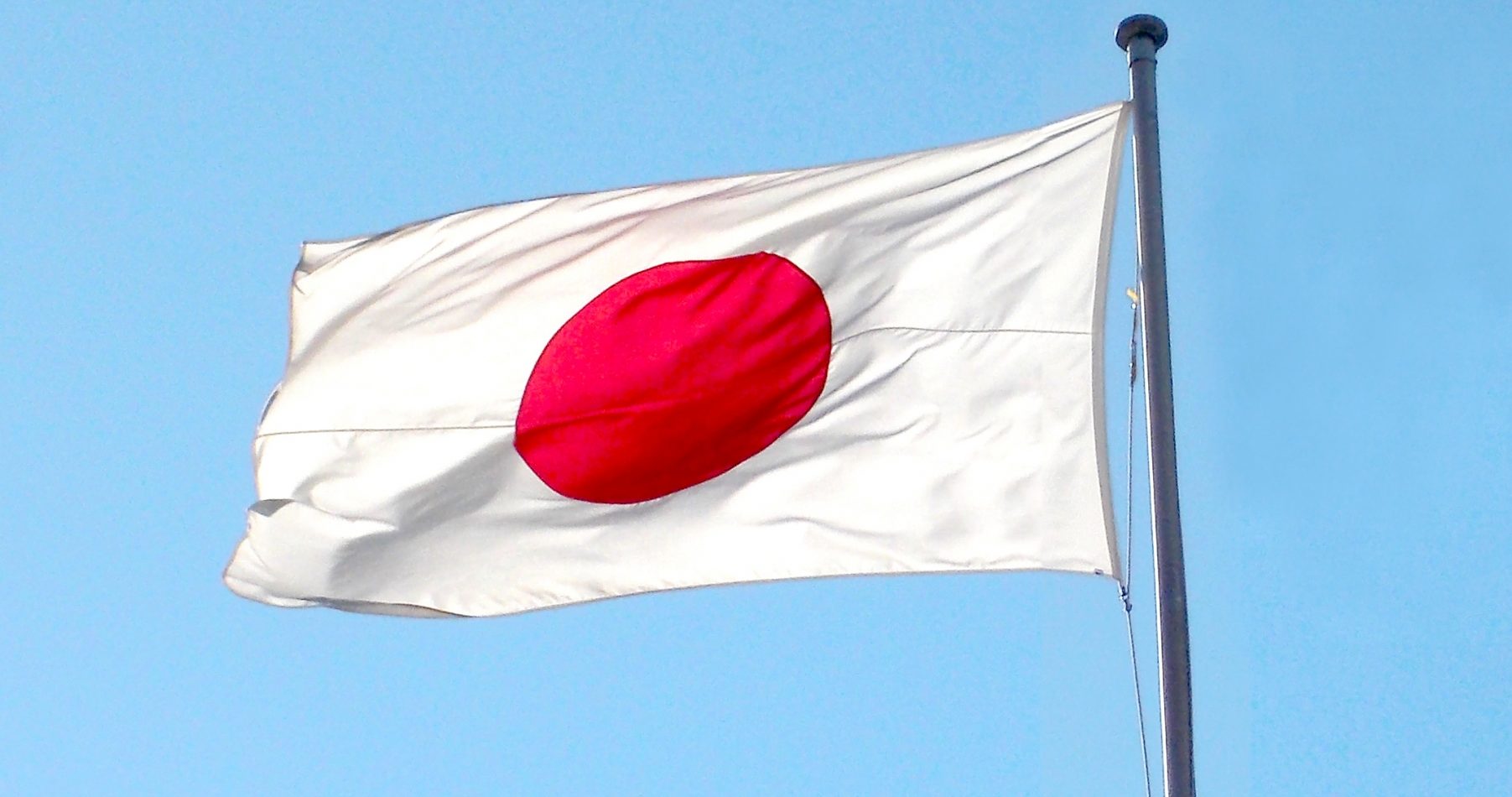
自動運転開発を手掛けるティアフォーが、自動運転タクシーの新型プロトタイプを開発した。車両の仕様やソフトウェア構成を含む自動運転システムの設計を公開し、業界の開発を促進していく方針だ。
同分野では米国や中国勢が二歩も三歩も前を進んでおり、日本は周回遅れの状況だ。巻き返しは容易ではない。しかしこの「捨て身戦略」と言えなくもない、ティアフォーが推進するオープンソース戦略がしっかりと実を結べば、状況は一変するかもしれない。
同社の動向とともに、オープンソース戦略のポテンシャルに迫る。
記事の目次
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |
| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |
| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |
| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| パソナキャリア |  |
| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |
| タクシーアプリDiDi |  |
| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |
| MOTAカーリース |  |
| お好きな車が月々1万円台から! | |
| スクエアbang! |  |
| 「最も安い」自動車保険を提案! | |
■ティアフォーの動向
設計情報を公開し、業界の取り組みをサポート
発表によると、ティアフォーはハンドルとペダルの操作が不要な自動運転タクシーの新型プロトタイプを開発し、2025年3月に神奈川県相模原市内で開催されたイベント「未来の乗り物大集合! 最新テクノロジーに『触れよう!』『乗ってみよう!』」で車両を公開した。

車両の仕様やソフトウェア構成を含む自動運転システムの設計については、自動車業界の関連企業が自動運転タクシー市場に参入しやすくなるよう公開する。日本発の自動運転タクシーの標準モデルの構築が進み、全国各地で同サービスの実用化が促進されるとともに、世界市場における日本の競争力強化に期待が持たれる。
車両は、既存のEVプラットフォームをベースにしている。自動運転タクシーに特化した内外装を独自設計し、自動運転用のオープンソースソフトウェア「Autoware」を最適に利用するためのセンサー構成を採用している。
また、大規模言語モデルを活用した対話エージェントを新規に開発し、乗車時の目的地設定などのユーザー体験の向上も実現したという。
詳細スペックは不明だが、ティザー画像には前面に各種センサーが取り付けられたワンボックスタイプの車両が映し出されている。車内には、ハンドルをはじめインストルメントパネルも見当たらない。代わりに、小さなカウンターデスクのようなテーブルの上にディスプレイが設置されている。助手席は後ろ側を向いた対面座席にできるようだ。

Waymoや百度のフリートは1,000台超、開発環境は好循環
多くの方がご存じのように、自動運転タクシーは米国と中国が頭3つ分ほど抜け出している。米国では、グーグル系Waymoがアリゾナ州やカリフォルニア州、テキサス州で無人サービスを実現している。走行エリアは延べ1,000平方キロを超え、フリートも1,000台を超えているものと思われる。
中国の百度は、北京や上海、広州、重慶、武漢、深センなど大都市を中心に広域展開しており、フリートは軽く1,000台を超えている。累計乗車回数は2025年1月に900万回を突破した。2024年11月に香港でも公道走行ライセンスを取得し、左側通行・右ハンドルの実証にも着手したようだ。
一方、日本はようやく公道実証が本格化する段階だ。Waymoや百度で言えば、2020年以前、5年以上前の段階に相当する。自動運転開発における5年以上の差は致命的と言っても過言ではない。
自動運転開発は走行経験がモノを言う。より多くの車両でより多くの道路を走行し続けているWaymoらは、その開発速度を加速度的に高めており、この差を埋めるのは至難の業だ。
そして、Waymoは日本進出を表明している。このWaymoにティアフォーが対抗するには、正攻法では相当厳しいと言える。
AWFアライアンスで1,000台超のフリートに対抗可能に
では、打つ手はないのか?――と言えば、そんなこともない。ティアフォーには大きな武器がある。それはオープンソース戦略だ。オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」の開発パートナー網を拡大することで、一社ではなしえない開発速度を実現することができる。
Autowareの業界標準を目指す国際業界団体「The Autoware Foundation」には、すでに60を超える企業・団体、2,500人を超えるエンジニアが参画しており、世界各地で開発プロジェクトを進めている。
こうしたメンバーがそれぞれ研究開発を進め、その成果を効果的に持ち寄ることができれば、開発速度は飛躍的に増す。ティアフォー一社でできることには限界があるが、こうしたパートナーが一丸となれば、Waymoに対抗できるはずだ。
連携の中身がカギを握りそうだが、Autowareが自動運転タクシーとして公道走行可能な水準に達すれば、世界各地から有力なデータを集めることができる。1,000台超のフリートを抱えるWaymoに単独でタメを張ることは難しくとも、それに匹敵する開発規模を実現することが可能になるのだ。
こうしたアライアンスは、局所的な一点突破型開発は難しいかもしれないが、さまざまな観点から研究開発した多様性あふれる技術を共有することができる。
このアライアンスのメリットを発揮することができれば、世界展開を始めたばかりのWaymoに追い付き、追い越すことも夢ではない。
今はまだ周回遅れかもしれないが、日本発の技術が世界を舞台に躍進する未来に期待を寄せたいところだ。
【参考】ティアフォーの取り組みについては「ティアフォーの自動運転/Autoware戦略」も参照。
■ティアフォーの自動運転タクシー事業
2019年に自動運転タクシー事業に着手
ティアフォーは2019年、JapanTaxi(現GO)、損害保険ジャパン日本興亜、KDDI、アイサンテクノロジーとともに自動運転タクシー事業化に向けた取り組みを開始すると発表した。ユニバーサルデザイン仕様のJPN TAXI車両に自動運転システムを統合し、サービス実証に着手した。
東京都内の西新宿エリアを中心に、5Gを活用した遠隔自動運転の性能評価や他社運行管理システムとの連携など実証を積み重ね、徐々に技術を高めてきた。
【参考】関連記事としては「「世界で戦う土俵ができた」…自動運転OS開発のティアフォー」も参照。
都内で段階的にサービス拡張、2027年には都内全域を対象に
2024年5月には、従来のタクシー配車が困難な時間帯・経路を対象に、レベル4水準の自動運転タクシーによる新たな移動サービスの提供を開始する計画を発表した。
都内のお台場エリアで複数拠点間によるサービス実証にすでに着手しており、2024年11月から交通事業者と共同で事業化を目指すという。
その後、段階的に区画と拠点数を拡張し、2025年にお台場を含む都内3カ所、2027年に都内全域を対象として、既存の交通事業と共存可能な自動運転タクシー事業を推進する。また、自動運転タクシー事業に適した新型車両の開発と製造も並行して進め、順次市場に投入していくとしている
ロボットタクシーの技術検証用としてタクシー型リファレンスデザインを適用したJPN TAXI車両は、お台場や西新宿といった交通量の多い走行環境に対しても運行設計領域を定義できる水準に達しているという。準備万端の様子だ。
2025年2月には、段階的な事業化の一環としてお台場と西新宿でプレサービス実証を実施したことを発表した。
自動運転タクシー事業の広域展開に向け、既存の運行設計領域を適宜拡張し、新たな交通環境に適合させるための技術検証や導入プロセスの構築を行ったという。
具体的には、両エリアの特定区域において、ティアフォーの自動運転システムを搭載したJPN TAXI車両を走行し、複雑な交通環境下における交差点右左折や路上駐車車両の回避を含む約500ものさまざまなシナリオを評価した。
その結果、交通量の多い走行環境に対しても既存の運行設計領域を適合・拡張できることを確認したほか、広域の自動運転に必要な技術課題を抽出することができたとしている。
【参考】ティアフォーの自動運転タクシー事業については「東京に自動運転タクシー!トヨタ車で11月事業化へ ティアフォー発表」も参照。
また、お台場では、利用者が音声入力で目的地を指示し、東京テレポート駅周辺を中心に走行した。1回の乗車における平均走行距離は約3キロで、総走行距離は約354キロに達した。
歩行者や交通量が多い西新宿では、利用者が配車アプリで7つの目的地から1カ所を選択し、指定された経路を走行した。1回の乗車による平均走行距離は約3キロで、総走行距離は約622キロだった。
同実証で得られた成果は、自動運転タクシー用リファレンスデザインに反映し、自動車業界の関連企業に提供していく。これにより、自動運転タクシーに適した車両開発・製造の参入障壁が低減化され、さまざまな自動車メーカーの同市場への参入が容易になるという。
2027年度までに、新たに自動運転タクシーを導入する地域に対し、リファレンスデザインを活用することで3カ月以内に自動運転タクシーの運用を開始できるサービスモデルを構築し、全国各地におけるロボットタクシーの社会実装に貢献していくとしている。
AWFにはArmやAMD、AWS、Foxconnなど世界企業が参画
Autowareのオリジナル版は、2015年に名古屋大学の加藤真平准教授(当時)によって開発・ローンチされた。当初からオープンソースプロジェクトとして、またROSをベースとした自動運転に関心のある研究者のためのR&Dプラットフォームとして研究開発されており、自動運転に関連するさまざまな事業機会を追求するためティアフォーが設立された。
2018年12月には、米Apex.AI、英Linaroと共同で自動運転OSの業界標準を目指す世界初の国際業界団体「The Autoware Foundation(AWF)」を設立すると発表した。
誰もが無償で使える自動運転OSとしてAutowareを世界でいっそう普及し、国や企業を問わず自動運転が早期実現することを目的としている。
Autowareの開発を主導するティアフォーは、オープンソースのエコシステムの可能性に共感し、Autowareのすべての権利をAWFに譲渡している。
ティアフォー創設者の加藤CEOは、AWFの理事長を務めている。また、プロジェクトやエコシステムの方向性を決定する技術委員会やワーキンググループでは、ティアフォーのシニアリーダーが議長や副議長として活躍しており、AWFに参画するメンバー企業や機関と緊密な連携を図っている。
AWFのプレミアムメンバーには現在、ArmやAMD、Amazon Web Services、driveblocks、Foxconn、AutoCore、ITRIなど19社、産業・政府系メンバーには、アイサンテクノロジーやADLINK、eSOL、日立、Astemo、Kudan、NTTデータ、マクニカ、NXP、ファーウェイ、TomTomなど38社がそれぞれ名を連ねている。
そうそうたるメンバーが揃っているが、後方支援組が多い印象もぬぐえない。各地でがんがん走行実証を行うような実行部隊が参戦すれば、開発は一気に加速していくのではないだろうか。実用化フェーズに突入した今、より多くの参画に期待したいところだ。
■日本国内の自動運転タクシーの動向
ホンダは後退、日産やWaymoが実用化目指し実証
国内における自動運転タクシー事業(類似サービス含む)は、ティアフォーのほかこれまでにホンダ、日産、Waymoに動きがあった。
いち早く計画を発表したのはホンダだったが、パートナーシップを結ぶ米GM、Cruise陣営が撤退したことを受け、計画は後退を余儀なくされたようだ。新たな自動運転サービス事業の構築に期待したい。
日産は、横浜市内を拠点に早くから自動運転サービス「EasyRide」の実証に取り組んでおり、一定エリア内に複数の乗降地点を設け、地点間を自由に移動可能なサービスの構築を進めている。ティアフォーと同様のサービスで、疑似自動運転タクシーと言える。2027年度をめどに、地方を含む3~4市町村で数十台規模のサービス提供開始を目指す計画だ。
Waymoは日本交通、GOとパートナーシップを交わし、東京都内で2025年中に実証を開始する。実用化時期は公表されていないが、まずは米国と異なる交通環境で自動運転システムがどこまで通用するのか見定め、改善を重ねていくものと思われる。
日本交通はティアフォーとも連携しており、タクシー配車同様、自動運転タクシーの配車サービスにおいても大きな存在感を発揮する可能性が高そうだ。
【参考】自動運転タクシーの動向については「自動運転タクシーとは?アメリカ・日本・中国の開発状況は?」も参照。
■【まとめ】絶対優位の先行勢にオープンソース戦略がどこまで通用するか
開発規模がモノを言う自動運転分野。莫大な資金と技術力を背景に台頭したWaymoらに対し、日本の一スタートアップに過ぎないティアフォーが単独で対抗するのは至難の業と言える。
先行勢の絶対的優位性を崩すのは容易ではないが、オープンソース戦略は対抗するための一手段として有用だ。横の連携を密にし、技術革新と開発規模をどこまで広げることができるか。今後の動向に引き続き注目したい。
【参考】関連記事としては「自動運転はいつから実用化される?レベル別・モビリティ別に解説」も参照。









