
音声認識ソリューリョンの開発で知られる米Cerence(セレンス)は、自社開発した緊急車両検知システム「Cerence EVD」がBMWグループに採用されたと発表した。
パトカーなどの緊急車両を検知するシステムで、BMWは自動運転レベル3システム「BMW Personal Pilot L3」に活用するという。
緊急車両の走行・進路を妨げることがないよう柔軟に対応するには、ある意味イレギュラーなアクションが求められる。自動運転における1つの課題だ。
Cerenceの技術を紹介しながら、自動運転における音声技術の有用さに触れていこう。
記事の目次
■Cerence EVDの概要
BMWがレベル3システムに採用
Cerence EVDは「Cerence Emergency Vehicle Detection」の略で、パトカーや救急車、消防車といった緊急車両が発する緊急信号固有の音響構造を認識し、それぞれのサイレンを確実に検知する。
BMWは、この機能をレベル3システム「BMW Personal Pilot L3」に活用する。緊急車両の接近を検知し、緊急車両に道を譲るためドライバーへ適切な対応のアドバイスを行うという。
BMW Personal Pilot L3起動時、近隣の緊急車両を検知すると、緊急車両が近づいている場合は自動運転の切り替えを遅らせる。また、走行中にサイレンを検知した際は車内のラジオなどの音量を下げ、自動運転モードからドライバーによる手動運転へのテイクオーバーを要請し、緊急車両が安全に通行できるようにする。
セレンスCTO(最高技術責任者)のIqbal Arshad氏は「自動運転システムの進化は、ドライバーが車内や道路で直面するさまざまな状況に関する情報をシームレスに収集し、適切な行動が取れるAI(人工知能)搭載コンパニオンの新時代を加速させる。Cerence EVDを活用したBMW Personal Pilot L3は、ドライビングエクスペリエンスを向上させるインテリジェントな自動化機能を提供する上で重要な進歩で、道路上のすべての人の安全性の向上に役立つ」としている。
【参考】BMWのレベル3については「自動運転レベル3機能、「世界3番目」はBMW濃厚 来年3月から提供」も参照。
メルセデスも緊急車両検知システムを導入済み
レベル3関連では、メルセデス・ベンツのレベル3システム「DRIVE PILOT」には、緊急車両検知用のマイクロフォンが搭載されている。検知後の動作・機能など詳細は不明だが、緊急車両の存在を意識した仕様となっている。
【参考】メルセデスのレベル3については「自動運転レベル3、米国初展開は独メルセデス!テスラのメンツ丸つぶれ」も参照。
ホンダのレベル3システム「トラフィックジャムパイロット」では、緊急車両に対応したシステムは特に見当たらない。
現行のレベル3は高速道路「渋滞時」を想定した仕様となっているため、比較的システムからドライバーへのテイクオーバーは容易だ。緊急車両にシステムが自動対応できるにこしたことはないが、テイクオーバーリクエストで対応するのもアリだろう。
その際、車両は緊急車両の姿が見えずともサイレン音をいち早く検知し、後ろから迫ってくるのか前からなのか、交差方向なのか遠ざかっているのかなどを可能な限り把握して、それぞれの挙動に応じた対応をテイクオーバーリクエストともにドライバーに提示できると良さそうだ。
まれに交差点で緊急車両と一般車両などの衝突事故が発生していることを考慮すると、こうしたシステムはレベル2+以下のADASでも有用かもしれない。交差点で接近を知らせてくれるだけでもその効果は大きいものと思われる。
Cerence EVDはこうした一般車両にも対応している。既存のマイクを使用してさまざまなサイレン信号と発信方向を正確かつ確実に認識し、サイレンを検知するとラジオなどの音量を自動で下げ、ヘッドユニットを介した視覚的な警告や車内アシスタントのオーディオによる警告をドライバーに行う。
【参考】ホンダのレベル3については「ホンダの自動運転レベル3搭載車「新型LEGEND」を徹底解剖!」も参照。
ホンダの自動運転レベル3搭載車「新型LEGEND」を徹底解剖! https://t.co/OdDXLocllA @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) March 17, 2021
レベル4以降では緊急車両対応が必須に
レベル4以降では、ドライバーが車内に常駐しているとは限らず、有事の際は基本的に自動運転システムが対応しなければならない。継続走行が難しい場合なども、自ら安全な方法で路肩などに停車することが求められる。
緊急車両が近づいてきた際も同様で、路肩に停車してやり過ごすなどの対応が必須となる。しかし、これが意外と難しいようだ。
例えば、後方から緊急車両が迫ってきた場合、路肩に停車するのが一般的だが、タイミングによっては駐車車両がすでにいたり交差点が近かったりすることもある。こうした場合、自動運転車はスムーズに対応しきれないことが考えられる。
また、狭い道を走行中に対向側から緊急車両が走行してきた場合、中途半端に車道上で停車し、結果として緊急車両の走行を妨害してしまうケースや、交差点で緊急車両とかち合った際に不動化するケースなどもありそうだ。
実際、米国ではWaymoやCruiseの自動運転車が消防車などの進行を妨げるトラブル事例が複数明らかになっている。2023年8月には、Cruiseの自動運転タクシーが交差点で消防車と衝突する事故も発生している。
こうした際に遠隔管理センターから手動介入することも考えられるが、これは本来苦肉の策で、システムが安全に緊急車両の進路を確保できるよう柔軟かつ高度な自動運転技術が試されるシーンと言える。
いずれにしろ、その大前提としていち早くサイレンを察知し、緊急車両の挙動を把握する音声認識技術は自動運転車に必須となる。近い将来、Cerenceのような技術が標準装備化される日が訪れることになるのかもしれない。
【参考】Cruiseのトラブル事例については「GMの自動運転タクシー、消防車と衝突!その代償は「車両数半減」」も参照。
GMの自動運転タクシー、消防車と衝突!その代償は「車両数半減」 https://t.co/f3sKEu4dmf @jidountenlab #自動運転 #GM
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) August 22, 2023
■Cerenceの概要
主力はAI音声アシスタントソリューション
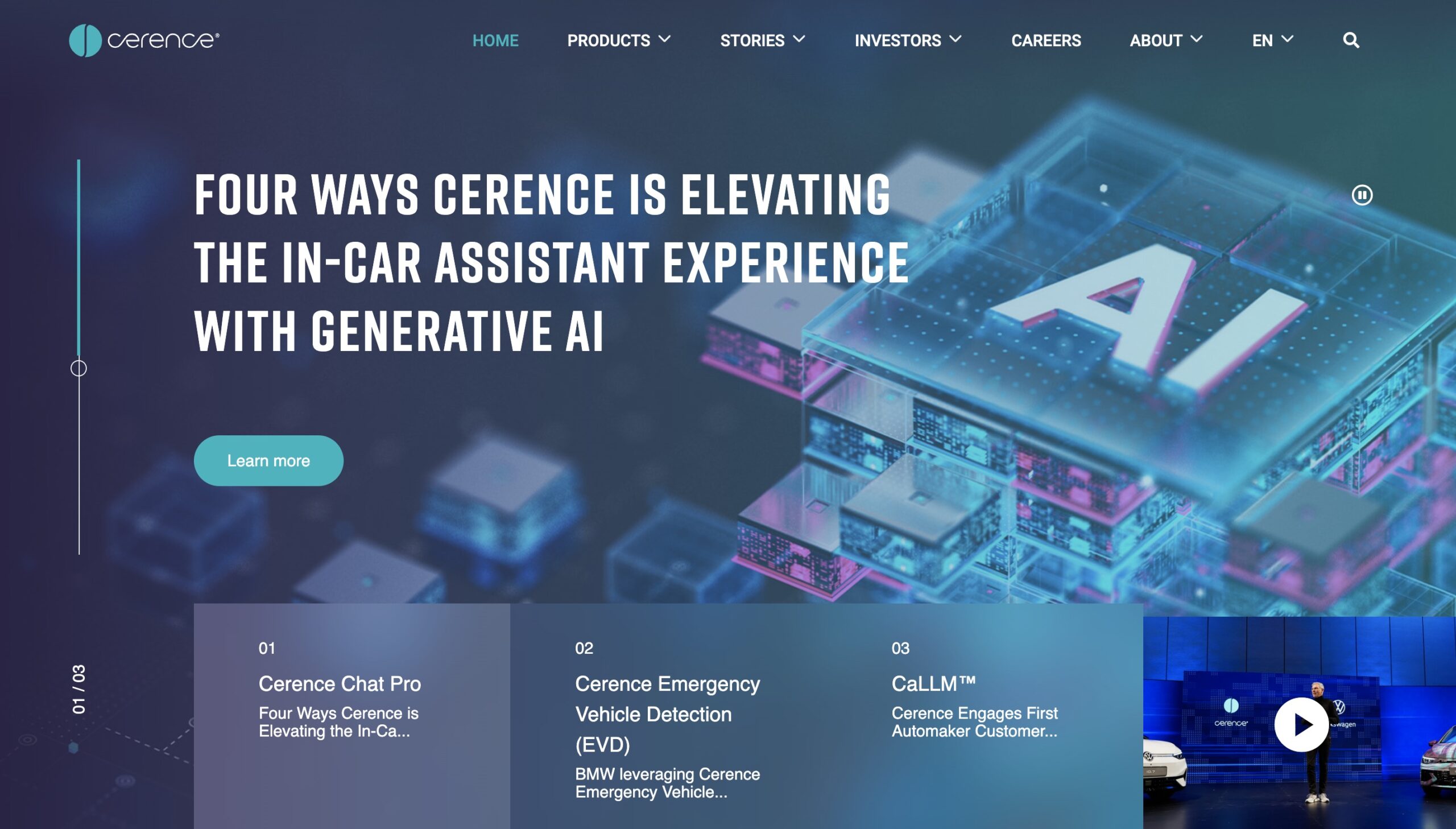
Cerenceは、AIアシスタントソリューションを中心に音声×AI技術を駆使してモビリティ業界で活躍するテクノロジー企業だ。
主力のCerence Assistantは、ドライバーをサポートするターンキー車載向け音声アシスタント・プラットフォームとして、直感的なAIコンパニオンが自動車メーカーとエンドユーザーの利便性を高める。
個人の好みやパーソナライズされたエンターテインメントを理解し、状況に応じたコマンドをマルチに実行する。理解すべき音声コマンドを優先して聞き分け、ユーザーの好みにあった駐車場検索や楽曲の再生、最安値のガソリンスタンドの案内など、さまざまなタスクを可能とし、移動の安全性や楽しさを最大化する。
車両のヘッドユニットで動作し、車両内外の複雑な状況を理解するため先進のAIが車両のセンサーやデータと統合されて車両の中枢として機能し、エッジテクノロジーとクラウドサービスを柔軟かつ安全に統合することで、運転をより直感的で楽しめるものにするという。
従来、音声アシスタントとの会話は発話ボタンを押して開始するのが一般的だったが、自動車メーカーやモビリティOEMと協力し、「ヘイ!〇×」などのウェイクアップワードの機能を提供している。
さらに、「Cerence Just Talk」を使用することで、ドライバーがアシスタントに向かって話しているかどうかをAIが判断し、ウェイクワードなしの会話も可能にした。乗客と話していると判断すればアシスタントは反応せず、アシスタントに話しかけていると判断すれば応答するシステムだ。
会話型AIを搭載したCerence Driveは、十分な直感性を備え、音声認識を超えたより深い理解精度を持つアシスタントを実現している。
自然言語理解と比類のないレベルの音声認識の精度により、ドライバーは自然な会話で指示を出すことができるため、特定のコマンドの学習や決められた方法で住所を入力する必要はない。例えば、「寒い」と言えば暖房を効かせ、「エンパイアステートビルに行きたい」と言えばルート案内を開始する。
ニューラルネットワークベースのテキスト読み上げ(TTS)技術も、驚くほど人間らしいバーチャルパーソナリティを実現しているという。
トヨタやホンダなども顧客に
Cerenceのソリューションはすでに4億7,500万台以上の自動車に導入されているという。トヨタやホンダ、スバル、スズキ、フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツ、ステランティス、ランドローバー、ヒョンデ、GM、フォード、SAIC、Geelyなどが顧客となっているようだ。
【参考】Cerenceの取り組みについては「CASE時代、「車内ブラウザ」が激熱!米Cerence、トヨタに提供」も参照。
CASE時代、「車内ブラウザ」が激熱!米Cerence、トヨタに提供 https://t.co/Ur1vQHVZin @jidountenlab #CASE #Cerence #トヨタ
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) December 28, 2021
ChatGPTをはじめとしたLLMの活用を加速
Cerenceは2023年12月、NVIDIAのテクノロジーを活用した自動車専用大規模言語モデル「CaLLM(Cerence Automotive Large Language Model)」を発表した。
NVIDIA DRIVEプラットフォーム上で実行されるCerenceの次世代車載コンピューティング プラットフォームの基盤として機能する。
自動車に特化した独自のインテリジェンスを備え、Cerenceの広範な自動車の専門知識と数十億のトークンを含む微調整された成長中の自動車データセットを活用し、一般的な知識のLLMを超える統合された車内ユーザーエクスペリエンスを提供する。
自動車の機能や特徴、要件を明確にサポートし、トレーニング、微調整、特注アプリケーションを通じて各メーカー向けにカスタマイズできる。機能としては、ユーザーのパーソナライゼーションやCerence Car KnowledgeなどのジェネレーティブAI搭載アプリケーション用の組み込み情報検索などがある。
2024年1月には、マイクロソフトとの提携も発表している。Microsoft Azure OpenAI Serviceを通じてOpenAIのChatGPTテクノロジーを統合し、次世代の生成型AI搭載車内体験推進に向け協業していく。
自動車メーカーらは、Cerenceの技術・知見とマイクロソフトのクラウド機能により、音声やタッチユーザーインターフェースへのシームレスな統合を通じて総合的なユーザーエクスペリエンスを実現可能になるという。
セレンスは、アシスタントプラットフォーム「Cerence Assistant」を使用し、これらの新機能を新車に導入していく計画で、自動車メーカーは購入後に付加価値を提供し、無数の知識領域とリアルタイムデータでユーザーエクスペリエンスを向上させることができるようになるとしている。
こうしたChatGPTテクノロジーを活用したCerenceのソリューションの先陣は、フォルクスワーゲンが切るようだ。Cerenceとフォルクスワーゲンは2024年1月、ユニークかつインテリジェントな車載グレードのChatGPT統合に向けを提携すると発表した。
新しい生成AI搭載「Cerence Chat Pro」を活用し、ドライバーと乗客が車載アシスタントと楽しく会話できる雑談を可能にする。ChatGPTを含む多数のソースを活用し、考えられるほぼ全ての質問に対して正確で適切な回答を提供するという。
【参考】自動運転×ChatGPTについては「自動運転車、「チャットGPT」の音声版が大活躍する未来」も参照。
自動運転車、「チャットGPT」の音声版が大活躍する未来 https://t.co/B2QChiFy6z @jidountenlab #チャットGPT #自動運転
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) December 28, 2022
■【まとめ】自家用車も自動運転車も音声技術によって進化
運転操作が不要な自動運転車においては、ナビや音楽、エアコンなど各種操作もボタンを押すことなく実行できることが望ましい。自動運転タクシーなどにおいても、移動中に「おすすめのラーメン屋ある?」といった日常会話を楽しめるかもしれない。
また、歩行者など外部とのコミュニケーション手段としても音声は非常に有用で、自動運転車の挙動を周囲に明確に伝えることもできる。
自家用車、自動運転車が音声技術によってどのように進化していくか、引き続き注目したい。
【参考】関連記事としては「Cerence、車内音声アシスタントでCESアワード!「Cerence Co-Pilot」お披露目」も参照。












