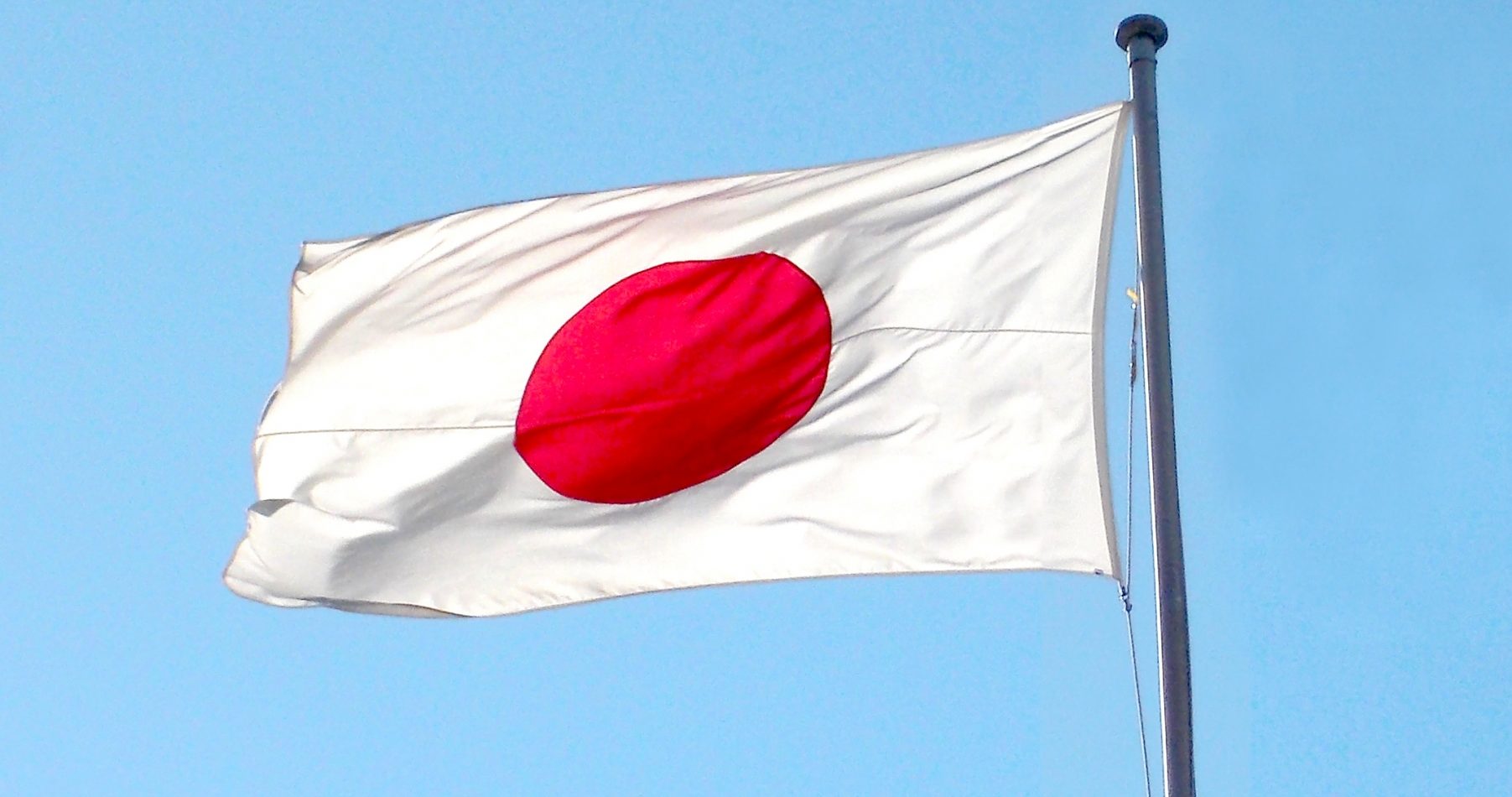
自家用車活用事業、通称「日本版ライドシェア」がスタートして2カ月が経過した。この日本版ライドシェアでは、サービスの運行が許されているのはタクシー会社のみで、極めて限定的なライドシェア制度と言わざるを得ない状況だ。
では、タクシー会社以外も運行主体になれるようにする「全面解禁」は、いつ実現するのか。反対勢力による反発は根強く、現在の情勢を踏まえると結論に達するのはまだまだ先となりそうだ。政府は6月にも全面解禁に向けて方向性を取りまとめる予定だったが、反対派の存在により棚上げとなった。
全面解禁による本格版ライドシェアの解禁を阻止する勢力は、どういった主張のもと反対しているのか。反対派や慎重派の意見をまとめてみた。
【参考】ライドシェアについては「ライドシェアとは?(2024年最新版)日本の解禁状況や参入企業一覧」も参照。
記事の目次
■本格版ライドシェア反対派
共産党
国会において、明確にライドシェア反対の立場を貫いているのが共産党だ。「利用者のいのち・安全を脅かすライドシェア導入など規制緩和に反対」する姿勢を貫いている。
一般ドライバーが自家用車で乗客を有料送迎することは道路運送法で原則禁止されており、営業許可のあるタクシーが緑地のナンバープレートであるのに対し、無許可車は白地ナンバープレートのままであり、ライドシェアは「白タク行為」そのものとし、乗客の安全を保障するしくみはぜい弱と断じている。
また、ライドシェアは副業を想定した仕組みで、価格破壊が容易に起こることも指摘している。早急な改善が必要なタクシー労働者の低賃金と劣悪な労働条件はさらに悪化する懸念があるため、断固阻止する構えだ。
共産党は自家用車活用事業をはじめ、自家用有償旅客運送についても「ライドシェアの突破口」になるため否定的だ。
さらには、ダイナミック・プライシング(変動運賃制度)についても「公共交通機関の運賃とは相いれないもの」とし、反対の姿勢を示している。
自民党のタクシー・ハイヤー議員連盟

タクシー業界と密接な関係を持つ自民党内のタクシー・ハイヤー議員連盟も本格版ライドシェアに反対の姿勢を強めている。
2023年10月の総会では、文部科学大臣の盛山正仁氏が安易なライドシェア導入は認めるわけにはいかない旨表明している。
基本的に所属議員の全て、またはほぼ全てが反対に回るものと思われる。所属議員数は定かではないが50人以上いるものと思われる。
自民党の推進派は、法改正を伴う本格版ライドシェア導入に向けてはまず身内の反対勢力を崩していかなければならないようだ。
全国ハイヤー・タクシー連合会
全国のタクシー事業者で組織する全国ハイヤー・タクシー連合会は、当然ながら本格版ライドシェアに反対している。
2023年9月に開催した第60回全国ハイヤー・タクシー事業者大会では、「国民の安全を脅かすとともに地方創生の担い手である地域公共交通の存続を危うくする『ライドシェア』と称する白タク行為を断固阻止する決議」を行った。
「ライドシェアと称する白タク行為は、事業主体が運行及び車両整備管理などについて責任を負わない点が最大の問題」「改正タクシー特措法の意義を著しく損なうもの」「運転者を独立した個人事業主と位置づけ、労働関係法令の規制を脱法的に逃れようとするもの」などとし、ライドシェア解禁を全力で阻止することとしている。
ちなみに全国ハイヤー・タクシー連合会の会長は川鍋一朗氏だ。川鍋氏は、大手タクシー事業者である日本交通の創業家一族で元会長であり、現在はタクシーアプリ最大手GOの会長という立場にある。
全国自動車交通労働組合連合会/全国自動車交通労働組合総連合会など
全国自動車交通労働組合連合会(全自交労連)、全国自動車交通労働組合総連合会(自交総連)、全日本交通運輸産業労働組合協議会(交運労協)、全国交通運輸労働組合総連合(交通労連)といったタクシーが関連する労働組合などもライドシェアに反対している。
全自交労連は2023年11月、「政府は、職業運転者の生活を奪い地域公共交通の崩壊を招くライドシェアの検討を中止せよ」、続く12月には「ライドシェアありきの空論を捨て、真に移動困難解決の議論を」と題した声明を立て続けに発表した。
現場で支え続けてきた労働者の声がライドシェア議論に反映されていないことから声明発表に至った。乗務員の多くは歩合制賃金で働いているため、営業収入の多寡により賃金が大幅に増減する点や、ライドシェアドライバーが世界的にワーキングプア化している事実、日本のハイヤー・タクシー産業が世界と比べユニークな営業形態をとっている点などを踏まえた議論を求め、ライドシェア導入に強く反対する意向を表明している。
自交総連は2023年10月、ライドシェア解禁反対を求め衆院第1議員会館で記者会見を行った。プラットフォーマーは利用者とドライバーをマッチングするだけで公共交通としての責任を負っていないと指摘し、利用者の安全確保について疑問を呈したという。
また、全自交労連、交通労連ハイタク部会、私鉄総連ハイタク協議会で構成するハイタクフォーラムは2024年2月、「危険なライドシェアを許さず安全な公共交通を守るための請願」を国会に提出した。ライドシェアを特区限定や条件付での解禁も含め一切認めないことなどを求める内容だ。
3月に開催した総決起集会でも、「ライドシェア新法絶対阻止」とする集会アピールを満場一致で確認したという。
日本労働弁護団
日本労働弁護団もライドシェアに反対する姿勢を強めている。2024年2月に「ライドシェア解禁に反対する緊急声明」、4月に「ライドシェアの実施及び法制化に反対する声明」をそれぞれ発表している。
ライドシェア解禁の動きは既存のタクシー運転者の労働条件を悪化させるだけでなく、公共交通であるタクシーの安全性を脅かすものとし、自家用車活用事業に対してもタクシーの供給過剰を招いてタクシー労働者の労働条件を悪化させるものであり、今後あらゆるライドシェアの実施に道を開くものとなりかねないとしている。
■本格版ライドシェア慎重派・消極派
公明党・国土交通大臣

公明党は本格版ライドシェア解禁に対し慎重な姿勢を崩さない。河野太郎規制改革相を筆頭に全面解禁に向けた動きが強まる中、前国土交通大臣の赤羽一嘉氏が2024年5月30日に首相官邸を訪れ、岸田文雄首相に「議論を拙速に進めることは容認できない」とする提言を提出し、前向きな議論に待ったをかけた。一部メディアからは「全面解禁の最大抵抗勢力」と言われる始末だ。
赤羽氏は、拙速に議論を進めるべきではなく、施策の実施効果を丁寧に検証するよう首相に求めた。同氏は公明党の「事故撲滅・持続可能な地域交通を実現するプロジェクトチーム」座長を務めており、党を代表する形で提言した格好だ。
この提言の後、岸田首相は規制改革担当相の河野太郎氏、現国土交通大臣の斉藤鉄夫氏と会談した。結論としては、自家用車活用事業導入後の状況を確認・検証するとともに、タクシー事業者以外の参入について並行して法制度を含めた議論を進めることとした。また、これら検証作業や法制度の議論に特定の期限は設けないことに合意した。
本格解禁に向けた道筋は残したものの、反対派・慎重派に配慮する形で結論を先延ばしすることとなった印象だ。
また、先だって河野氏と意見を交わした斉藤氏は、意見交換終了後の取材で全面解禁に否定的な立場を示している。
自家用車活用事業の拡充など改善に向けては河野氏と一致したものの、プラットフォーマーらによる本格版ライドシェアに対しては、タクシー改革の足かせになるなどの懸念を示し、法改正には消極的だ。「導入しないで済むことがベスト」としており、現時点においては否定派の立場をとっている。
近年、国土交通大臣のポストは公明党の指定席となっている。同省は、道路運送法に代表されるようにタクシーやライドシェアなど旅客運送に関わる規制を握っており、本格版ライドシェア実現に向けてはその協力が欠かせない組織だ。
支持率低迷が続き強く出られない自民党。公明党を口説き落とさない限り本格版ライドシェアの実現はないと言っても過言ではない。
公明党としては、明確に本格版ライドシェアに反対する主張は行っておらず、安全確保・利用者保護を第一に慎重姿勢を崩さない状況だ。こうした勢力に対する落としどころを見出せるかも今後の大きな焦点となりそうだ。
【参考】本格版ライドシェア解禁に向けた最新動向については「Uber日本撤退の引き金に?ライドシェア完全解禁、「棚上げ」決定」も参照。
Uber日本撤退の引き金に?ライドシェア完全解禁、「棚上げ」決定 | 自動運転ラボ https://t.co/pwQhZ7j9NB @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 31, 2024
立憲民主党
立憲民主党は、反対派寄りの慎重派と言える立ち位置だ。支持母体やザ・野党的立場から反対派としての色が濃い印象だが、党としては明確に「ライドシェア反対」をうたっていないようだ。
同党が2023年12月に公表した「立憲民主党のモビリティ政策~ 都市部、地方・過疎地域における有償運送(有償ライドシェア)に関する考え方 ~」によると、プラットフォーム事業者によるライドシェアについては「歴代政権が示してきた『安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があると考えている』『特区でも認めない』との見解のとおり」とし、持続可能な地域公共交通の実現と矛盾する政策、また政府がめざす持続的・構造的な高水準の賃上げを中心とした労働市場改革とも相反するものと位置付けている。
事実上の反対派と言える内容だが、完全否定の明言を避けているようにも感じられる。党としては、見解を統一しきれていないのかもしれない。
ライドシェアの超党派勉強会には立憲民主からも議員が参加しており、肯定派も存在するものと思われる。民主党政権時に国土交通大臣を担った馬淵澄夫氏は、運行や整備管理、事故対応などへの不安を指摘しつつも、公共交通確保の観点から交通手段の選択肢を増やし、抜本的対策を打ち立てるべく議論を進めるべきというスタンスをとっている。
今後、党としてどのような統一見解を示すか注目だ。
【参考】ライドシェアに対する政治家の見解については「ライドシェア推進派の政治家一覧(2024年最新版)」も参照。
ライドシェア推進派の政治家一覧 https://t.co/EjSFBiPSZw @jidountenlab
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) February 1, 2024
■【まとめ】日本独自の仕組みが必要?
タクシー関連の組織や労組が反対するのはある意味必然であり、これらの組織は最後の最後まで抵抗し続けることはほぼ間違いない。
国会関連では、政権与党内にも相当数の反対派・慎重派が存在することが気がかりだ。おそらく、海外のライドシェア事例をコピペしたような事業案では理解を得ることができず、より高い安全性を確保可能な日本独自のライドシェアの仕組みが必要になるものと思われる。
場合によっては、政治資金規正法改正案のような骨抜き案・妥協案で決着することもあるだろう。また、自家用車活用事業の実績やタクシー業界の努力次第では、「やっぱり本格版はいらなくね?」……となることも考えられる。
まず、規制改革推進会議が6月にどのような(中間)取りまとめを発表するのか。取りまとめ事態を先延ばしするのであれば、どういった方針で議論を継続していくのか。政府の動向に要注目だ。
【参考】関連記事としては「ライドシェアで自民党分裂!タクシー会社限定に幹事長「おかしい」」も参照。












