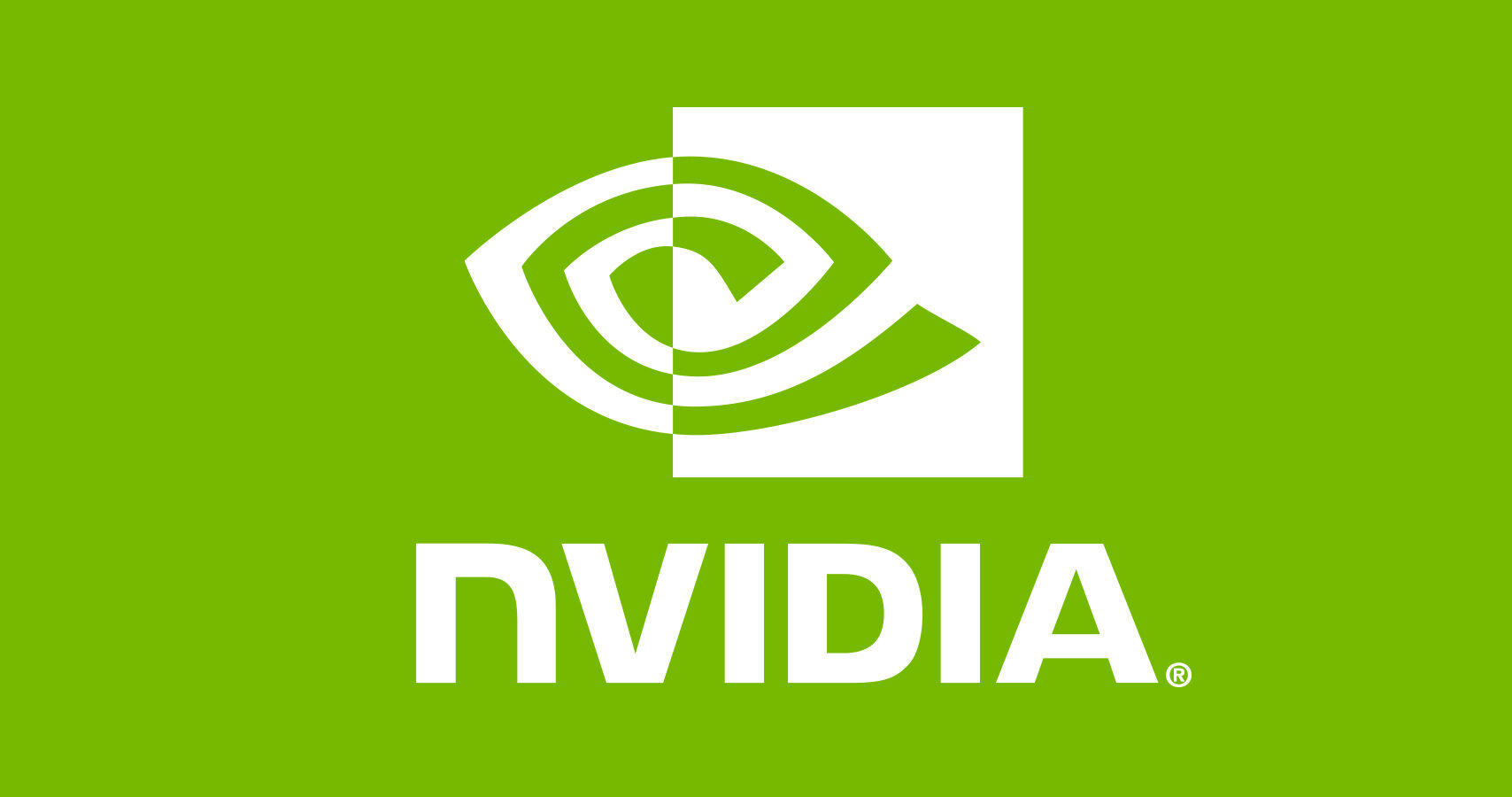
米国・中国企業を筆頭に開発競争が続く自動運転分野。グーグル系Waymoに代表されるテクノロジー企業やスタートアップ、自動車メーカーらが業界の主導権を手にするべく日夜しのぎを削っている。
果たしてどの企業が勝者となるのか競争の行方が気になるところだが、いずれの企業が勝者になっても業績を伸ばすだろう企業が存在する。米半導体大手のNVIDIAだ。
開発企業におけるNVIDIAソリューションの採用率は非常に高く、勝ち組が誰であれ業界が伸びれば伸びるほどNVIDIAの業績も上向く構図が出来上がりつつある。
自動運転業界におけるNVIDIAの立ち位置について解説していこう。
記事の目次
■NVIDIAの自動運転戦略
コンピューター化が進行する自動車業界で高性能SoC需要が高まる

NVIDIAは2015年、CESで自動運転開発向けの「NVIDIA DRIVE PX」と最先端のデジタル・コクピット向けの「NVIDIA DRIVE CX」を発表し、自動運転分野へ正式に参入した。
同社CEOのジェンスン・フアン(Jen-Hsun Huang)氏は当時、「未来の自動車で中核となるのは、モバイル型のスーパーコンピューティング。たくさんのカメラとディスプレイを使い、未来の車は自身で周囲の状況を観察し、理解できるようになっていく。未来の車は、知能があるとしか思えないようなさまざまなことをしてくれるはず。コンピュータービジョンや深層学習、グラフィックスが進歩したおかげで、このような夢が実現可能となった」とし、「NVIDIA DRIVEが登場した結果、今後はスーパーコンピューターに匹敵するビジュアル・コンピューティング機能を運転者一人ひとりが利用できるようになり、車のスマート化が急速に進む」と期待を込めた。
このフアン氏のビジョンは、今まさに自動車業界で起こっている変革と一致する。高度なADAS(先進運転支援システム)や自動運転技術、コネクテッド技術などの搭載が本格化し、ソフトウェア重視の「ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)」が開発の主流になり始めている。
【参考】関連記事としては「SDV(ソフトウェア定義型自動車)の意味は?自動運転化の「最低条件」」も参照。
自動車のコンピューター化の進行に伴い、それを効果的に稼働させるSoC高度化に向けた需要も年々高まっている。
特に、自動運転車はカメラやLiDARなどの車載センサーが取得した膨大なデータをリアルタイムで処理し、オブジェクトの検出や車両の制御判断を瞬時に下さなければならない。処理能力絶対主義と言えるほど高性能なコンピューターが求められるのだ。
GPU(グラフィックスプロセッシングユニット)開発により画像処理に優位性を持つNVIDIAにとって、自動運転分野は新たなドル箱と言える。
なお、NVIDIA Tegra X1プロセッサを2基搭載した当時のDRIVE PXの処理能力は、2.3TFLOPSだった。翌2016年発表のDRIVE PX 2は8TFLOPSで、これはMacBook Pro150台分に相当するという。
2017年ごろから開発パートナーが続々
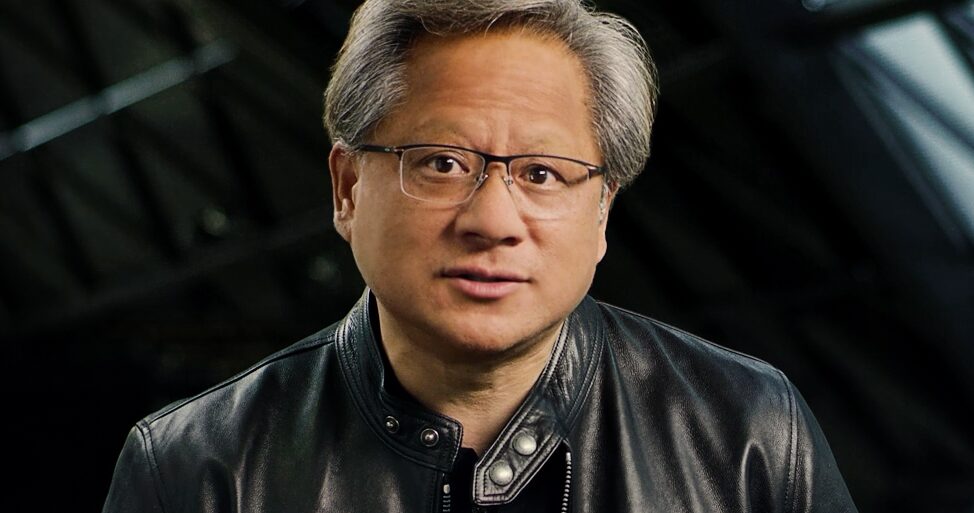
2017年には、自動運転開発に向けた各社とNVIDIAとの協業・パートナーシップが本格化する。アウディがNVIDIAとの提携に本腰を入れ、2020年の公道走行実現に向け最先端のAI(人工知能)搭載車の共同開発を進めることを発表したほか、ボッシュも量産車向けAI自動運転システムの開発に向け協業を発表した。
ボルボ・カーズとオートリブも自動運転開発に向けNVIDIA DRIVE PXプラットフォームを採用した。ZFとHELLAも自動運転車の量産展開に向け戦略的パートナーシップを締結した。百度に至っては、クラウドデータセンターや自動運転車、スマートホームにおけるAI技術向上に向けパートナーシップを結んでいる。
ドイツポストDHLグループが開発を進める自動配送トラックにNVIDIA DRIVE PXを採用したほか、HERE Technologiesは自動運転車向けに業界をリードするHDマップ作成ソリューションの共同開発を進めると発表している。同様に、ゼンリンもHDマップソリューションについて共同研究することに合意している。
2017年に公式リリースされたパートナーシップだけでこのボリュームだ。この勢いは以後も止まらず、2018年には当時自動運転の自社開発を進めていたUber Technologiesやフォルクスワーゲン、Aurora Innovation、ヤマハ発動機もそれぞれ提携を発表している。
ボルボ・カーズは、2020年代初頭に発売予定のレベル2+車にNVIDIA DRIVE AGX Xavierを採用することを発表している。量産車・オーナーカーへの採用は業績に大きく反映される。後継車両への継続搭載も見込まれるため、非自動運転車であってもビジネス上非常に重要なものとなる。
2019年には、Didi Chuxingが自動運転及びクラウドコンピューティングの領域でNVIDIAと提携を発表したほか、TRI-AD(現ウーブン・バイ・トヨタ)とAIコンピューティングインフラストラクチャやシミュレーション、自動運転車を開発するための車載コンピューターの各分野で協業すると発表した。
NVIDIAとトヨタ既存の関係を発展させ、TRI-AD、TRIの3社で開発を加速させるとしている。
2020年には、メルセデス・ベンツがSDV向けのコンピューティングアーキテクチャを構築するためNVIDIAと協業すると発表した。韓国の現代自動車グループは、今後発売するヒョンデ、起亜、ジェネシスの各モデルにNVIDIA DRIVEのインフォテインメントおよびAIプラットフォームを採用するとしている。
クボタは、農業機械のスマート化に向けNVIDIAのエンドツーエンドAIプラットフォームを採用・協業していくことを発表した。
パートナーエコシステムは数え切れず……
このように、自動運転車をはじめ量産車、農業機械、HDマップなど、自動運転や自動車に関わるさまざまな分野でNVIDIAはパートナーシップを構築し、自社ソリューションの採用を拡大しているのだ。
NVIDIAの公式サイトでは、NVIDIA DRIVEパートナーエコシステムにメルセデス・ベンツ、ボルボカーズ、ヒョンデ、ジャガーランドローバー、FAW(第一汽車集団)、GWM(長城汽車)、ロータス、BYD、ポールスター、NIO、IM Motors、Lucid Motors、Xpeng、Zeekr、Weltmeister、Faraday Future、AIONなどの自動車メーカー・ブランドが名を連ねている。
自動運転開発企業では、Pony.ai、AutoX、Cruise、Kodiak Robotics、Einride、Momenta、Phantom AI、DeepRoute.ai、Wayve、WeRide、Zoox、TuSimple、Plus、ティア1サプライヤーではボッシュ、コンチネンタル、ヴァレオ、LiDAR開発企業ではLuminar Technologies、Innoviz Technologies、AEye、Aeva Technologies、Cepton、Ouster、その他ソニーやテンセント、フォックスコンなど非常に多彩なメンバーが名を連ねている。
このほか、パートナーエコシステムとして紹介されていないものの、トヨタやホンダ、日産、フォード、GM、BMWなどもさまざまな分野でNVIDIAソリューションを活用している。おそらく、主要自動車メーカーは網羅しているのではないだろうか。
EV(電気自動車)系新興メーカーでは、上記以外にもLi AutoやJidu、VinFast、Xiaomiなども採用している。NVIDIAが2022年に発表した内容によると、世界の乗用EVメーカー上位30社のうち、実に20社がコンピューティングプラットフォームとして「NVIDIA DRIVE Orin」を採用しているとしている。
テスラはNVIDIA採用?不採用?
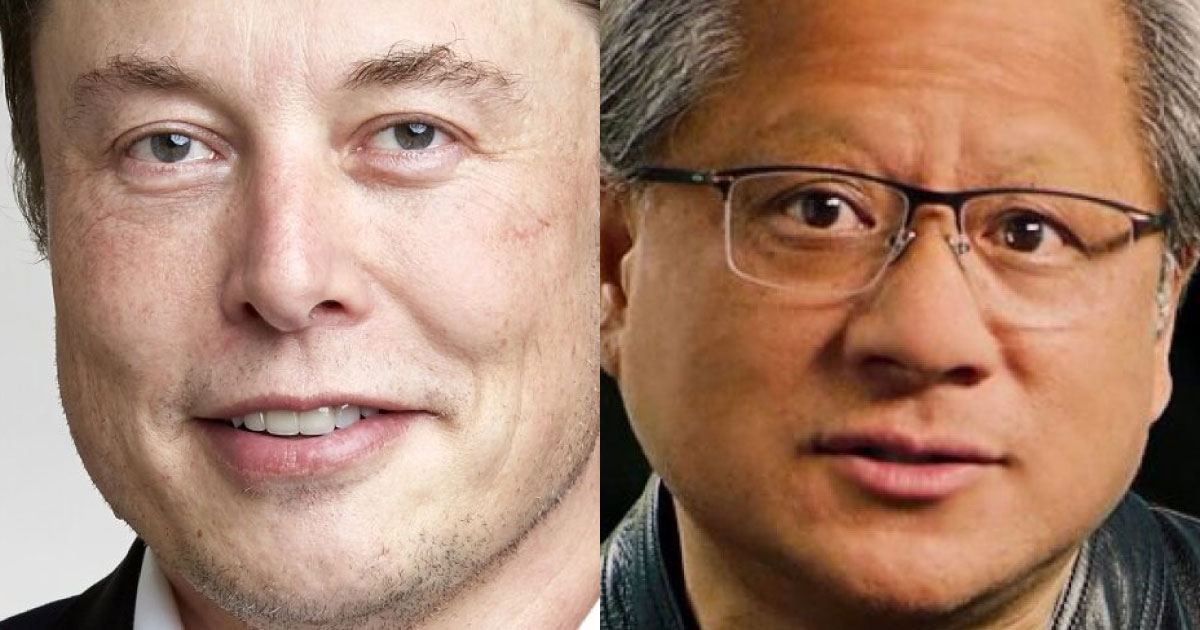
テスラについては、現在の使用状況は不明だ。過去、NVIDIAのSoCを使用していたのは間違いなく、NVIDIAの技術カンファレンスにイーロン・マスク氏が登壇したこともある。
しかし、マスク氏は2019年、完全自動運転向けのAIチップの自社開発を正式発表し、自社モデルへの搭載を進めていく方針を打ち出した。その際、NVIDIA製品よりも自社開発したチップの方が優れている旨説明している。
両社の関係は不明瞭な点が多いが、フアン氏は2024年5月、ヤフー・ファイナンスの取材に対し「自動運転の分野を最もリードしているのはテスラ」と語り、この報道を知ったマスク氏がX「Thanks Jensen! @nvidia」と礼を述べている。
一見ポジショントークのようにも感じられるが、おそらくフアン氏は、誰もが手にすることができるエンドツーエンドの自動運転システムとして「テスラ」の名を挙げたものと思われる。
Waymoなど他社とは比較対象として異なるものだが、少なからずフアン氏とマスク氏の関係はまだ続いていることがうかがい知れる。
【参考】EV業界におけるNVIDIAについては「NVIDIAの自動運転チップ、EV企業の推定シェアは60%強」も参照。
【参考】NVIDIAとテスラについては「エヌビディアCEO、自動運転「最先端はテスラ」と明言」も参照。
開発競争が過熱すればNVIDIAは儲かる
自動運転開発企業においては、メジャーどころのほぼ全てと言ってもよいほどNVIDIAが浸透している印象だ。マップやLiDAR開発などを手掛ける各社も網羅している。つまり、自動運転開発競争が過熱すればするほどNVIDIAの売り上げは伸び、そしてどの企業が勝ち残ろうとNVIDIAの影響力はかげることなく業界を席巻し続けるのだ。
高いシェアを維持・向上させるNVIDIAの採用は、強力なライバルが出てこない限りまだまだ続く。そして、開発の継続性を考慮すれば、一度NVIDIA製品に親しんだ企業に乗り換えてもらうのは容易ではない。
このように考えると、自動運転業界そのものが転ばぬ限り、NVIDIAの自動運転セグメントはぼぼ確実に業績を伸ばし続けることになりそうだ。
Waymoとモービルアイが唯一の脅威?

NVIDIAの業績を脅かす存在は、今のところグーグル系Waymoとインテル系モービルアイくらいではないだろうか。
自動運転業界をリードするWaymoがNVIDIAソリューションを使用しているかは不明で、過去の報道をうかがう限り、Waymoもチップの独自開発を進めている。過去にはサムスンに製造を委託したことも報じられている。業界のトップランナーのNVIDIA依存率がゼロなのかどうか、気になるところだ。
モービルアイは、NVIDIAのガチのライバル的存在だ。ADASソリューションで培ったネットワークと技術を武器に一定のシェアを誇る。
チップだけではなく自動運転システムの開発能力も非常に高く、システムごと採用する例も少なくない。中国のEVブランドや欧州勢など、モービルアイのレベル2+相当のシステムを実装する例も出ている。
NVIDIAに対抗できるポテンシャルと信頼性を持った現状唯一の存在と言っても過言ではなさそうだ。
【参考】自動運転向けの半導体開発企業については「完全解明!自動運転×半導体、世界の有力企業11社一覧」も参照。
■【まとめ】モビリティ業界における本格需要はこれから
2024年1月期決算で過去最高収益をはじき出した半導体大手の米NVIDIA。その勢いはとどまるところを知らず、2025年度第1四半期決算は前年同期をさらに上回った。向かうところ敵なしの状態が続いているようだ。
時価総額は2024年6月4日時点で2兆8,009億ドルに上る。テック企業としてはマイクロソフトの3兆867億ドル、アップルの2兆9,712億ドルに次ぐ数字で、アマゾンの1兆8,555億ドル、メタ・プラットフォームズの1兆384億ドル、アルファベット(グーグル)の1兆223億ドルを超えている。
2024年1月期通年の自動車・ロボットセグメントの売上高は約11億ドルで、全体の収益約609億ドルから見ればまだ2%に満たない数字だ。
自動運転がNVIDIAの業績を左右する規模にはまだ至っていないようだが、見方を変えれば伸びしろとも捉えられる。モビリティ業界の潜在需要はまだまだ眠っているはずだ。
今後、同社が自動運転業界でどのように存在感を高めていくのか、要注目だ。
【参考】関連記事としては「NVIDIA株、一段高へ期待感!車載半導体、自動運転向けで採用加速」も参照。













