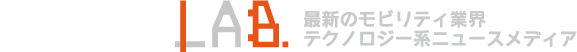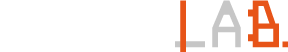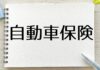中国IT大手のテンセントが「島」を購入したとのニュースが流れている。開発が進む深センの臨海地だ。
島とはいえ道路がつながっており、埋立地かもしれない。東京都の豊洲や大阪府の舞洲のイメージに近いものと思われる。いずれにしろ、同地区は湾を囲む形で一体的な開発プロジェクトが進められており、今後イノベーションの中心地として大きく発展していくことになるのだろう。
こうした埋立地や島は、次世代に向けた新たな実証試験地に適している。埋立地は一から開発が可能なまっさらな土地であり、島は従来の都市構造と隔離された地理条件を備えているためだ。これは、自動運転を実現するうえで立ちはだかる大きな壁を乗り越える実証地として非常に有用だ。
今回は、こうした島などの利点を生かした「自動運転特区」の有効性について解説していこう。
■自動運転車と一般車両との混在は避けて通れない
基本的に、自動運転は実用化が進んでも一般車両と混在して走行することになる。手動運転を好む層の存在や車両価格の差などが要因だ。手動運転を禁止する段階まで到達しない限り、原則として同じ道路上を走行するのだ。
自動運転を導入し始めたばかりの初期段階では、この混在が大きなハードルとなる。法律上無人の完全自動運転が認められたとしても、手動運転とは異なる独特の挙動や制限速度内の超安全走行を嫌がるドライバーは相当数存在するものと思われる。また、歩行者や自転車からも一線を引いた状態で見守られることになるだろう。
道路交通法で公道走行が認められたとしても、その存在自体が広く認められるまでは相当の時間がかかる。また、自動運転に対応したインフラの整備も行わなければならないため、技術水準が上がり実用化の段階に突入しても、全国一律で解禁するのは相当高いハードルとなるだろう。
実用化は、自動車専用道路や自動運転の誘致に積極的な自治体などの一部エリアから徐々に広がっていくものと思われるが、実用化区域を明確に区切ることは困難なため、自動運転車の走行を全く想定していないドライバーが近接する可能性も高い。これは意外と危険だ。
社会実装におけるさまざまなルールづくりや認知度・理解度が深まるまで、混在環境下は危険度が高まりがちになるのだ。
■特区制度活用で自動運転優先社会を
危険性ばかりを指摘すると実現に対し消極的になってしまいがちだが、その解決方法の一つが「特区」だ。自動運転特区として、可能な限り隣接地域と差別化し、交通インフラや案内看板なども整備するほか、まちとして「自動運転シティ」と大々的に標榜するくらいの意気込みで臨むことが理想だ。「自動運転に取り組むまち」を超え、「自動運転優先のまち」と言えるほど尖った施策でルール作りを進めることが望ましい。社会に定着したルールを変えていくには、やはり一定のインパクトが必要なためだ。
こうしたエリアでフィージビリティを高め、自動運転を全国に波及させていく――という方策が一般的に妥当な線といえるだろう。
■自動運転シティは「島」が有利?
こうした自動運転シティは、他の地域と隔離されていればいるほど実行しやすい。そこで「島」の出番だ。島内全域を自動運転シティとし、自動運転車を前提としたインフラ作りを進めていくのだ。
自動運転に必要となるIoT化や通信網の整備なども進めて「近未来のまち・スマートシティ」を目指し、自動運転以外の新技術も含めた実証の場として定着させることで、継続的に企業を誘致できる環境を構築していく。地域としての持続性が生まれ、住民へもさまざまな恩恵がもたらされる。
島特有の産業である漁業なども自動運航船の開発とリンクさせたり、本島との連絡・交通手段にドローンを活用したり、遠隔医療の実証を行うなど、応用範囲は広い。
旧来の生活を望む住民は淘汰されてしまう可能性が高いが、限界自治体・集落と化した島の再生策として考えれば、選択肢として考慮するに値するものになるはずだ。
自治体としてそこまでの決断ができないのであれば、民間が島を丸ごと一つ買いあげ、私有地とした上で自動運転シティ化するのも一つの手だ。自動運転業界において最先端のショーケースを作り上げる気構えが必要となるが、世界各国の開発企業を呼び寄せることも夢ではなくなる。
■世界に広がる自動運転シティ構想

島ではないが、自動運転シティ構想は世界的な注目を集めるプロジェクトで、中国が開発に力を入れている。中国は自動運転に対応したスマートシティを各都市の近郊で一からまるごと作り上げるという構想を発表しており、北京や上海といった既存の大都市を補完する機能も持たせる計画のようだ。
道路などのインフラは、自動運転車と協調して機能するV2I(vehicle to infrastructure)を前提としているほか、鉄道は地下に建設し、地上を走行する公共交通車両は全てEVシャトルバス、個人車両は自動運転車――といった将来像を描いているようだ。
また、カナダのトロントでは、米グーグル系のSidewalk Labs(サイドウォークラボ)社がスマートシティ開発構想を発表している。ウォーターフロント地区の約3.2キロ平方メートルの土地を再開発し、グーグルのカナダ本社を移転するとともに、自動運転やロボットをはじめとした最先端技術を活用したスマートシティの建設を目指すとしている。こうした民間主導の動きが今後広がる可能性は思いのほか高そうだ。
このほか、自動運転車の走行テスト専用のまち「自動運転タウン」を建設する動きも、アメリカ(M City)や韓国(K-City)などでみられる。試験走行用サーキットに街並みを模倣した各施設を作り、よりリアルな実証実験を行う仕組みだ。
こうした動きは日本国内にもある。安倍晋三内閣は2018年、暮らしやすさ、そしてビジネスのしやすさにおいて世界最先端を行くまちづくりを進め、第四次産業革命を先行的に体現する最先端都市となる「スーパーシティ」構想を実現するため、「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会を開催している。
中間とりまとめによると、移動においては自動走行やデータ活用による交通量管理・駐車管理など、物流においては自動配送やドローン配達などを構成要素としており、各領域にまたがる社会の未来像を先行実現するとしている。
【参考】中国の自動運転シティ構想については「日本は中国を見習うべきか…自動運転の環境整備、躊躇一切なし」も参照。自動運転タウンについては「“住めない街”続々…自動運転テスト向け、仮想の”人”も歩き出す?」も参照。
■【まとめ】スマートシティ構築が世界的潮流に
次代に向け、社会の在り方を根本から変えるような都市設計が求められる反面、既存のまちを再開発する手法はやはりハードルが高い。その土地・その社会に住み慣れた人がいるからだ。
日本で手っ取り早く実現するためには、立地的な条件を除外すれば無人島や限界を迎えつつある島が有力候補となる。立地も条件に入れるならば、大都市近郊に大規模な埋め立て地を造成するか山林を切り拓く必要がありそうだが、環境面から問題視する声も大きくなりそうだ。
社会の在り方を根本から変えるということは、当然並大抵のことではない。しかし、長い年月をかけた末に世界の各都市が最終的にスマートシティ化するのであれば、世界に先んじて挑戦する価値があるのも確かなことだ。
スーパーシティ構想の行方をはじめ、スマートシティ構築に向けた自治体や企業の取り組みに注目したい。
【参考】関連記事としては「自動運転車に実証実験・テスト走行が必須な理由 実用化に向けて回避すべき危険・リスクは?」も参照。