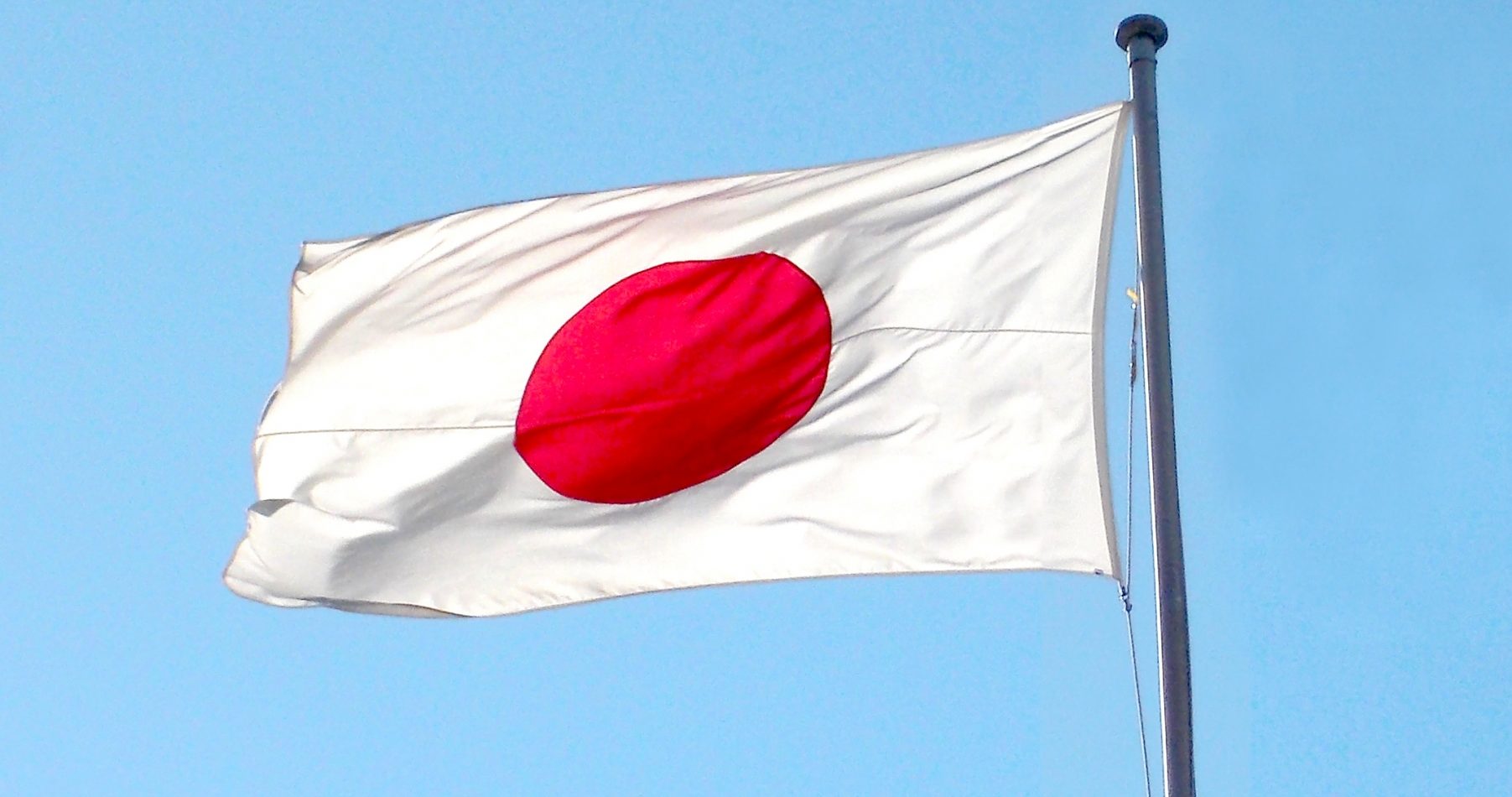
開発から社会実装段階への移行を始めた自動運転技術。その進化は、官民総出で取り組んできたこの10年間のプロセスに裏打ちされたものだ。
Waymoや百度など個別企業の技術には現状敵わないかもしれないが、国総体の取り組みとしては、世界をリードする先頭集団に位置付けられる水準といっても過言ではない。
自動運転分野における官民連携や協議はどのように進められているのか。国が設置した検討会や委員会、協議会の活動をまとめてみた。
記事の目次
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |
| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |
| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |
| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| パソナキャリア |  |
| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |
| タクシーアプリDiDi |  |
| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |
| MOTAカーリース |  |
| お好きな車が月々1万円台から! | |
| スクエアbang! |  |
| 「最も安い」自動車保険を提案! | |
■自動運転ワーキンググループ(2024年度~)
自動運転タクシー実用化へ集中審議

自動運転タクシーの社会実装のための制度のあり方について短期集中的に検討を行うため、国土交通省は2024年10月、交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会の下に「自動運転ワーキンググループ」を設置した。
ビジネスモデルに対応した規制緩和などに取り組むほか、認証基準具体化による安全性の確保や、運輸安全委員会における自動運転車に係る事故調査体制の確保を通じた再発防止、被害が生じた場合における補償の観点などを踏まえ、自動運転タクシー実装に向けた制度の構築を進める。
自動運転の専門性を有する事業者が、タクシー事業許可を有していなくても運行管理を受託できるようにする運用制度の明確化や、タクシー手配に係るプラットフォーマーに対する規律の在り方、特定自動運行時に必要な運行管理の在り方、認証基準具体化により自動運転車の製造者が満たすべき安全性能の明確化、事故原因究明を通じた再発防止策などについて議論し、結論を得たものから順次制度化を推進していく。
2025年中を目途に結論を導き出す構えだ。
▼自動運転ワーキンググループ
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s201_jidouunntenn01.html
【参考】自動運転ワーキンググループの取り組みについては「自動運転車の事故、「国レベルが調査に動く」基準を明確化へ」も参照。
■自動運転インフラ検討会(2024年~)
自動運転に資するインフラの在り方を検討
自動運転インフラ検討会は、自動運転に資する道路構造や路車協調システム、道路交通情報の収集・提供に関する体制やルール、情報通信インフラなど、インフラの在り方を検討することを目的に2024年度に設置された、国土交通省所管の検討会だ。
合流支援情報提供システムや交差点センサーなどの技術基準をはじめ、遠隔監視、合流支援情報、先読み情報といった情報通信インフラの在り方、自動運転車優先レーンの効果、切替拠点など自動運転に必要となる施設、自律走行に資する道路上の対応、高速道路における遠隔監視・緊急時対応などの在り方、サービスニーズ・車両技術などを踏まえたインフラの展開方針などについて議論を進めている。
実証や事業者ヒアリングなどを交えながら、2025年度中に中間とりまとめを行う方針だ。
▼自動運転インフラ検討会
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/jido-infra/index.html
■モビリティDX検討会(旧自動走行ビジネス検討会/2015~)
モビリティ領域におけるDX化を促進
モビリティDX検討会は、2014年度末に始まった「自動走行ビジネス検討会」を前身とする経済産業省・国土交通省所管の検討会だ。
自動走行ビジネス検討会は、自動運転分野において世界をリードし、かつ社会課題の解決に貢献することを目指し、産学官オールジャパン体制で自動運転のビジネス化を推進するため設置された会議体で、2022年度まで長らく国内自動運転分野の進展に貢献してきた。
デジタル化を通じたモビリティの将来像の実現に向け、クルマのデジタル化への対応(E/Eアーキテクチャの変革 / ビークルOSの開発 / AD・ADASの高度化)や、移動・物流サービスモデルの構築(事業性の構築 / 社会受容性の向上)、開発・実装に向けた環境整備(安全性評価手法の確立 / インフラ整備 / V2X通信の活用 / 法制度 / 人材確保)など、各ワーキンググループを通じて議論を進め、2016年から2022年度まで毎年「自動走行の実現及び普及に向けた取組報告と方針」を策定・更新してきた。
自動運転における協調領域の特定、国際的なルールづくりに戦略的に対応する体制の整備、産学連携の促進も手掛けるなど、幅広い領域で検討を進めてきた重要な組織だ。
この活動を引き継ぐ形で2023年度に「モビリティDX検討会」が組織化された。デジタル技術の進展に伴い、今後自動車・モビリティ領域ではDXがGXと並ぶ大きな競争軸となっていくことが想定されるため、ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)や自動運転、MaaSといった新たなモビリティサービス、企業を超えたデータ利活用など、DX全体を貫く戦略を策定する。
2024年度はSDV領域、モビリティサービス領域、データ利活用領域、安全性評価戦略の各サブワーキンググループが設けられ、それぞれ議論を進めている。
▼モビリティDX検討会
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/jido_soko/index.html
■モビリティワーキンググループ(2023年度~)
デジタル庁における自動運転議論の場
自動運転やドローン、サービスロボットなど、地域のモビリティを支える技術の同時かつ一体的な事業化指針となる「モビリティ・ロードマップ」の策定を推進するため、デジタル庁が2023年度に設置したのがモビリティワーキンググループだ。AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方を検討するサブワーキンググループも設置されている。
これまでの取り組みにおいてレベル4を実用化する技術や制度整備に一定の目途が付いたものの、その事業化を促し、地域公共交通の維持・活性化に貢献していくことを念頭に社会実装を考えると多くの課題が残されていることから、技術や制度の確立に留まらず、継続的に事業を行うことができるようビジネスモデルの確立に重点を置いた検討を進めている。
モビリティ・ロードマップ2024では、初年度となる2024年度を総括的事業実証ステージと位置づけ、自動運転事業化に向けた技術の習熟・高度化や自動運転事業化加速に向けた審査手続の透明性・公平性の確保などを進めることとした。
2025~2026年度は先行的事業化ステージと位置づけ、自動運転をはじめとした新たな技術の導入コストの低減・負担の合理化、データの収集・共有の加速、路車協調など協調領域における技術の高度化と実践、モビリティサービスを支える人材育成、業態を支える制度の施行・改善を進めていく方針だ。
そして2027年度以降を本格的事業化ステージに位置付け、業態を支える制度の活用普及と新たなモビリティサービス市場の確立やオーナーカーなど他形態への展開を推進していく。
現在取りまとめているモビリティ・ロードマップ2025では、需給一体となったモビリティサービスの効率化の観点から、地域の住民に移動の自由を確保する交通商社機能の確立に関する指針が盛り込まれる見込みだ。
また、自動運転技術の実装に向けた支援策の一環として、初期導入費用の低減を図る観点からリース・レンタル方式についても議論を深めていくものと思われる。
▼モビリティワーキンググループ
https://www.digital.go.jp/councils/mobility-working-group
【参考】モビリティワーキンググループの取り組みについては「デジタル庁、「交通商社」の設立を主導か 水面下で検討」も参照。
■都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会(2017年度~)
都市交通に対する自動運転の影響などを検討
将来的な自動運転の活用に向け、自動運転技術の都市への影響可能性の抽出・整理、自動運転技術の活用について検討を行うため、国土交通省所管のもと2017年度に「都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会」が設立された。今なお続く会議体だ。
都市交通、街路空間、駅前広場、身近なエリアなど、望ましい都市像の実現に向けた自動運転技術活用のための対策ポイントや具体的な取組例などを取りまとめている。
▼都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000079.html
【参考】都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会の取り組みについては「超重要!自動運転技術を生かす都市構造、ガイドライン作成へ」も参照。
■警察庁による調査検討委員会(2015年度~)
自動運転の実現に向けた調査検討委員会(2020年度~2021年度)
警察庁は2015年度に調査検討委員会を立ち上げ、自動運転時代の道路交通法の在り方をはじめ、自動運転システムを使用する運転者の義務の在り方や自動運転システムにおける規範遵守の在り方、公道実証の環境整備、自動運転システムの走行中データの保存の在り方、他の交通主体との関係など多岐に渡る議論を進めてきた。
2020年7月に始まった「自動運転の実現に向けた調査検討委員会」では、限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスを念頭に、従来の運転者の存在を前提としない自動運転を可能にするため、より具体的な制度や交通ルールの在り方について調査研究を進めた。
自動運転の拡大に向けた調査検討委員会(2022年度~)
前述の調査検討委員会から、さらなるレベル4の進展を見据え、交通ルール上の課題について各種調査・検討を行うことを目的に2022年度に開始したのが「自動運転の拡大に向けた調査検討委員会」だ。
特定自動運行が、走行エリアを管轄する都道府県公安委員会から許可を得る点や、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであることと規定されていることから、高速道路におけるレベル4や自家用車におけるレベル4には制度上課題が残っているため、検討すべき道路交通法上の課題の抽出を進めている。
①「地域の理解」の考え方②高速道路上で ODD を外れた場合や交通事故の場合の措置などの円滑な実施③自家用車の特定自動運行の許可制度への当てはめ方④人または物の運送を目的としないユースケースの特定自動運行の許可制度への当てはめ方――の4課題を抽出した。
2024年度には、東京都内で実用化を目指す動きが活発化しているロボットタクシーを念頭に、現在の技術水準において、開発者側が自動運転車の実装にあたり課題となり得ると認識している交通ルールに関し、すべての交通参加者の安全と円滑確保の観点から課題の有無・対応方法について論点整理を行うための各種調査・検討を行っている。
▼警察庁の各種有識者会議一覧
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/index.html
【参考】自動運転の拡大に向けた調査検討委員会の動向については「自動運転車、路肩の渋滞が「駐車場待ち」か「左折待ち」か判断できず」も参照。
■自動走行に係る官民協議会(2017~2019年)
官民連携の象徴的協議会
未来投資戦略2017に基づき、具体的なビジネスモデルを念頭に置いた実証を円滑・迅速に実施できるよう必要な制度・インフラの整備を時期を明確にして進める上で、実証成果をはじめとした各種情報を官民が共有し意見を交わす場として設置されたのが「自動走行に係る官民協議会」だ。
同協議会における検討成果は、未来投資会議・構造改革徹底推進会合に報告され、次年度の成長戦略に盛り込まれるほか、IT戦略本部で決定する政府全体の制度整備の方針(大綱)や「官民 ITS 構想・ロードマップ」策定に反映される重要な位置づけだ。
地域移動サービスにおける自動運転導入に向けた走行環境条件の設定のパターン化参照モデルを作成するなど、実証成果の取りまとめなどにも大きく貢献した。
▼自動走行に係る官民協議会
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/jidousoukou/index.html
【参考】自動走行に係る官民協議会の取り組みについては「【資料解説】自動運転の官民協議会、第10回の要点は?パターン化参照モデルとは」も参照。
■ラストマイル自動走行等社会実装連携会議(2017~2018年度)
実証プロジェクトをマッチング
ラストマイル自動走行等社会実装連携会議は、自動運転を活用した新たな地域の端末交通システムなどの実現に関心のある者が集い、情報交換やプロジェクトのマッチングを行う場として2017年度に組織化された。
国の取り組みや政策に関する情報提供をはじめ、参加者が取り組んでいるプロジェクトや抱えている課題について意見・情報交換を進め、取り組みを推進していく狙いだ。
アイサンテクノロジーやSBドライブ(現BOLDLY)、ZMP、ディー・エヌ・エー、ヤマハ発動機、ルネサスエレクトロニクス、豊田通商、名古屋大学未来社会創造機構、日立、人日本自動車研究所、NTTドコモなどの企業をはじめ、みちのりホールディングスや京阪バスといった交通事業者や自治体なども広く参加していた。
■【まとめ】国家として世界トップレベルの自動運転環境を構築
このほかにも、「ロボットタクシー導入等に向けた自動運転における自賠法上の損害賠償責任に関する検討会」(2024年度)、「自動運転車の安全性能確保策に関する検討会」(2024年度)、「自動運転に対応した道路空間に関する検討会」(2019年度~2020年度)、「自動運転における損害賠償責任に関する研究会」(2016年度~2017年度)、「自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会」(2018年度)、自動走行ロボットを活用した配送の実現に向けた官民協議会(2019年度~)など、さまざまな会議体が存在する。
国土交通省、経済産業省、デジタル庁が中心的な役割を担いつつ、省庁横断的、そして民間を交えた効果的な議論を進められているからこそ、国家として世界トップレベルの自動運転環境を構築することができたのだ。
日本特有の心配性とも言えるきめ細やかさゆえに公道実証・実用化面は慎重過ぎる傾向にあるが、実用化の波が徐々に社会受容性を高めており、勢いに乗る日もそう遠くない将来訪れるものと思われる。
海外開発勢の日本進出も始まり、激変していくことが予想される自動運転業界。2025年度の動向にも要注目だ。
【参考】関連記事としては「自動運転、日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。










