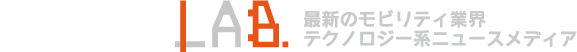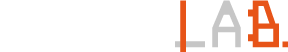2020年の東京オリンピック・パラリンピックで日本の自動運転技術を世界に披露する——。そんな目標も掲げ、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)が日本自動車工業会などと連携して、自動運転部門で実証実験を進めている。
SIP第2期は予定より1年前倒しし、2018年度から2022年度までの間、自動運転システムの開発・検証(実証実験)や自動運転実用化に向けた基盤技術開発、規制改革・制度整備などについて研究を進める予定だ。SIP第2期の計画の全貌に迫る。
■SIP第1期から第2期への流れ
世界各国でその実現に向けて動き出した自動運転の技術開発であるが、2014年にSIP第1期がスタートした頃は、各社がまだ手探り状態で目標もバラバラであったが、ここ数年で一気にその推進が加速したと言える。
これからスタートする第2期の目標はもはや技術向上よりも、実際に地域が運用できる交通システムに仕上げる事を命題としている。着実に社会実装を進め、2020年までに東京の臨海副都心や羽田地区で運転手のいらないバスを走らせ、過疎地や地方都市では市民の足となる自動運転のビジネスモデルをつくることを目指している。
自動運転分野の技術開発は民間自動車メーカーなどが独自で進めているため、SIPでは技術開発は行わず、ダイナミックマップや情報セキュリティーなどの共通基盤技術を開発する。産官学の連携や自治体・住民・事業者との協働も推進していく。国際的に日本の自動運転技術も広くアピールしていきたい考えだ。
■SIP第2期で目指すことと狙い
自動運転を実用化し普及させることにより、交通事故の低減や交通渋滞の削減、交通制約者のモビリティの確保、物流・移動サービスのドライバー不足の改善・コスト低減など、日本が慢性的に抱えていた社会的課題の解決に貢献し、すべての人が質の高い生活を送ることができる社会の実現を目指す。
SIP第2期ではテーマ名を第1期の「自動走行システム」から「自動運転(システムとサービスの拡張)」へ変更し、「実用化」を意識した取り組みを強化する。具体的な目標としては、自動運転の実用化範囲を高速道路だけではなく一般道にも拡張し、自動運転技術を活用した物流・移動サービスを世界に先駆けて事業化することなどを目標に掲げている。
ちなみに第1期から第2期のテーマ名変更理由については、具体的に①SIP第2期は第1期の継続・延長ではないこと②呼称としてより一般的となった「自動運転」を用いることになったこと③自動走行システムという技術開発中心のフェーズから、自動運転の実用化に向けたサービス拡張のフェーズへ入ること—の3点が挙げられている。
また「移動」「物流」「オーナーカー」について、それぞれ個別の実現目標を掲げている。
移動サービスでは「2020年までに限定地域で無人自動運転(自動運転レベル4)移動サービスを実現」、物流サービスでは「2025年以降に高速道路でトラック完全自動運転(自動運転レベル4)を実現」、オーナーカーでは「2025年目途に高速道路での完全自動運転(自動運転レベル4)を実現」「一般道における運転支援技術のさらなる高度化(一般道・自動運転レベル2以上)」といった具合だ。
【参考】自動運転レベルの定義については「自動運転レベル0〜5まで、6段階の技術到達度をまとめて解説|自動運転ラボ ![]() 」も参照。
」も参照。
■研究・開発内容や取り組み内容
自動運転を実用化し普及させていくためには「車両の開発」と「走行環境の整備」を同時に進めていく必要がある。第2期では特に「走行環境の整備」などの協調領域を中心に開発を推進する。安全性の確保のために業界共通で取り組むべき課題は多く、産学官連携で取り組んでいきたい考えだ。
注目されているのが「信号情報技術の開発」や「交通情報利用のための技術開発と多用途展開のための要件・仕組みの検討」「準天頂衛星みちびきからの位置情報サービスに関する調査研究」など。
自動運転に対する社会的受容性の醸成も進め、社会需要性イベントの企画・開催や自動運転のインパクトの明確化、高齢者や障害者などの「交通制約者」への支援に関する研究なども行う。海外研究機関との共同研究なども進め、国際社会との連携にも力を入れていく。
またSIP第2期では、管理法人となる新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)への交付金を活用して取り組みを進める。
■自動運転社会実現へ重責
SIP第2期では、研究成果を公共性を有する団体・機関や民間企業などに引き継ぎ、技術移転をすることも目標に掲げている。民間企業が自動運転開発に力を入れていく中、内閣府が主導するこのプロジェクトは自動運転社会到来に向けた環境を整えていくという意味でも非常に重要な意味を持つ。2018年度から2022年度までの取り組みに注目していきたい。
【参考】SIP第2期については「内閣府のSIP第2期自動運転が始動へ 五輪見据え自動運転バス実証実験|自動運転ラボ 」も参照。
AI自動運転の運命決める勝負の5年間 内閣府のSIP第2期始動へ https://t.co/X1ejPjpsrb @jidountenlabさんから
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) August 7, 2018