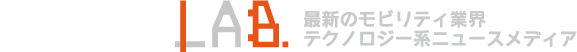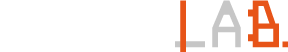中国・アリババグループでクラウドコンピューティングやAI開発・サービスなどを手掛けるアリババクラウドは2020年9月、年次イベント「Apsara Conference 2020」で自律走行が可能な配送ロボット「小蛮驢(シャオマンリュ)」を発表した。EC世界最大手がついに配送ロボットの本格導入に着手するようだ。
北米の雄・Amazon.com(アマゾンドットコム)もすでに「Amazon Scout(アマゾン・スカウト)」の実用実証を米国各地で展開しており、EC各社の取り組みはますます盛んになっているようだ。
なぜ、宅配事業者ではないEC自らが宅配ロボットの開発に力を注ぐのか。アリババやアマゾンの取り組みを中心に、宅配ロボットの有望性について解説する。
記事の目次
■小蛮驢(シャオマンリュ)とは?
小蛮驢はラストマイル配送用自律走行型配送ロボットで、アリババグループのグローバル研究機関であるアリババDAMOアカデミーが開発した。

1回の充電で最大おおよそ100キロ走行することが可能で、一度に50個の荷物を運ぶことができる。DAMOアカデミー責任者のジェフ・チャン氏によると、EC市場の発展が著しい中国では現在1日あたり約2億個の荷物が配送されているが、今後数年で1日あたり10億個に増加すると予想されているという。
混雑した環境下でも自らルーティングして走行することができ、アリババクラウド独自の高精度測位技術により、GPSの電波が弱い場所や電波が届かない場所でも走行することができる。
また、独自開発したヘテロジニアス・コンピューティング・プラットフォームや3D Point Cloud Semantic Segmentation(PCSS)技術、ディープラーニングを活用することで障害物を識別し、人や自動車の動きを数秒前に予測して安全性を高めることができるという。
利用者は、物流子会社のCainiao(菜鳥網絡)やアリババのECモール・タオバオ(淘宝網)のモバイルアプリで配送日時を指定し、ロボット到着後、アプリに表示される受け取り用のパスコードを入力すれば荷物を受け取ることができる。
■アリババグループの取り組み
アリババとCainiaoは2018年、配送ロボットGplus(ジープラス)の開発を発表した。LiDAR開発を手掛けるRoboSenseと共同開発したモデルで、当時、将来的な量産化にも言及している。トラックをそのまま小さくしたような4輪車にLiDARを搭載し、公道走行を可能にした。杭州の本社周辺ですでに実証を重ねているという。
また、Cainiaoは2019年、成都で敷地面積20万平方メートルの自動運転パークの稼働を開始したことを発表している。倉庫や敷地内の物流ソリューションを無人化しており、敷地内で配送ロボットが経験値を重ねながら活躍しているようだ。
2018年には、人工知能製品の開発を行うAlibaba AI Labsがホテル向けの給仕サービスロボット「Space Egg(スペース・エッグ)」を発表したほか、子会社化の食配サービスプラットフォーマー・Ele.me(餓了麼)もドローンを活用した物流に取り組み始めるなど、ロボット技術の実装に積極的なようだ。
配送ロボット開発を手掛けるスタートアップ・Neolix(新石器)のロボットをCainiaoのスマート物流センターに配備するなど、他社技術の導入も進めるほか、自動運転タクシーの開発を手掛けるAutoXへの出資や、配車サービスを手掛ける傘下のAmap(高徳地図)が自動運転スタートアップのWeRideと提携を交わすなど、自動運転分野への関わりも年々深めている。
【参考】Cainiaoの自動運転パークについては「アリババ傘下の物流会社・菜鳥網絡、自動運転パークの稼働開始」も参照。Neolixについては「レベル4級の自動運転物流ロボ、中国Neolix社が大量生産へ」も参照。
■アマゾンの取り組み
アマゾンは宅配ロボット「Amazon Scout(アマゾン・スカウト)」を自社開発し、2019年1月から本社を構えるカリフォルニア州やワシントン州で実証を開始している。40センチ四方程度の6輪仕様小型タイプで、歩道などを走行するラストマイル向けのロボットだ。

試験エリアは徐々に拡大しており、2020年7月にジョージア州アトランタやテネシー州フランクリンでもサービス実証を開始することを発表している。
アマゾンは2017年にロボット開発を手掛けるDispatchを買収しており、Dispatchの技術がスカウトの開発に貢献しているという。2019年には、自動運転レベル3を搭載したEV開発を手掛けるRivianに出資したほか、2020年6月には自動運転開発を手掛けるZooxの買収も発表している。
Zoox買収に関しては、現状、自動運転タクシーの実用化など同社の開発を促進していく目的にスポットがあてられているようだが、将来的には、クラウド事業「アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)」の有効活用をはじめ、拠点間配送などを担う場面にも自動運転技術の導入を進めていく可能性も十分考えられる。今後の展開に要注目だ。
【参考】Scoutについては「米Amazonの自動運転配達ロボ「Scout」、試験の場を拡大中」も参照。Zoox買収については「Amazon、加州の自動運転実績6位のZoox買収!無人配送へ前進」も参照。
■EC他社の取り組み
EC関連では、中国大手のJD.com(京東商城)も早くから配送ロボットの開発に乗り出しており、2017年にはロボット開発を手掛けるGo Further AIと共同で無人配送ロボット「超影」を発表している。高さ1.6メートルのやや大きめのボックスタイプで、2018年には配送ステーションなどで実用実証を開始している。
日本のEC大手楽天も2016年にドローン配送サービス「楽天ドローン」を開始するなど物流改革に積極的で、2019年2月には京東集団と提携を交わし、楽天が国内で構築する無人配送ソリューションに京東のドローンと地上配送ロボットを導入することに合意したと発表している。同年5月に千葉大学の構内、9月からは神奈川県横須賀市の公園で京東の配送ロボットを活用した配送実証実験を行っている。
【参考】楽天の取り組みについては「楽天の自動運転・MaaS・配送事業まとめ ライドシェア企業へ出資も」も参照。
楽天の自動運転・MaaS・配送事業まとめ ライドシェア企業へ出資も ドローンやロボットを最大限活用 https://t.co/3xIhrnsjRX @jidountenlab #自動運転 #ロボット #楽天
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) September 27, 2019
■ラストマイルにおける宅配ロボットのインパクト
ECをはじめとした宅配需要は右肩上がりの傾向にあり、小口多頻度化の進行と物流を担う配送ドライバー不足などを要因にラストマイル配送は社会問題と化している。
象徴的なのがアマゾンの宅配をめぐる攻防だ。佐川急便は2013年、アマゾンとの大口取引によって低く抑えられた配送料が経営を圧迫し、再三の値上げ交渉も決裂して取引を中止した。佐川が抜けた穴を埋めるヤマトも次第に利益が圧迫されるようになり、運賃交渉を活発化している。
アマゾンも個人事業主と業務委託契約を結ぶAmazon Flexを導入するなど独自の配送システムの構築を進めており、宅配大手への依存度は年々下がっているようだ。
ECサイドとしては、送料を可能な限り安くしてリアル店舗や他社サイトから利用者を取り込みたいところだ。しかし、その負担は出店者や配送業者が補うケースが多いため、モデルとして定着しにくい要素を多く含んでいる。無い袖は振れないのだ。
ドライバー不足と業務量の増加で否が応でも人件費を高めなければならない宅配事業者サイドと、少しでも送料を低く抑えたいECサイドの溝を埋めるには、既存の宅配モデルにメスを入れ、業務そのものを効率化するほかないのだろう。
そこで期待が高まるのが宅配ロボットの社会実装だ。自動運転タクシーなどと同様、イニシャルコストは増加するものの人件費を大幅に圧縮することが可能なため、利益を圧迫せずに送料を大幅に引き下げられる可能性が高まるのだ。
送料の引き下げは、ECサイドにとってリアル店舗に対する優位性を大きく高める。ゆえに、EC各社は宅配事業者以上にロボット開発に注力するのだろう。
【参考】宅配ロボット導入が送料に及ぼす変化については「送料が10分の1に…大本命!「自動運転×小売」の衝撃 世界の取り組み状況まとめ(特集:自動運転が巻き起こす小売革命 第1回)」も参照。
■【まとめ】事業コストの圧縮が勝敗のカギに 宅配ロボットめぐるEC攻防が激化
送料引き下げと人件費の削減を両立する宅配ロボットがラストマイル問題を解決する大きなポテンシャルを秘めていることがわかった。EC各社にとっては、物流にかかる事業コストの圧縮が今後の発展のカギとなるため、こうした新たなビジネスモデルの早期確立がライバル社との競争を左右することになるのだ。
アリババとアマゾンをはじめとしたEC大手の開発競争、及び実用化をめぐる競争は、今後いっそう激化しそうだ。
【参考】関連記事としては「自動運転の宅配ロボット(デリバリーロボット)取組事例まとめ!」も参照。