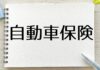自動運転バスやタクシーの実用化により、拡大を見せ始めた自動運転市場。米Waymoを筆頭とする開発プレイヤーが続々と頭角を現し、注目度を増している。
一方、株式市場においては、一部企業が先行してIPOを果たしているものの、まだ目立った動きはない。一般投資家の熱視線を集めるフェーズには至っていないようだ。CruiseやArgo AIといった失敗例もあるため、投資家としてはまだまだ慎重にならざるを得ないのかもしれない。
しかし、こうしたリスクを回避しつつ業績を伸ばすことが可能な自動運転関連企業も存在する。Uber Technologiesに代表される配車プラットフォーマーだ。将来にわたり、こうしたプラットフォーマーが自動運転銘柄のド本命となるかもしれない。
なぜ配車プラットフォーマーが有利なのか。その理由を解説していこう。
記事の目次
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |
| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |
| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |
| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| パソナキャリア |  |
| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |
| タクシーアプリDiDi |  |
| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |
| MOTAカーリース |  |
| お好きな車が月々1万円台から! | |
| スクエアbang! |  |
| 「最も安い」自動車保険を提案! | |
■自動運転と配車プラットフォーマーの関係
自動運転システム開発事業者が花形ではあるものの……
自動運転分野においては、やはり自動運転システムを開発する事業者が花形であり主役となる。世界初の商用自動運転タクシーを実用化した米Waymoは未だに自動運転の代名詞的存在として業界の頂点に君臨している。
中国では、テクノロジー企業の百度を中心に、WeRideやPony.ai、AutoXといった新興開発勢が名を馳せている。日本国内で言えばティアフォーだ。こうした開発勢を中心に業界は動いている。
自動運転技術そのものがまだ発展途上のため、開発各社の技術に注目が集まるのは当然の話だ。より安全なレベル4実現に向けた開発競争の真っ只中にあり、どの企業が技術面で抜け出してくるのか、そして量産化に結び付けていくのか――といった点にまだまだ注目が集まるフェーズだ。
Waymoや百度あたりが技術・実用化面で頭一つ抜け出している印象だが、各社の猛追は激しく、気を緩めれば2~3年で追いつき追い越されかねないほど、業界全体の進化が著しいのだ。
主導権争いはまだまだ続き、開発各社への注目もまだまだ高まっていきそうだが、例えば5年10年後を想像してほしい。各社のレベル4技術が高水準で安定し、量産体制が整ったフェーズだ。
各社の技術間のばらつきが少なくなり、開発技術そのものへの注目度は低下していくことになる。代わって、サービスの提供体制や中身に注目が集まっていくことが予想される。どういった企業がどういった形で自動運転サービスを提供しているのか、付随するサービスは何か――といった観点だ。
例えばWaymoであれば、自動運転システムそのものへの注目度は低下し、どこの国・まちでどのようなサービスを展開しているか、料金はどのくらいか、車内サービスはどのようなものか――といった具合だ。
個別のアプリから汎用アプリへ
こうしたフェーズにおいては、配車プラットフォーマーが大きく存在感を増す。現在、開発各社の大半は自社開発、あるいは自動運転サービスの提供主体となる提携事業者の配車アプリを個々に用いているが、利用者目線で見れば個別のアプリをそれぞれ用意しなければならなく、UI・UXもマチマチで利便性が低い。
しかし、Uber Technologiesのような既存アプリに統合されれば利便性は大きく向上する。Uber Technologiesのアプリさえインストールしておけば、各社の自動運転サービスを利用することができるためだ。使い方も統一され、迷うこともない。場合によっては、運賃比較なども容易に行うことができるようになる。
新たなプラットフォームが勢力を拡大する可能性もあるが、すでに多くの顧客を持つUber Technologiesら既存勢力が有利であることは間違いない。WaymoなどがUber Technologiesとの距離を縮めているように、すでにその兆候は表れ始めている。配車アプリとして世界を網羅するUber Technologiesは大きなアドバンテージを持っているのだ。
つまり、自動運転サービスがスタンダードなものへと変わっていく将来、Uber Technologiesなどのプラットフォーマーがいっそうの躍進を遂げるのだ。

運賃低下による利用増の可能性も
現在主力のライドシェアは徐々に自動運転に置き換えられていくことになる。レベル4のODD(運行設計領域)によるが、近距離移動は自動運転、レベル4が対応していない中長距離移動は手動ライドシェア――といった具合に棲み分けが進む。レベル4の進化とともにその境界線も動き、徐々に自動運転のシェアが高まっていくことが予想される。
さらに、ドライバーを必要としない自動運転サービスは、普及に伴い低コスト化を実現する。開発企業や車両提供企業との契約にもよるが、運賃を下げても開発企業やプラットフォーマーの利益を増大することができる可能性も高まる。需要はさらに高まっていくのだ。
特段の開発費用負担もなし
加えて、プラットフォーマーは自動運転開発費用を負担していない点も注目に値する。現在、開発各社は莫大な資金を投入して研究開発を進めているが、技術が高水準で安定化した後もさらなる高みを目指して開発を進めなければならない。なかなか困難な道なのだ。
言ってしまえば、プラットフォーマーにとって自動運転サービスは、配車サービスにもってこいの新たなモビリティサービスであり、特段の追加費用を要することなく導入に伴う利用増の恩恵を受けることができるサービスなのだ。
技術がスタンダード化する近い将来、自動運転関連業界においてはプラットフォーマーが覇者となっている可能性がありそうだ。
■Uber Technologiesの事業概要
年間31億回の利用規模に成長
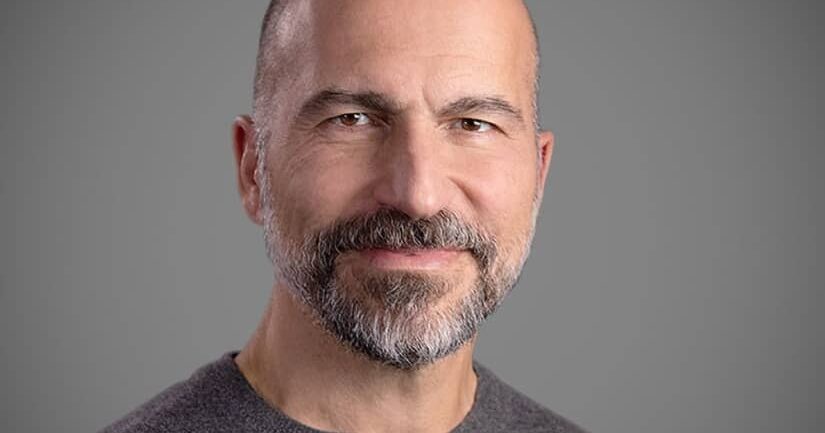
2009年設立のUber Technologiesはライドシェアを中心に世界各地で配車サービスを手掛けており、現在世界70カ国以上、10,000都市以上でサービスを展開している。そのサービスは、自家用車によるライドシェアやタクシーに留まらず、ボートや気球などさまざまなモビリティに及ぶ。
食料品を配達するUber Eatsや貨物配送のUber Freightなど、マッチングサービスの領域も試行錯誤を重ねながら拡大を図っている。マッチングサービスの利用は年間30億回規模に達している。
拡大路線を継続しているため赤字が続いていたが、2023年通期で営業利益11億1,000万ドル(約1,650億円)の黒字を達成し、2024年通期では同27億9,900万ドル(約4,200億円)まで業績を伸ばしている。
2024年の売上収益は前年比18%増の439億7,800万ドル(約6兆6,000億円)で、月間アクティブプラットフォーム消費者数(MAPC)は同14%増の1億7,100万人、利用回数は同18% 増の31億回に達した。ドライバーと配達員は四半期中に合 200億ドル (約3兆円/チップ含む) 稼ぎ、収益は前年比16%増となっている。
サブスクリプションサービスのUber Oneの会員数は前年比60%増の3,000万人に達した。同サービスを新たに6カ国で開始し、合計34カ国となった。さらに、EMEA、APAC、中南米地域の新しい国でUber One for Studentsを開始した。
自動運転開発各社との提携も拡大中
自動運転関連では、中東向けに新たに中国WeRideとの提携を発表している。また、Avrideとの提携のもと、テキサス州内で自動配送ロボットによるUber Eatsの配達を開始した。
日本では、Cartkenとの提携のもと大阪でサービスを展開するとしている。また、大手タクシー配車サービス提供会社と提携し、最大20,000台の車両をプラットフォームに導入する予定で、国内の乗客と海外旅行者による利用の増加により、日本における需要は引き続き堅調としている。
黒字達成後株価は急伸
Uber Technologiesは2019年5月にニューヨーク証券取引所に上場を果たした。公開価格は仮条件(44~50ドル)の下限に近い45ドルに設定され、注目の初値は42ドルで公開価格を下回った。大型IPOとして注目度は高かったものの、投資家の目は厳しかったようだ。
上場後、株価はゆるやかに下落し、同年末には30ドルを下回り、2020年3月には20ドルを切る寸前まで下落した。その後、コロナ禍における米国の経済政策とともに株価は回復し、2020年末には50ドル台、2021年前半には一時60ドル台まで値を上げた。
その後、他社同様経済政策の影響で再び下落に転じ、2022年6月ごろには20ドル台前半で推移した。しかし、黒字を達成した2023年を転機に株価は上昇をはじめ、年初の26ドルから年末には60ドル台まで数字を伸ばした。
2023年からの黒字化は、しっかりと株価に反映されているようだ。

【参考】Uber Technologiesの株価については「Uberが株価50%急騰!自動運転タクシーの展開発表が起点 最高値更新へ」も参照。
伸びしろの割にPERはまだ低水準でお買い得?
本業の伸びしろはまだまだ多く、自動運転サービスのプラットフォーマーとしても機能し始めた。今後のさらなる成長に期待は高まる一方だ。
ここでやっと本題だ。注目度が高まるUber Technologiesの株価は、果たしてお買い得なのだろうか。
判断指標の一つに「株価収益率(PER)」がある。Price Earnings Ratioの略で、株価がEPS(1株当たり純利益)の何倍の水準になっているかを示す数値だ。企業の純利益をベースに考えると、PERが高ければ高いほど株価は割高となる。逆に、低ければお買い得と言えるわけだ。
日本では、概ね15倍を目安に割安かどうかを判断することが多いようだ。
Yahoo!ファイナンスを参照すると、2025年2月27日時点におけるUber TechnologiesのPERは15.76倍となっている。15倍を若干超えているが、では世界に名だたるテック企業や自動運転業界・モビリティ業界をにぎわす他社はどのような水準なのか。
半導体大手のNVIDIAは、PER40.45倍となっている。EV大手テスラに至っては126.43倍だ。株式市場を代表する2銘柄だけに相当割高な状態と言えるが、それでも買われ続けるほど人気なのだろう。参考までに、アップルは35倍、アルファベット(グーグル)は20.38倍、アマゾンは36.88倍の水準だ。
トップクラスのテック企業と比較するのは見当違いと言われそうだが、マッチングプラットフォーマーとして圧倒的なシェアを誇るUber Technologiesは、戦略次第でこうしたテック企業に匹敵するポテンシャルを有する――と言っても間違いではないはずだ。
今は「ライドシェア企業」としてのイメージが強いが、人間の生活に欠かせない人やモノの移動に利便性をもたらすソリューションと捉えればそのポテンシャルは未知数とも言える。知名度と実績を生かし、さまざまなマッチングサービスに拡張することもできる。Uber Technologiesのポテンシャルを侮ってはならないのだ。
そう考えれば、PER15.76倍のUber Technologiesはお買い得に感じられないだろうか。前述した自動運転市場における展望も踏まえると、株式市場におけるポテンシャルも非常に大きいのではないだろうか。
なお、同業ライバルのLyftはPER217倍となっている。利益水準が低いなどの要因が考えられそうだ。自動運転関連では、Aurora InnovationやLiDAR開発を手掛けるLuminar Technologies、Innoviz Technologiesなどが上場済みだが、各社ともまだ赤字のため算出できない。モービルアイも赤字だ。
■【まとめ】自動運転時代に本領発揮
Uber Technologiesのダラ・コスロシャヒCEOは、米国だけでも自動運転市場は1兆ドル(約152兆円)以上の規模があると口にしたそうだ。もともと自動運転技術の自社開発を進めていたことが物語るように、配車サービスは未来の自動運転時代を見据えたものでもある。
すでに黒字化を達成し勢いに乗るUber Technologiesだが、その本領が発揮されるのは来るべき自動運転時代なのかもしれない。そう考えると、お買い得のうちに同社株式を手にしておくのもアリではないだろうか。
※編注:この記事は特定の株式銘柄への投資を推奨するものではありません。
【参考】ダラ・コスロシャヒCEOの発言については「自動運転の機会潜在性「米国だけで1兆ドル以上」 Uber CEOが発言」も参照。