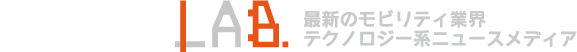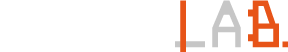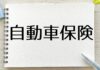次世代移動通信システム「5G」とともに実証が進む自動運転車の遠隔操作技術。自立走行する車両の監視やバックアップが主な役割となるが、通信技術を用いて、本来各車両に搭載すべきシステムを簡素化する技術開発なども進んでいるようだ。
こうした技術が進展すれば、自動運転車に必須と言われるAI(人工知能)システムなども簡略化・省略することが可能になる。現在開発が進められる遠隔操作技術には、どのようなパターンがあるのか。
遠隔操作技術に焦点を当て、開発状況を交えながら導入メリットなどを探ってみた。
記事の目次
■「遠隔型」の自動運転とは?
子どものころ、「ラジコンを大型化すれば人を乗せて走行できるのではないか」と考えたことはないだろうか。このアイデアは、現在開発が進められている遠隔操作技術によってより高度に実現するかもしれない。
一般的に、自動運転車には「目」となるカメラやLiDARなどのセンサー類、そしてセンサーから得た情報を解析し、ブレーキやアクセル、ステアリング操作などの制御指令を下す「脳」となるAIなどが組み込まれ、自立走行を可能にしている。とりわけ、ドライバーの代わりにさまざまな情報を収集・解析し、判断を下すAIは、膨大なシステムとなる。
このAIの役割を、遠隔技術によって管制塔が担うシステムがまず考えられる。仕組みとしては、自動運転車に搭載されたセンサーの画像データなどがリアルタイムで管制塔に送信され、このデータを管制塔に設置されたAIシステムが瞬時に解析し、制御指令を各車両に送信するシステムだ。つまり、管制塔がクラウドの役割を果たし、ネットワーク経由でコンピュータ資源をサービスの形で提供する仕組みだ。
もう一つは、管制塔に設置したコクピットから直接車両を遠隔操作するシステムだ。AIそのものを扱わず、車両に搭載されたセンサーの映像を管制塔でリアルタイムに表示し、モニターを見ながらアクセルペダルやステアリングなどが備わったコクピットでドライバーが直接運転する仕組みとなる。ラジコンを操作するような感覚で、スマートフォンの画面を見ながら小型ドローンを操作する技術の応用版のイメージだ。
■「遠隔型」のメリットは?
管制塔AIシステムでは、本来各車両に搭載するはずだったAIシステムを簡素化、もしくは省略することで、大幅にコストを削減することが可能になる。
管制塔にはスーパーコンピュータのように膨大な情報を処理するAIシステムが必要となるが、各車両に配備するAIシステムを省略するほうがはるかにコストを下げることができる。
一方、管制塔コクピットシステムは、AIそのものが不必要となり、各車両にコクピットを用意する必要もない。
両者とも運転席が不要となり、余計なシステムを車両に搭載する必要がなくなるため、車内スペースを広く有効活用することが可能になる。
また、システムのアップデートなども、システムが管制塔に集中しているため作業を効率的に行うことが可能になるだろう。
いずれにしろ、個々の車両はセンサーを搭載したラジコンのような存在に近づいていき、開発・生産コストの低減が見込まれることになる。
そして開発・生産コストの低下は、より多くの用途に技術を向かわせる。農業機器や工場内の機器、ドローンなど、関連技術はすでに実用化が進んでいるが、人が立ち入ることができない災害現場の調査車両や火星探査機など、さまざまな分野で技術を活用する環境が育まれていくことにつながるのだ。
コストの低減効果、スペースの有効活用、システムアップデートの効率化、システムの多用途化―以上4つのメリットが、遠隔システム導入により創出される。
■「遠隔型」のハードルは?
管制塔からの指令のもと走行する遠隔自動運転車。一番の懸念材料は、やはり通信技術だ。膨大な量のデータを収集し、瞬時に指令を届ける必要がある。通常の自動運転車の場合、センサーの画像をAIが解析し制御指令を出すまでにそれほどのタイムラグは生じないが、管制塔システムの場合、各車両と管制塔間の通信時間が生じるため、より大きなタイムラグを生じる結果になる。
低遅延・大容量通信が可能となる5G技術は必須だが、コンマ1秒のタイムラグが重大な事故を招く可能性もあるため、比較的低速走行で一定の範囲・ルートを走行する自動運転車に向いているのかもしれない。
また、万が一通信が途切れた場合、各車両にとってはAIシステムが故障したも同然で、車両はただちに走行不可状態に陥る。こうした際に安全かつ速やかに停車措置をとるシステムや復旧システムも必須だが、通信切断そのもののバックアップシステムを搭載し、すぐに他の回線に切り替えて走行できる環境づくりなども求められそうだ。コクピット型も同様で、当然低遅延技術やバックアップシステムなどが必須となる。
こうした状況下、リモート運転システムの開発を進める株式会社ソリトンシステムズが「超短遅延技術」の実用化に取り組んでいる。
同社は2018年11月、東京から名古屋の自動車をリモート操作し、実用スピードで遠隔運転するデモンストレーションを実施したことを発表。「Glass to Glassでの遅延時間」(映像がカメラのレンズに入ってから表示装置のモニターに映し出されるまでにかかる時間)を最小40ミリ秒台まで短縮可能な超短遅延技術を適用したほか、運転視界内の死角を除去する画像処理や、自動車の揺れの伝達などの諸方式を組み込むなどし、実用的な自動車走行スピードで安全なリモート運転操作が可能であることを実証した。
2019年6月には、名古屋で実施した遠隔運転の動画を初公開した。「Glass to Glassでの遅延時間」50ミリ秒台を実現しており、これは時速60キロメートルで遠隔車両を走行させることができるレベルという。
【参考】ソリトンシステムズの取り組みについては「ソリトンシステムズ、遠隔運転のYouTube動画を公開 将来の自動運転の補助に」も参照。
ソリトンシステムズ、遠隔運転のYouTube動画を公開 将来の自動運転の補助に https://t.co/fkycoivdVr @jidountenlab #ソリトンシステムズ #遠隔運転 #自動運転
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) June 27, 2019
■家電メーカーも参入
遠隔自動運転技術の開発に取り組む企業は幅広い。自動車メーカーや通信メーカー以外にも多くの企業が参入しており、とりわけリモートコントロール技術を持つ家電メーカーらのボルテージが高まっているようだ。
ソニーの取り組み
ソニーは2017年10月、新たな移動体験の提供を目的としたコンセプトカート「SC-1」の試作開発を発表した。SC-1は乗員の操作による運転に加え、クラウドを介した遠隔操作による走行も可能にしており、車両の前後左右に取り付けたイメージセンサーによって360度全ての方向にフォーカスが合わされた映像で周囲の環境を把握できるという。
2019年3月には、NTTドコモと5Gを活用した新たな利用シーンの創出に向け手を組んだ。ドコモがグアム島に開設した「ドコモ5GオープンラボGUAM」、及び子会社のドコモパシフィック社が2019年夏以降に提供開始予定の屋外試験環境を活用し、SC-1の遠隔操作実現に向けた共同実証実験を行うことに合意した。
実験では、5Gの低遅延、大容量、高速の特長を生かし、長距離間におけるSC-1の遠隔操作に必要な伝送速度の確認や操作品質評価などについて、グアムの5Gネットワーク試験環境を経由することにより検証することとしている。
パナソニックの取り組み
一方、自動車コクピットのエレクトロニクス化などに力を入れるパナソニックは、米ラスベガスで開催されたCES 2019で、小型モビリティのコンセプトカー「SPACe_C」を披露した。
従来比2倍以上の出力と小型化を実現した小型EV向け「48V ePowertrain」新プラットフォームをベースとした上下分離構造のモデルで、上側のキャビンを乗せ換えることで多用途に活用できるコンセプトだ。
日経ビジネスが報じたところによると、こうしたコンセプトカーをもとに、高価なセンサー機能を遠隔側に移し、代わりに遠隔側の計算機にLIDARのデータを集めまちなかを走行する車両間で共有する開発案などが出ているようだ。
こうした開発が進むと、個々の車両は従来の「自動車」から語弊はあるが「高性能なラジコン」的な要素を深めていき、家電メーカーらの新たな成長分野としての側面を強めていく可能性が高い。
家電大手も注目の遠隔自動運転は、既成概念を超えさまざまな形で実現するのかもしれない。
【参考】SPACe_Cについては「自動運転時代には「上下分離構造」が当たり前に?!パナソニックの「SPACe-C」」も参照。
CES 2019:パナが提案する「上下分離構造」自動運転車が便利! https://t.co/IUEI0EE3A5 @jidountenlab #自動運転 #上下分離構造 #CES
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) January 10, 2019
■自動車関連メーカーの取り組み
自動車関連では、国の音頭のもとさまざまな実証が進められている。産業技術総合研究所などは2018年11月、福井県永平寺町における「ラストマイル自動走行の実証評価」に関連する新たな実証として、遠隔ドライバー1人が2台の自動運転車両を運用する遠隔型自動運転の実証実験を行うことを発表した。
【参考】産業技術総合研究所の取り組みについては「産業技術総合研究所、遠隔自動運転の実証実験 世界初、1人で2台を運用」も参照。
2019年2月には、アイサンテクノロジーやKDDI、ティアフォー、名古屋大学などが5Gを活用した複数台の遠隔監視型自動運転の実証実験を愛知県一宮市で実施した。愛知県ではその後も「あいち自動運転推進コンソーシアム」活動の一環として同年3月、愛・地球博記念公園(モリコロパーク)でティアフォーら県内企業3社による遠隔型の自動運転実証実験を実施している。
【参考】愛知県での取り組みについては「国内初!5G車両を含む2台の遠隔監視型自動運転の実証実験 愛知県一宮市で実施」も参照。
NTTデータと大和自動車交通、群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センターは2018年9月、東京都内の公道で複数の自動運転車両を用いたオンデマンド移動サービスの実証実験を実施し、配車依頼の受け付けをはじめ、車両への走行指示や走行中の遠隔監視などを運行管制システムで実現する取り組みを行った。
【参考】NTTデータなどの取り組みについては「NTTデータ、自動運転移動サービスの実証実験 豊洲の公道、将来はレベル4目指す」も参照。
ソフトバンク系のSBドライブも、遠隔運行管理システム「Dispatcher(ディスパッチャー)」を開発し、実用化に向け各所で実証に力を入れている。
こうした動きに呼応するかのように、遠隔操作に対するルール作りも進んでいるようだ。読売新聞などが報じたところによると、警察庁は2019年3月17日までに、遠隔自動運転技術を活用したバスやタクシーの実証実験において、遠隔操作者に2種免許の所持を義務づける方針を固めたようだ。
【参考】警察庁の取り組みについては「警察庁、自動運転の遠隔操作に2種免許の保持義務付けか」も参照。
警察庁、自動運転の遠隔操作に2種免許の義務付け検討か 全国の実証実験で適用へ? https://t.co/BKMTymzVPu @jidountenlab #警察庁 #遠隔 #自動運転 #免許
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) March 18, 2019
■【まとめ】遠隔操作技術の進化が既成概念を打ち破る
遠隔自動運転の肝は5Gに代表される高速低遅延の通信システムにあり、自動運転レベル4の運行をはじめ、農業機械やトラックの隊列走行などさまざまな分野で活用される。基本は通信技術と自動運転技術にあるが、その中の一案として、個々の車両のシステムを簡素化して高性能ラジコン化するような開発も進められているのだ。
もちろん、実用化に際しては、多くの場合一定のAIシステムを車両に搭載し、自由度や安全性などを高めることになるものと思われるが、こうした考え方自体が既成概念であり、新たな技術はその壁を破っていくものともいえる。
将来、当然のように家電メーカーが自動運転車両を製造し、洗濯機の隣の売り場で自動運転車が販売されている……といったことも、実現する可能性はゼロではないはずだ。
【参考】関連記事としては「【最新版】自動運転車の実現はいつから?世界・日本の主要メーカーの展望に迫る|自動運転ラボ」も参照。
【最新版】自動運転車の実現はいつから?世界・日本の主要メーカーの展望に迫る https://t.co/wGPYiXnZEg @jidountenlabさんから
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) August 22, 2018