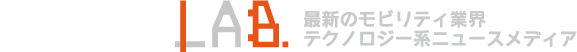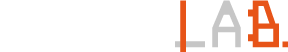実証段階からサービス段階への移行を強めている自動運転技術。移動や輸送サービスなどを無人化する技術として、本格市場化が目前に迫っている印象だ。
一方、すでに市場化が始まっている分野もある。自動運転技術を搭載した建設機械や農業機械だ。機械の種類にもよるが、ダンプトラックやトラクターなどは乗用車よりも早く自動運転市場の開拓を始めている。
一般乗用車や商用車に比べ、建機や農機の自動化がなぜ先行しているのか。その理由に迫っていく。
記事の目次
■建設機械や農業機械における自動化の歴史
無人ダンプトラックは1970年代にすでに発表
日本建設機械工業会が発行した「日本建設機械史」などによると、高度成長を経て安定成長時代に入った昭和50年代ごろにロボット技術による省力化が各産業で脚光を浴び、建機においても自動化の機運が高まって「建設ロボット」の開発が始まったという。
▼日本建設機械史
https://www.cema.or.jp/general/organization/ccgh5100000004sc-att/kenki3_2020.pdf
各機能にコンピューター制御を導入した機能別の自動化が中心だが、建機のロボット化における重要な転機と言える。
無人化関連では、1976年に小松製作所が電磁誘導方式による無人ダンプトラックを発表したという。また、1980年代後期、新キャタピラー三菱(現キャタピラージャパン)が高知県の鳥形山石灰石鉱山に無人ダンプトラックを導入したという記録が残っている。
キャタピラー、小松ともに20世紀には無人ダンプトラックの開発に本格着手しており、1990年代にはGPSを活用した無人ダンプトラックの走行試験や試験導入なども進められていたようだ。
その後、21世紀に入り、自動運転技術やIoT技術の進展とともに建機の自動化・無人化を図る取り組みが大きく進み始めた。
農機のスマート化はSIPなどを通じて大きく加速
農機においても、1990年代にはすでに一部研究機関や企業が自動化・無人化に向けた研究に着手していたという。
担い手不足などを背景に2010年代にスマート農業の機運が一気に高まり、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)における官民協働の研究開発などを通じて本格的な製品化に向けた取り組みが進んだ。
近年盛んになっている公道における自動運転開発と共通する技術は多いが、建機・農機の自動化はこうした動きと独立して進められてきたようだ。
■公道と建設現場・農業現場の違い
建設現場や農業現場は制限区域化

一般公道における自動運転の場合、車道を走行するさまざまな車両をはじめ、路肩の駐停車両、歩行者や自転車などが走行経路に混在する。自動運転車は、各交通参加者が思い思いの移動を繰り返す中、交差点など複雑な環境下を含め自律した走行を行わなければならない。
一方、建設現場は一般公道と異なり、歩行者など不特定多数の交通参加者が混じることのない制限区域となる。多くの場合、入口に警備員が立ち、建設機械の動線や作業員が立ち入れる場所などを明確に区切り、安全を最大限確保している。自動運転システムを搭載した車両は、あらかじめ設定したルートやエリア内を走行する。
農業の現場も基本的に不特定多数のものが自由に立ち入れる環境ではなく、制限区域化の私有地となる。畑や水田など明確に区切られた広大な領域を走行する。
こうした不特定多数が流出入しない制限区域化においては、自動運転システムが注意しなければならない事象が減少するため、自律走行の難易度が下がる。
歩行者などのオブジェクトに対し、ノーマークとまではいかないものの一般公道のように神経質なレベルで注意を払う必要はなく、自動運転車を優先する形で走行させることも可能になる。
特有の課題も
一般公道に比べ、制限区域化は自動運転の実用化の観点から優位にあると言えるが、現場特有の難易度もある。公道は大半がきれいに整地され、多くの車道は区画線でしっかりと区切られているが、建設現場や農地には明確な区画線はなく、地面に凹凸があるケースも多い。
道路標識や道路沿いの建築物などランドマークとなり得るものも少ないため、自車位置推定が難しい面もありそうだ。
また、建設機械や農業機械は、ただ走行すればよいわけではない。それぞれの機械が土砂の運搬や掘削、整地、耕うん、代かき、播種などの役割を担っている。自動運転のメリットを生かすには、こうしたタスクの自動化も欠かせない。自動化できるタスク以外は遠隔操作を活用して車内を無人化するなど、少しずつ機能の高度化を図っている段階だ。
ただ、やはり制限区域化であるメリットは大きい。基本的に道路交通法などの法律が厳格に適用されることはなく、労働安全衛生法令などに従ってしっかりと独自の安全対策を施すことで実用化できるため、一般公道よりも早く社会実装が進んでいるのだ。
統一基準作りに向けた動きも着々と進展

建設関連では、担い手不足や生産性向上といった課題解決に向け各社が独自に自動化を推し進めているが、安全や開発面での統一的基準がなく、企業・現場ごとの安全対応や各機器・システムごとの開発となっているのが現状で、効率的な開発や普及環境の整備が求められている。
このため、国土交通省や厚生労働省などが2022年3月に「建設機械施工の自動化・自律化協議会」を設置し、建機における自動・自律・遠隔施工を実施する際の安全ルールの標準化や自動化目標の設定、協調領域の設定、自動化機器の性能などについて検討を進めている。
安全ルールを標準化し設定することで、各現場において速やかに施工着手できるほか、各機会が備えるべき要件などを明確化することで開発を促進していく狙いだ。
当面の自動化対象は、人を排除した無人エリア内での施工を想定しており、山間部など一般人が立ち入ることがない施工現場から順次展開していく方針だ。
2020年度中に「自動・自律施工の安全ルール(第一段階)」を策定・公表し、2023年度に「無人エリアにおける自動・自律施工の現場検証要領」や「無人エリアにおける自動施工機械の機能要件」、第一段階から条件を拡大した「自動・自律施工の安全ルール(第二段階)」をそれぞれ策定・公表していく計画としている。
農業関連では2017年にガイドライン発表
農機関連では、農林水産省が「スマート農業の実現に向けた研究会」などを通じて2017年3月に「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」を策定している。
▼農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン
https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/gizyutu/attach/pdf/210326-3.pdf
2021年に発行された改訂版では、ロボット農機の定義をはじめ、リスクアセスメントと保護方策の立案などの安全性確保の原則、使用上の条件、製造者・販売者・導入主体それぞれに求められるべき要件、事故等発生時の対応などが取りまとめられている。
自動運転可能な農機としては、トラクター、茶園管理用自走式農業機械、田植機、自走式草刈機、自走式小型汎用台車の5種を挙げ、それぞれ使用上の条件などを記載している。
なお、自動運転レベル同様農機における自動化技術もレベル分けされており、従来の手動操作はレベル0、人が搭乗しながら自動操舵や直進アシスト行うものがレベル1、人の近接監視・あるいは目視可能な遠距離監視のもと自律走行・作業を行うものがレベル2、完全無人状態で遠隔監視のみ行うものがレベル3となっている。
農機の種類にもよるが、現在製品化されている農機はレベル2に及んでいる。
■建設機械各社の開発動向
導入実績豊富な無人ダンプトラック
コマツは、鉱山向けの無人ダンプトラック運行システム「AHS」を2008年に商用化し、その後の10年間で100台超が世界各地の現場に導入されている。世界最大手の米Caterpillarも、すでに500台以上の無人トラックを世界中で稼働させているという。
ボルボ・グループも鉱山・採掘現場などにおける自動運転化を促進しており、2018年にノルウェーの鉱業現場に自動運転トラック6台を提供し新たな輸送サービスを開始している。公道走行も含めた自動化に期待が寄せられるところだ。
ソフトウェア開発やIoT開発を手掛けるJIG-SAWやAI開発企業のアラヤ、建設機械の遠隔操作・自動運転化技術の開発を進めるARAVなども建機自動化に取り組んでいる。
海外では、米Built RoboticsやSafeAIといったスタートアップも建機の自動化ソリューションの開発を進めている。SafeAIはマクニカとパートナーシップを締結しており、トータルソリューションを提供している。
【参考】自動運転建機については「自動運転と建機(2022年最新版)」も参照。
【参考】SafeAIとマクニカの取り組みについては「建機の自動運転化で「現場」の常識が変わる!(特集:マクニカのスマートモビリティへの挑戦 第10回)」も参照。
自動運転と建機(2022年最新版) https://t.co/RsgrzwCuV4 @jidountenlab #自動運転 #建機
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) June 5, 2022
■農業機械各社の開発動向
ロボトラクターが続々製品化
クボタは2016年に自動操舵機能を備えたトラクターを発売し、翌2017年には有人監視のもと無人自動運転を実現するロボトラクターを市場投入している。「Agri Robo」シリーズには、トラクターのほかコンバインや田植え機もラインアップされている。
ヤンマーも2018年から自動運転トラクターを順次発売しており、自動運転農機シリーズ「SMART PILOT」にはオート田植機やオートコンバインなどもラインアップ済みだ。
井関農機も有人監視型のロボットトラクターや土壌センサー搭載型の可変施田植機などを製品化している。
海外では、最大手のDeere & Companyが先行しており、完全自律走行型のトラクターを2022年中に量産化・市販する計画を発表している。
日本のNSW(旧日本システムウエア)や米Autonomous Solutions(ASI)、中国FJDynamicsのように、後付け可能な自動運転システムやプラットフォームの開発を進める企業も続々登場している。
【参考】農機開発メーカーの動向については「自動運転と農業トラクター(2022年最新版)」も参照。
【参考】NSWについては「後付け可能!NSW、自動運転制御ユニットの提供スタート 農機や建機など向けに」も参照。
自動運転とトラクター(2022年最新版) https://t.co/mdXl40gPiI @jidountenlab #自動運転 #トラクター
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) June 3, 2022
■【まとめ】各タスクの自動化・無人化技術の進展に注目
制限区域化で作業を行う建機・農機は自動運転実用化に適しており、生産性向上や安全性向上などの観点から多くの需要も見込める分野と言える。
その一方、建機・農機は各機械が担うさまざまなタスクも無人化できなければ完全無人化を図ることはできない。自動車分野における自動運転技術の多くはそのまま建機・農機にも応用可能なため、今後は各タスクを自動化・無人化する技術の進展に注目したいところだ。
【参考】関連記事としては「自動運転はどこまで進んでいる?(2022年最新版)」も参照。