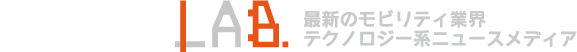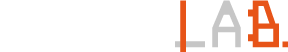独自動車メーカーのフォルクスワーゲンが「We」を冠した各種サービス展開に力を入れている。WeShare、WeExperience、WePark、WeDeliver、WeChargeといった具合に、カーシェアをはじめ駐車場検索や決済、マイカーへの宅配サービスなど多角的にサービスの導入を進めており、今後もこの流れは続きそうだ。
しかし、こうした展開を危惧する見方もある。いわゆる「流行」だ。大手企業によるブランドネーム・流行ネームの多角事業化はその事業分野の流行の象徴となるが、これが時として業界の「あやしい兆候」にもなるのだ。
こうした流行がなぜあやしい兆候となるのか?また、自動運転関連分野において現在どのような兆候が表れているのか?――について解説していこう。
記事の目次
■流行ネームの広がりは黄色信号?
「We」という名を使った企業やサービスは近年増加傾向にあるようで、メジャーなところでは、オフィスシェアビジネスを展開する米WeWorkや、中国テンセントのチャットアプリWeChatなどが挙げられる。自動運転関連では、中国のスタートアップ「WeRide.ai」が有名だ。
「We」は「私たち(は)」という日常的によく使われる単語であるため、流行り廃りに関係なく使用されることが多そうだが、非常に使い勝手の良い単語であり、特にMaaSのようなサービス系では流行りネーム化し、ブームが起こったかのように多用される可能性もある。
かつてインターネットバブルに沸いていた時代、「ドットコム」を冠した社名や事業名が乱発されたのを覚えている方も多いのではないだろうか。
IT系ベンチャーをはじめ、ソニーが「ソニースタイルドットコム・ジャパン」、ファミリーマートが「ファミマ・ドット・コム」といった子会社を立ち上げるなど、大手もインターネットサービスの事業化に際しドットコムを用いた。
年月を経て、結果としてドットコムの多くは事業名の変更や消滅などにより姿を消してしまったが、その背景には、流行ネームそのものの問題ではなく、流行する事業への安易な参入と展開に問題の本質がある。
当時、e-コマースの可能性などが大きく広がり、デジタルやインターネット分野の事業化が相次ぎ、数多くのベンチャーが設立されるとともにジャンルを問わず数多くの大手企業も力を入れた。インターネット分野に注力すること自体は間違いではないものの、中には明確なビジョンや技術力を伴わず、まさにブームに乗る形で「とりあえず参入」するケースも多かった。
ある意味、ドットコムのようなネームが流行りだし、そこに大手がこぞって乗り出したときは黄色信号だ。事業そのものがブーム化され、内容を伴わない事業展開が乱発される恐れがあるのだ。
【参考】フォルクスワーゲンのWeについては「VW(フォルクスワーゲン)「We」のMaaS事業解説&まとめ」も参照。
VW(フォルクスワーゲン)「We」のMaaS事業解説&まとめ https://t.co/uv6ure87jV @jidountenlab #VW #We #MaaS
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) December 8, 2019
■AI分野にも黄色信号?
自動運転を含め、世界的な開発ブームが巻き起こっている「AI(人工知能)」にも、警鐘を鳴らす声は多い。ディープラーニングの登場などによりAIの可能性が飛躍的に広がり、次世代技術の構築に大きく貢献していることは事実で、高度な開発能力を持つ企業やスタートアップに注目が集まっている。
一方で、開発能力を伴わずに「AI企業」を名乗る例も散見されており、受注した仕事を外部にふり、問題が起きた際には責任逃れする企業もあるようだ。こうした例は、業界全体のイメージを落としかねない。
自動運転分野では、前述のWeRide.aiをはじめ、中国のPony.aiやRoadstar.ai、米Apex.AIなど「.AI」が流行している感を受ける。個々の開発能力を問題視する気はないが、米Drive.aiのように資金難から身売りする企業も出ており、勝ち組と負け組が出始めているのも事実だ。
「AI開発を進める新進気鋭のスタートアップ」と言うと聞こえは良いが、開発能力とともに事業として明確なビジョンを持ち合わせているかが重要だ。
【参考】Drive.aiについては「資金難に陥ったDrive.ai、資金難でアップルに身売り 自動運転スタートアップ」も参照。
資金難に陥ったhttps://t.co/XBrjjZh4Xn、資金難でアップルに身売り 自動運転スタートアップ https://t.co/AB9BUaLbkx @jidountenlab #Apple #自動運転 #買収
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) June 26, 2019
■「〇〇ペイ」が流行るキャッシュレス決済は?
国内では、「〇〇ペイ」というキャッシュレス決済がまさに流行中だ。ソフトバンク系のPayPayをはじめ、楽天ペイ、LINE Pay、メルペイ、ゆうちょPay、ファミペイ、au Pay、Apple Pay、Google Pay……と枚挙にいとまがない。自動車関連では、トヨタが「TOYOTA Wallet」を発表し、キャッシュレス決済市場に本格参入を果たしている。
まさにキャッシュレス群雄割拠の時代だ。国策を背景に広がりを見せるキャッシュレス決済の機会はまだまだ裾野が広く、新規参入組もまだまだ増えそうだ。
ただ、ユーザー目線で言えば、すでにおなか一杯の感が強いのではないだろうか。各社が顧客獲得に向けキャッシュバックなどサービスに力を入れるのはうれしいものの、「A店では〇×ペイ」「B店では△□ペイ」――と対象サービスが分かれているケースが多く、使い分けるのは正直しんどい。
近い将来淘汰が始まるものと見られ、こちらも勝ち組・負け組が出始めるだろう。「なんとなく参入したペイ」は淘汰され、ユーザーや提携店舗の利便性を第一に考えたペイメントサービスが生き残っていくことになる。
【参考】キャッシュレス決済については「自動運転化・コネクテッド化が金融業界にもたらす変化とは? 新サービス続々登場で決済機会が増加」も参照。
自動運転がもたらす終焉無き「決済手数料バブル」が始まる…金融業界、自動車イノベーションで莫大な恩恵|自動運転ラボ https://t.co/MOQxUREZcI @jidountenlab #自動運転 #金融 #決済
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) September 16, 2018
■自動運転関連ではMaaSに警鐘
自動運転分野では近年、MaaSに関する取り組みが急増傾向にある。鉄道やバスなどの交通事業者をはじめ、経路検索などを扱うデータ企業、プラットフォーム開発企業、付加サービス企業など、裾野は大きく拡大している。
全国各地で自治体などとの連携のもとMaaS実証も盛んに行われ始めている。全国的に「MaaSを促進しよう」といった機運が高まっており、試験導入などの例はますます増えていくものと思われる。一般市民の認知度も今後どんどん上昇していくだろう。
ただ、ここに懸念が残る。地方や観光地の交通形態に課題があるのは事実だが、「横に習え」で導入するケースが相次ぐ可能性があるのだ。
各交通事業者が連携したサービスを受けることができるといった枠組み・形だけを作って成果とするケースや、中心市街地活性化などでよく見られる数字のみを追い求めるケースなどだ。コンサルティング企業が計画づくりを担い、各地で画一的な活性化事業を行っている例は多い。
MaaSにおいても、こうした画一的な事業化が進む可能性がある。各地でMaaSが誕生する契機となるのは喜ばしいことだが、「交通に関する課題を解決する」という本質部分において、ユーザーが置き去りにされる可能性があるのだ。
MaaSの本質は利便性の高い移動サービスを構築することにあるが、そこに介在する地域の個性や住民の気質なども考慮し、真に支持されるサービスを作り上げなければならない。ユーザーエクスペリエンス(UX)を充実させるためには、器だけのMaaSでは不十分なのだ。
自動運転ラボでも「MaaS UXラボ」を設立し、その「MaaS×UX」について研究している。まさに前述のようにMaaSの本質である利便性の高い次世代モビリティサービスの普及を後押しすることなどが目的だ。
【参考】関連プレスリリースとしては「MaaSxデジタルキーをテーマとしたUX研究機関「MaaS UXラボ」設立に伴う、TBSラジオ「ACTION」スマートキー特集への出演のお知らせ – 自動運転ラボ」も参照。
■自動車メーカーの本質とは?
自動車メーカーが特に気を付けなければならないのは、自動車メーカーとしての本質だ。「自動車をつくる会社からモビリティ・カンパニーにモデルチェンジする」と明言したトヨタは、MaaSをはじめ決済サービスなどさまざまな取り組みを加速させている。フォルクスワーゲンやダイムラーなども同様だ。
ただ、自動車メーカーの本質は当然ながら「自動車」にある。これからの時代を見据え、さまざまな移動サービスとの連携や関連サービスなどに力を入れるのも重要だが、「なんでもできるMaaS」の構築が目的になってしまうと、本来の「車を使った移動」という本質部分を失いかねない。
自社にできることと自社がやりたいこと、そしてユーザーが求めていることそれぞれが合致するのが理想だが、ときに流行や世論が霞となり、あるべき姿を見失わせることがあるのだ。
■【まとめ】流行するAIやMaaS 本質を見失なうことのないように
苦言のような形になっているが、自動運転ラボはあくまで自動運転やMaaSに取り組む各社を応援しており、非難するつもりはさらさらない。AIやキャッシュレス決済、そしてMaaSも、大きな需要と可能性があるからこそ流行するのだ。
ただ、流行の類が時に本質を見失わせ、CS(顧客満足度)やUXから乖離したサービスに向かうことがある点や、継続性のない一過性のサービスでユーザーを落胆させることもある――という点はしっかりと警鐘を鳴らしていきたい。
【参考】MaaSについては「【最新版】MaaSとは? 読み方や意味・仕組み、サービス・導入事例まとめ」も参照。