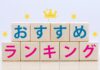ステアリングシステム開発などで高い実績を誇るトヨタグループの株式会社ジェイテクト(本社:愛知県刈谷市/取締役社長:佐藤和弘)の論文が、IEEEカンファレンスで最高位となる「Best Paper Award(論文賞)」を受賞した。
電動パワーステアリングを介して自動運転システムと運転者の意思をつなげるシステム「Pairdriver(ペアドライバー)」に関する論文で、人とシステムとの直感的なコミュニケーションを実現する技術だ。
自動運転化された自家用車は、人間による手動運転とコンピュータによる自動運転が混在し、人間とシステム間で操作権限を移行するオーバーライドが発生するが、Pairdriverはこのオーバーライドをナチュラルに実施するコア技術となり得る。
Pairdriverとはどのような技術なのか。ジェイテクトの最新の取り組みに迫る。
記事の目次
■IEEEカンファレンスの概要
人と自律システムの協調をテーマに会議開催
IEEE(米国電気電子技術者協会/Institute of Electrical and Electronics Engineers)は電気・情報工学分野の技術標準化を推進する機関で、国際会議の開催や標準規格の策定、教育的活動などを通じて技術革新を推進している。
IEEEは2024年5月、カナダで「Trustworthy Human-Autonomy Teaming=人と自律システムの協調性」をテーマに据えた「第4回IEEE国際ヒューマンマシンシステム会議(IEEE ICHMS 2024)」を開催した。
安全で信頼できる人間とシステムの認知科学、エンジニアリング、設計、検証可能なAIの決定のための技術的支援、信頼性のモデリング、測定、管理、複雑な社会技術システムにおけるAI対応の自律性の採用に対する信頼と障壁の基本的な問題など、脳に着想を得た自律システムのさまざまなスケールでの研究に焦点を当てた内容だ。
わかりやすく言い換えれば、人間とAI、コンピュータの信頼性ある協調をいかに図っていくか……といったイメージだ。
IEEEはこの会議に合わせ同テーマに関する論文を募集しており、その中で、ジェイテクトが応募した論文「The Haptic Link Enabling Driver-Automation Teaming」が最高位となる論文賞に輝いたのだ。ジェイテクトによると、論文賞の受賞は初という。
以下、ジェイテクトの取り組みを紹介していく。
▼Pairdriver|株式会社ジェイテクト
https://www.pairdriver.jtekt.co.jp/
■ジェイテクトの取り組み
操舵タスクを人とシステムが共有
ジェイテクトの論文「The Haptic Link Enabling Driver-Automation Teaming」は、同社が開発した「Pairdriver(ペアドライバー)」に関するものだ。
Pairdriverは、今後の自動運転市場の拡大を見据え、車の操舵タスクを人とシステムが共有して安全運転を実現する協調操舵システムとして2022年10月に発表したものだ。
クルマを思い通りに走らせたい人と自動運転システム、この2つのベクトルをゆるやかに調和するために生み出された。
電動パワーステアリング(EPS)を介して、自動運転システムと運転者の意思をつなげるという。ハンドル操作など運転者の入力トルクの情報と、車内外に取り付けられたセンサーによって検知・解析した車両運動の情報を統合し、その「システムの意思」をハンドルの振動や反力を通じて運転者に伝える。
「人とシステムとの直感的なコミュニケーション」による運転アシストにより、今までにない安全・安心を提供する運転環境を実現するとしている。
ハンドルから伝わる力触覚情報によって共通の理解を得る「Interaction」、互いの操作意思を推測しながら自動運転の次の行動を適応させる「Arbitration」、ドライバーの操作意思を走行目標の軌跡に組み入れる「Inclusion」の3つの思想からなる制御コンセプトによって構成されている。
これらのサイクルにより、ドライバーと自動運転システムが1つのチームのように機能する走行環境を実現する。
例えば、自動運転で走行中、システムが運転者の操舵を検知すると、操舵補助を伴いながらスムーズに運転者の操舵意思を反映し、システムと運転者の意思を同調させながら車両を操舵するという。
手動運転も可能な現行の自動運転車は、多くの場合手動運転と自動運転を切り替える際にスイッチ操作などの明確な切り替え動作が必要となっているが、Pairdriverは高度なセンシング技術と制御技術により、こうした動作を行うことなく自然かつ安全に自動運転から手動運転に移行することができるようだ。
ドライバーはハンドルを介してシステムの意図を「直感的」に感じることができる。また、ドライバーのハンドル操作に危険が及ぶと想定される際は、その操作にレジスタンス(反力)を与え、ドライバーが自ら運転したい時は寄り添うようなガイダンスを行うなど、システムがドライバーの操舵意図に応じた動きを行う。
ドライバーの操舵意図を逐一システムが読み取り、本来の走行ルートに組み入れ新たなルートを導き出すため、自動運転機能を保ったまま継続的に走行することもできるという。
ハードウェアであるステアリングが、ドライバーとシステムを同調するセンサーとして機能する発想だ。これまでの「ソフト・ハード一体型」とは異なり、ソフトウェアがハードウェアに依存しない仕組みを、独自の制御技術によって開発した。
これにより、必要とされる操舵特性をソフトウェアだけで構築することができ、さらには新たな機能も簡単に実装できるため、ステアリングアプリのソウトウェアフレームワークとしての役割を果たせるという。
カーメーカーやエンドユーザーが必要とする操舵特性をソフトウェアだけで構築し、フレキシブルかつ効率的に実装することができ、クルマの価値をソフトウェアで高めるSDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)時代に最適なソフトウェアソリューションになっているとしている。
ADASにおいてもPairdriverが活躍
既存のADAS(先進運転支援システム)においても、Pairdriverはステアリングに関わるアプリケーションのユーザビリティを向上させる。
車線逸脱警告機能・車線逸脱防止機能では、クルマが車線を逸脱しかけた際、その危険性をハンドルの振動によってドライバーに伝える。レスポンスの良いPairdriverのハンドル制御により、再現性の高い警告振動を実現し、走行状況に応じた振動の強弱によってより正確に状況を把握可能になる。
また、システムが車線逸脱の兆候を察知すると、その危険性をハンドルの反力によってドライバーに伝える。反力の強弱を自由に設計できるためリスクの度合いに応じた反力を伝えることが可能となり、高性能な舵角制御と協調操舵によって逸脱防止機能を維持しつつ、滑らかな操作介入を実現する。
こうした機能は、車線中央維持支援や車線変更支援としても有用だ。パワーアシスト制御の設計ノウハウを運転支援時のハンドリングフィールに活用し、自然で滑らかな制御介入をドライバーに伝達する。
駐車支援においても、クルマが障害物に近づいた際にハンドルの反力によってドライバーに注意を促すことができ、ドライバーの誤ったハンドル操作に対しカベのように強い反力を付加し、その危険性を伝えるという。
オーバーライドをスムーズに実行
自動運転車において、手動運転と自動運転との切り替えは神経を尖らせるものと思われる。例えば、運転席が2つ搭載された自動車にドライバーが2人乗っており、交互に運転操作を行う状況を想像してみてほしい。
停車状態で運転操作を交代するのであれば問題ないが、走行中に別のドライバーに運転を引き継ぐ、あるいは別のドライバーから運転を引き継ぐことを想像した場合、非常に神経を消耗する。どのタイミングで制御権限が相手から自分に移ったのか、あるいは自分から相手に移ったのかあいまいであり、速度を維持するにはどの程度ペダルを踏み込めばよいのか分かりにくいためだ。
こうしたオーバーライドの難しさは、自動運転システムが相手でも同様だ。スイッチを押せば自動運転システムが稼働し、あるいは自動運転をストップするにしろ、シームレスに制御を移行するのは難しいものがある。
こうした際に、ステアリングがセンサーとなることで自然なオーバーライドが実現する。ステアリングを握ることでヒトとシステムが意思疎通し、スムーズな制御の移行を実現するのだ。Pairdriverは、将来の自家用自動運転車の在り方を示しているのかもしれない。
【参考】オーバーライドについては「自動運転における「オーバーライド」とは?「切り替え」という意味」も参照。
自動運転における「オーバーライド」とは?「切り替え」という意味 https://t.co/7YCILc1F7w @jidountenlab #自動運転 #オーバーライド #切り替え
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) September 19, 2021
■自動運転とステアリング
格納式ステアリングも話題
自動運転におけるステアリング関連のトピックと言えば、これまでは「格納式ステアリング」が話題の中心だった。
手動運転時は平時と変わらないが、自動運転時にはダッシュボードにステアリングが格納され、ゆとりのある車内空間を演出する仕掛けだ。
ステアリング開発を軸とするジェイテクトも、当然こうした格納式ステアリングを開発している。将来技術として開発を進めているステアバイワイヤや員ホイールモーターの協調技術を盛り込んだコンセプトモデル「Future Concept Vehicle」において、自動運転化を見越したステアリング格納機能(Retractable Column Module)を披露している。
こうしたステアリング格納式は、独アウディなどもコンセプトモデルで採用している。自動運転時代のスタンダードとなるか注目の技術だ。
合わせて、今回のPairdriverのように、ステアリングをセンサー化する技術も非常に興味深いものだ。人間とシステムが物理的に触れ合う接点であり、かつ自動車の制御を担うステアリングをHMI(ヒューマンマシンインタフェース)として活用する素晴らしいアイデアだ。
ステアバイワイヤシステムにより自由度が増したステアリングは今後さらに進化し続け、単純なハードウェアから脱却し、スマートステアリングとしてさまざまな機能を持ち始めることになりそうだ。
【参考】アウディのステアリング格納機能については「独アウディ、「自動運転時はハンドル格納」の方針変わらず」も参照。
【参考】ジェイテクトのステアリング格納機能については「自動運転時代は「ハンドル格納機能」がアツい トヨタ系ジェイテクトの考え方」も参照。
自動運転時代は「ハンドル格納機能」がアツい トヨタ系ジェイテクトの考え方 https://t.co/I8BFWWiYoq @jidountenlab #自動運転 #ハンドル #トヨタ
— 自動運転ラボ (@jidountenlab) October 9, 2019
■【まとめ】Pairdriverは自動運転時代のHMIとして有用
ハンドル・ステアリングをセンサーとして活用し、自動運転時代のHMIとして機能させる興味深い技術だ。タイヤやヘッドランプ、フロントガラスなど、自動車を構成する各パーツも、次世代モビリティに向けスマート化が図られ、新たな機能を搭載していくことになるのかもしれない。
自動運転と協調し、その精度や効用を高めていく存在として、こうした各パーツの進化にも引き続き注目していきたい。
【参考】関連記事としては「ジェイテクト、米開催の展示会で自動運転技術への取り組みなど紹介」も参照。