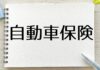自動運転分野で世界の先頭を走るグーグル系Waymoが、積雪地域への対応に挑戦しているようだ。全天候型の自動運転技術を構築し、他社との差をさらに広げていくのだろうか。
Waymoの取り組みとともに、雪国における自動運転の開発状況に触れていこう。
記事の目次
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |
| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |
| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |
| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |
| 編集部おすすめサービス<PR> | |
| パソナキャリア |  |
| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |
| タクシーアプリDiDi |  |
| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |
| MOTAカーリース |  |
| お好きな車が月々1万円台から! | |
| スクエアbang! |  |
| 「最も安い」自動車保険を提案! | |
■Waymoの取り組み
積雪地帯における自律走行にもアプローチ
Waymoによると、同社の自動運転システムは雨や霧、砂嵐、氷点下の気温でも問題なく走行することができるという。米国をはじめ、世界中の多くの都市にサービスを展開していく上では積雪地帯などへの対応も必要となるが、雨天などに対する体系的かつ科学的な取り組みと同様のアプローチで、雪の多い冬の天候にも対応できる能力を向上させている。
Waymoの安全性を重視した方法論には、「課題の理解」「一般化可能なソリューション設計」「能力の厳格な検証」「責任ある規模拡大」の 4 つの主要ステップを踏むという。
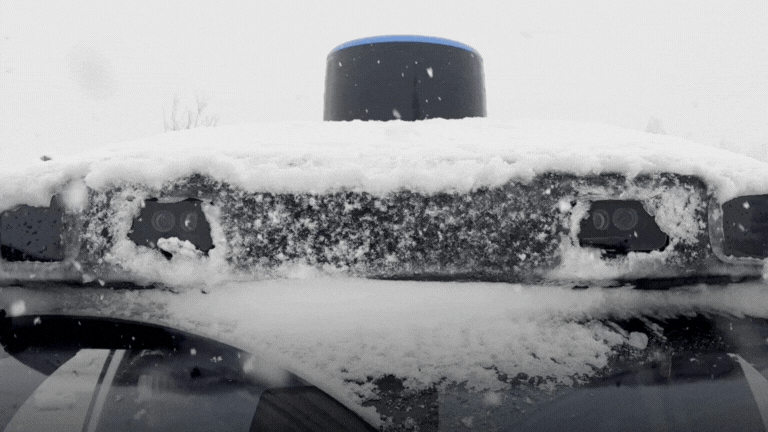
課題の理解
雪は単一の現象ではなく、人間や自動運転システムにさまざまな影響を及ぼす条件の集合体であり、大気の状態はかすかな積雪から完全なホワイトアウトまでさまざまで、路面も雪に覆われていたり凍結していたりする場合もある。さらに、路肩の積雪などの環境要因が状況を複雑化させる。
Waymoは、ニューヨーク州北部やミシガン州アッパー半島、シエラネバダ山脈を定期的に走行するなど、米国内でも特に降雪量の多い地域でシステムの進化に取り組み、数万マイルに及ぶ走行実績を積み重ね、幅広い冬の天候に対応できるようトレーニングすることを可能にしたという。
一般化可能なソリューション設計
Waymoは、霧のサンフランシスコも雪のデンバーも多様な状況下で同じように走行できる単一の自動運転システムの構築を進めている。
第6世代のドライバーは、1億マイルを超える完全自動運転の経験に基づいて最先端のハードウェアとAIを組み合わせることで、より過酷な気候の都市でも完全自動運転の運用に適応し、維持することができるという。
カメラ、レーダー、LIDARといった各センサーが視野を補完しあうことで悪天候を克服し、巧妙なエンジニアリングと加熱素子を用いた自動クリーニングシステムによって常にセンサーを清潔に保ち、車両が停車することなく継続的にサービス提供できるようにしている。
冬の条件をナビゲートするために設計された、より豊富な入力と高度な機能を備えた既存モデルをベースにした最先端AIは、雪やぬかるみ、氷、通常の路面を区別することができる。
しっかり判別可能にすることで見たもの・感じたものに基づいてナビゲートできるようになり、他の道路利用者からの洞察も交え通行止めや迂回、変化する路面状況などに適応できるよう設計している。
システムがトラクションの低下を検出すると、速度、加速、ブレーキを自動的に調整する。各車両は、モバイル気象ステーションとしても機能し、データを収集して独自の運転判断を通知し、他の車両と情報を共有する。

能力の厳格な検証
Waymoは、実走行やクローズドコースにおけるテスト、大規模シミュレーションを通じて、汎用性の高いシステムを検証している。デトロイト、デンバー、ワシントンD.C.といった降雪都市をはじめとする各地で冬の気象条件への理解を深め、システムの性能を検証している。
クローズドコーステストでは、制御された環境下でシステムを限界までテストし、氷上でのトラクション喪失といった極端なシナリオを認識し、対応する方法を学んでいる。
雪解け後も、シミュレーションを活用することで年間を通して学習を進めており、ニューオーリンズが経験した100年に一度の降雪のような稀で異常なシーンにも備えることができるとしている。
責任ある規模拡大
技術検証が終了すれば、地域の状況に基づいた車両の運行時期に関する明確なガイドラインを定め、サービスを拡大する。規模拡大に伴い、氷点下でも車両を清潔に保ち充電を維持する点や、乗客の体験を最適化する点に至るまで、冬季サービスに対応するための業務も改善していく。
冬の天候は複雑だが、乗客が最も必要としている時に信頼性の高いサービスを提供することに尽力する方針としている。

寒冷地域への進出も視野に
Waymoはこれまで、アリゾナ州フェニックス、カリフォルニア州サンフランシスコ、ロサンゼルス、テキサス州オースティン、ジョージア州アトランタで自動運転タクシーを商用化しているが、これらはいずれも比較的暖かい地域だ。
自動運転に対する各州の規制や需要などもあるが、天候面も考慮したうえでエリアを選定しているものと思われる。
今後は、フロリダ州マイアミやワシントンD.C.、ネバダ州ラスベガス、カリフォルニア州サンディエゴ、テキサス州ダラス、ワシントン州、コロラド州デンバーなどに順次拡大していく計画を発表しているが、この中で、デンバーは雪が多いことで知られている。シアトルは緯度の割に温暖だが、路面が凍結してスケートリンクのようになることもある。
徐々に天候面におけるODD(運行設計領域)も拡大していく計画のようだ。Waymoの次世代となる第6世代の自動運転システムは、ミシガン州やニューヨーク州北部、シエラネバダ山脈などにおける長年の冬季実証を踏まえて設計されており、より過酷な気候下でも自律走行できるよう設計されているという。
【参考】関連記事は「Google/Waymoの自動運転戦略まとめ ロボタクシーの展開状況は?」も参照。
自動運転車両がモバイル気象ステーションに?
Waymoは自動運転開発プロジェクトの初期段階から天候の影響・理解に注力しており、天候の影響について「濡れた道路はカメラが反射して認識する可能性がある」「霧、靄、雨などの結露はセンサーデータを変化させる可能性がある」「水滴、汚れ、氷は人間の運転者のフロントガラスを汚すのと同様にセンサーの表面を汚す可能性がある」「濡れた路面や凍った路面は滑りやすく、摩擦が減少する」といった可能性を挙げている。
カメラやレーダー、LIDARを搭載したセンサースイートは、窓に付着する雨滴を利用してさまざまな気象状況を分類するなど、気象視程センサーから得られる高品質な地上データと組み合わせることで気象視程に関する定量的な指標を生成するという。
車両周囲の天候をリアルタイムで定量的に分析し、霧や雨などの天候状況を把握し、その強度を判別できることで、Waymoの各車両が自律型の「モバイル気象ステーション」として機能する。
既存の気象観測所や衛星、気象レーダーから遠隔的に観測される気象データは走行エリア内を網羅していないが、自動運転フリートを移動式気象観測所として運用し、時空間にわたる気象に関する数百万点のデータポイントを組み合わせることでリアルタイムの気象マップを作成することができるという。
自社の自律走行に役立てるだけでなく、長距離輸送を行う配送パートナーなどに情報提供することなども計画していたようだ。
■雪道における自動運転
雪道の運転は人間でも難しい
降雪・積雪地域の運転は、人間のドライバーでも難易度が格段に上がる。降雪時は雪で視界が遮られ、ひどいときはほぼ視界ゼロのホワイトアウトに見舞われることもある。吹雪の中郊外を走行中、前走車両のバックランプが見えなくなった時の不安はなるべく味わいたくないところだ。
車道は積雪により区画線や路側帯、路肩の縁石なども判別できなくなる。路肩を含め一面真っ白で、完全に車線を見失うこともある。積雪により車道がすり鉢状になることも珍しくない。
住宅街などでは、マンホール部分だけ熱で雪が解け、数十センチ陥没していることもある。狭い道路は、路肩の雪山により幅が狭まって一方通行と化すことも多い。交差点も路肩の雪山によって見通しが悪くなる。
路面は、一見積雪がなく乾燥した道路に見えても、ブラックアイスバーンと化していることもある。積雪状態でも、気温などにより摩擦係数は大きく変化する。轍や凹凸ができていることもスタンダードだ。
人間のドライバーでも、常に注視しながら刻々と変化する状況に柔軟に対応しなければならないのだ。
将来的には自動運転が雪道走行を克服?
では、自動運転システムの場合はどうなのか。降雪時や見通しの悪い交差点など、物理的な視界の悪さは人間よりもセンサーの方が優れている可能性がある。限界はあるだろうが、LiDARやカメラ、レーダーなど異なる種類のセンサーを駆使することで、人間が苦手とするシーンも克服できるのかもしれない。
車線が見えずとも、高精度3次元地図などで自車位置を正確に推定できれば、走行すべきラインを見失わずに安全を保てる。
微妙な起伏や摩擦の変化など刻一刻と変わる状況に柔軟かつリアルタイムにどこまで対応できるかについても、センサーとAIの進化で対応可能な領域と言える。
ハードルが高いのは間違いないが、将来的には人間よりも自動運転・コンピュータの方が雪国における走行を克服できるのではないだろうか。
■積雪・関連地域における各社の取り組み
AvrideやMOIAなどが実証
自動運転による雪道走行に関しては、米Avrideも力を入れている。同社はロシアのYandexから独立したスタートアップで、Yandex時代は寒冷地であるモスクワをはじめとした各所で降雪・積雪時の実証を行ってきた。
ノイズを最小限に抑え周囲の3D画像を作製する方法を学習させ、大雪の中でも周囲の物体を検出し、正しい車線にとどまりながら走行したり、横断歩道を認識したりすることができるよう改良を重ねている。
Avrideとなってからも、自動配送ロボットの雪道走行実証などを行っている。高い地上高でスタックを防ぎ、低速時に大きなトルクを発揮することで氷上でもトラクションを維持するなど、さまざまな観点から実証を進めているようだ。
【参考】関連記事は「Waymo最大のライバル!?ロシアYandex、自動運転の実力」も参照。
欧州では、フォルクスワーゲングループのモビリティテック企業MOIAが雪道の自動運転実証に力を入れているようだ。
同社は米オースティンや独ミュンヘン、ハンブルクなどでID. Buzz ADの公道実証を積み重ねているが、ノルウェーの首都オスロでの実証にも着手した。
雪や視界不良の状況下におけるセンサーの性能や、雪に覆われた交通標識や道路標示との相互作用、 低温時の一般的な運転ダイナミクス――に重点を置き、冬季をはじめとした過酷な気象条件下でも安全に運転できる性能を獲得し、欧州や北米における長期的かつ商業的成功を実現する構えだ。
国内ではBOLDLYが注力
国内では、ソフトバンクグループのBOLDLYが北海道上士幌町や東川町など各地で雪道における自動運転バスのサービス実証を進めている。
ARMAによる定期運行を行っている上士幌町では、2024年5月に自動運転レベル4認可を取得し、ルートの一部で無人走行実証にも着手している。冬季間における無人運行の有無は不明だが、国土の半分を豪雪地帯が占める日本でも、雪道対応を避けて通ることはできない。
除雪作業の自動運転化を図る取り組みも進められている。ブレード付き除雪車やロータリ除雪車の自動化においては、センチメートル級の自車位置推定技術とともに、ブレードやロータリ機構の自動化も行う必要がある。排雪時においては、自動運転ダンプとの連携も欠かせないだろう。
すでに除雪車の運転支援システムの開発やロータリ除雪車の投雪作業自動化、梯団走行の自動化、無人自動除雪ドローン実証など、さまざまな取り組みが各地で進められている。
こうした技術が実現すれば、無人の自動運転除雪車が作業し終えた路線を自動運転バスが走行する――といった流れも確立されるかもしれない。
【参考】関連記事は「「雪道の自動運転」で日本が世界をリード!実証続々」も参照。
■【まとめ】自動運転車のポテンシャルはホワイトアウトも克服?
現状の技術では、刻々と変化する降雪・積雪路面などに対応するのは不完全かもしれないが、自動運転車であればホワイトアウト状態でも走行可能になるポテンシャルを有していると言える。
センサー技術や自車位置推定技術など、さらなる向上が欠かせないが、リーディングランナーであるWaymoはどの段階で克服し、実用化に結び付けていくのか。今後の開発動向に注目だ。
【参考】関連記事としては「自動運転が可能な車種一覧(タイプ別)」も参照。